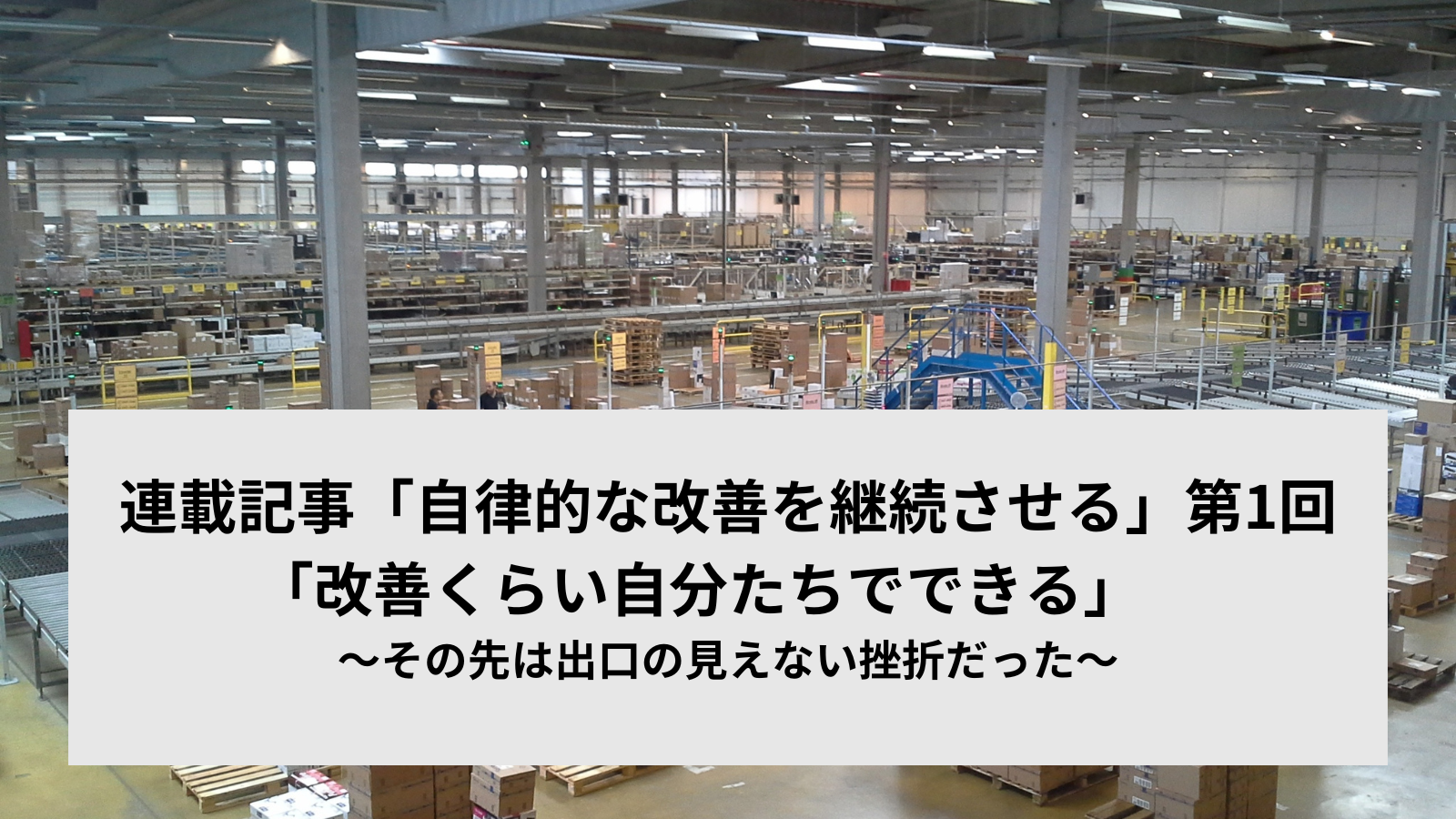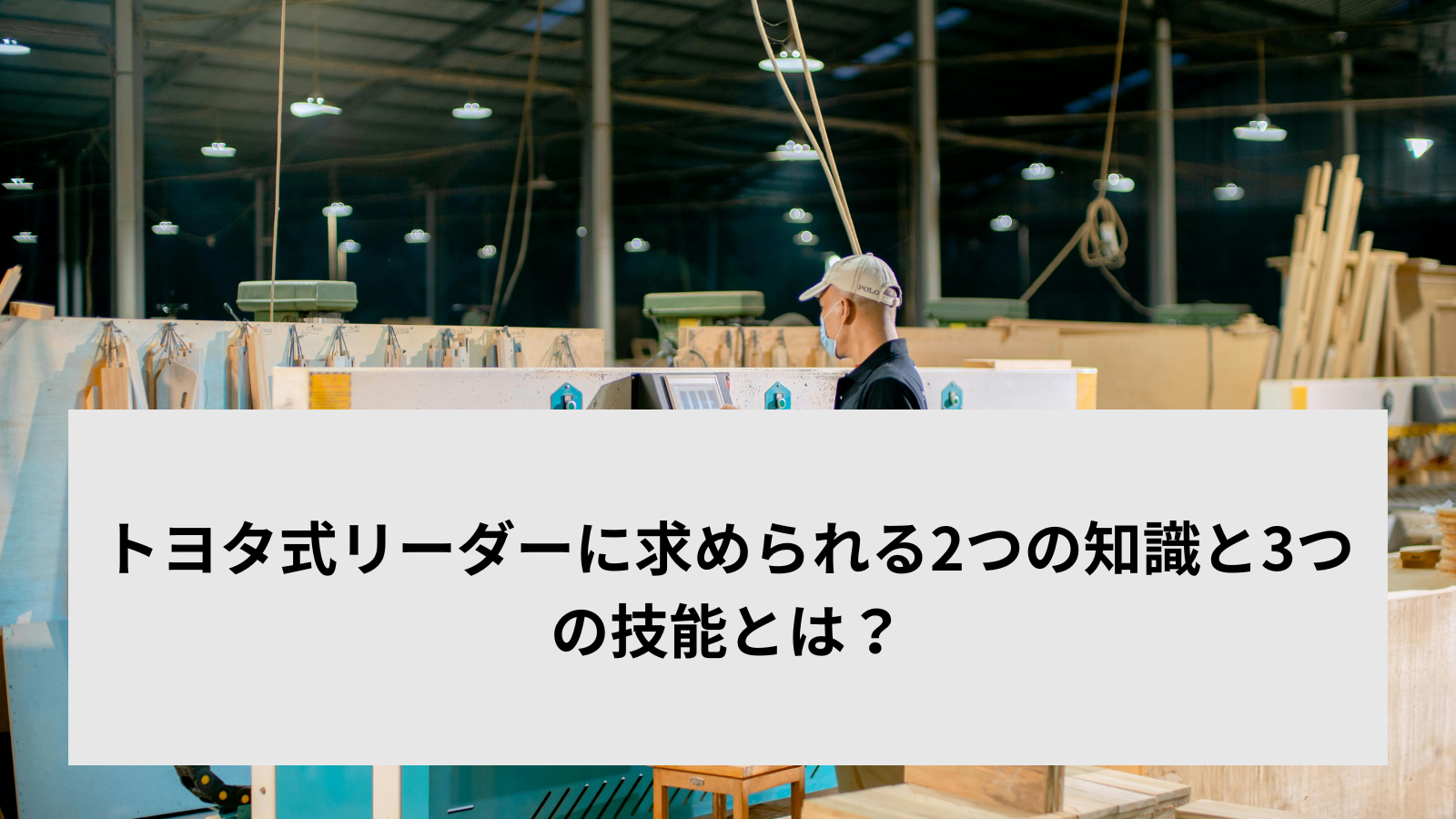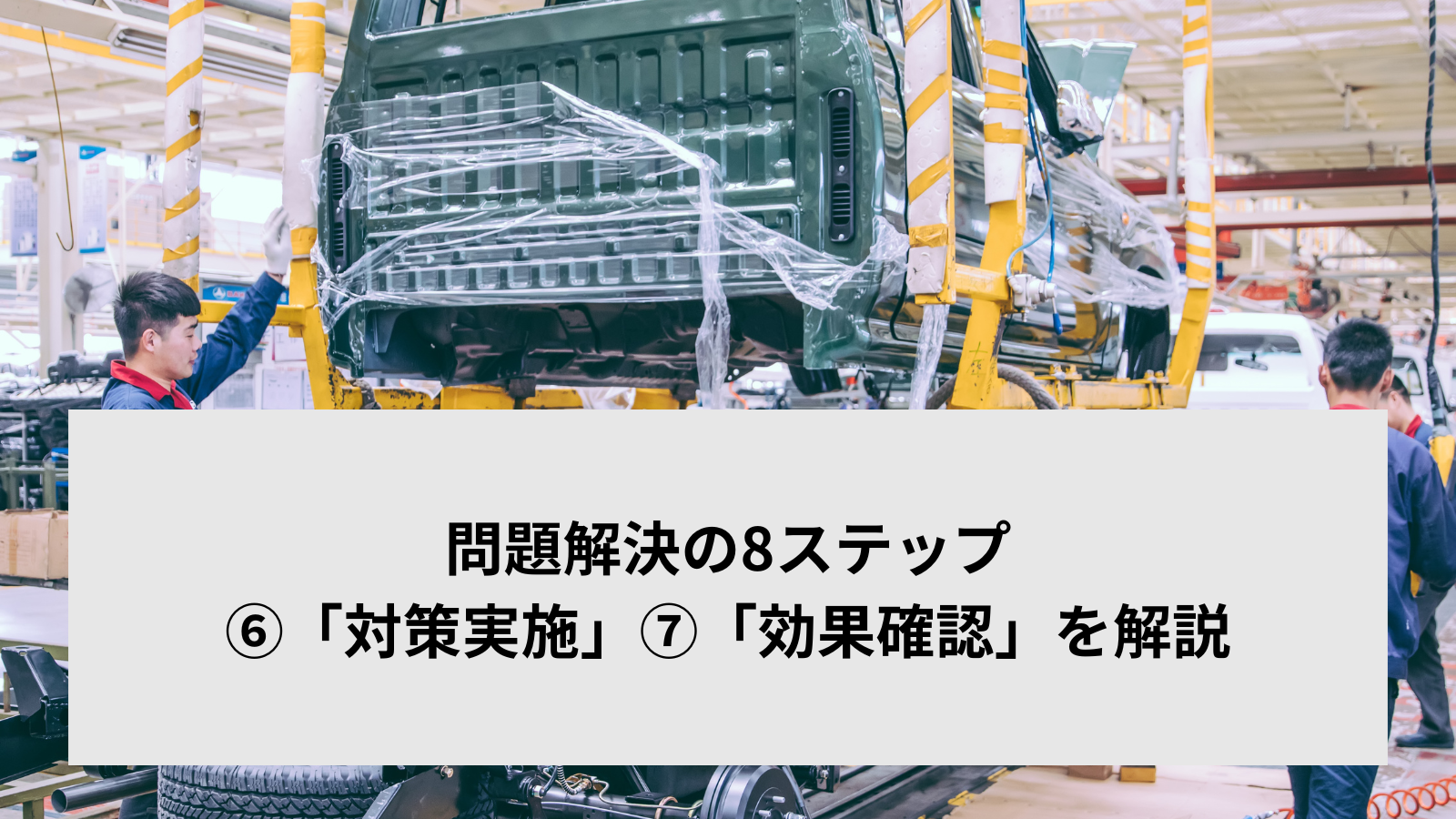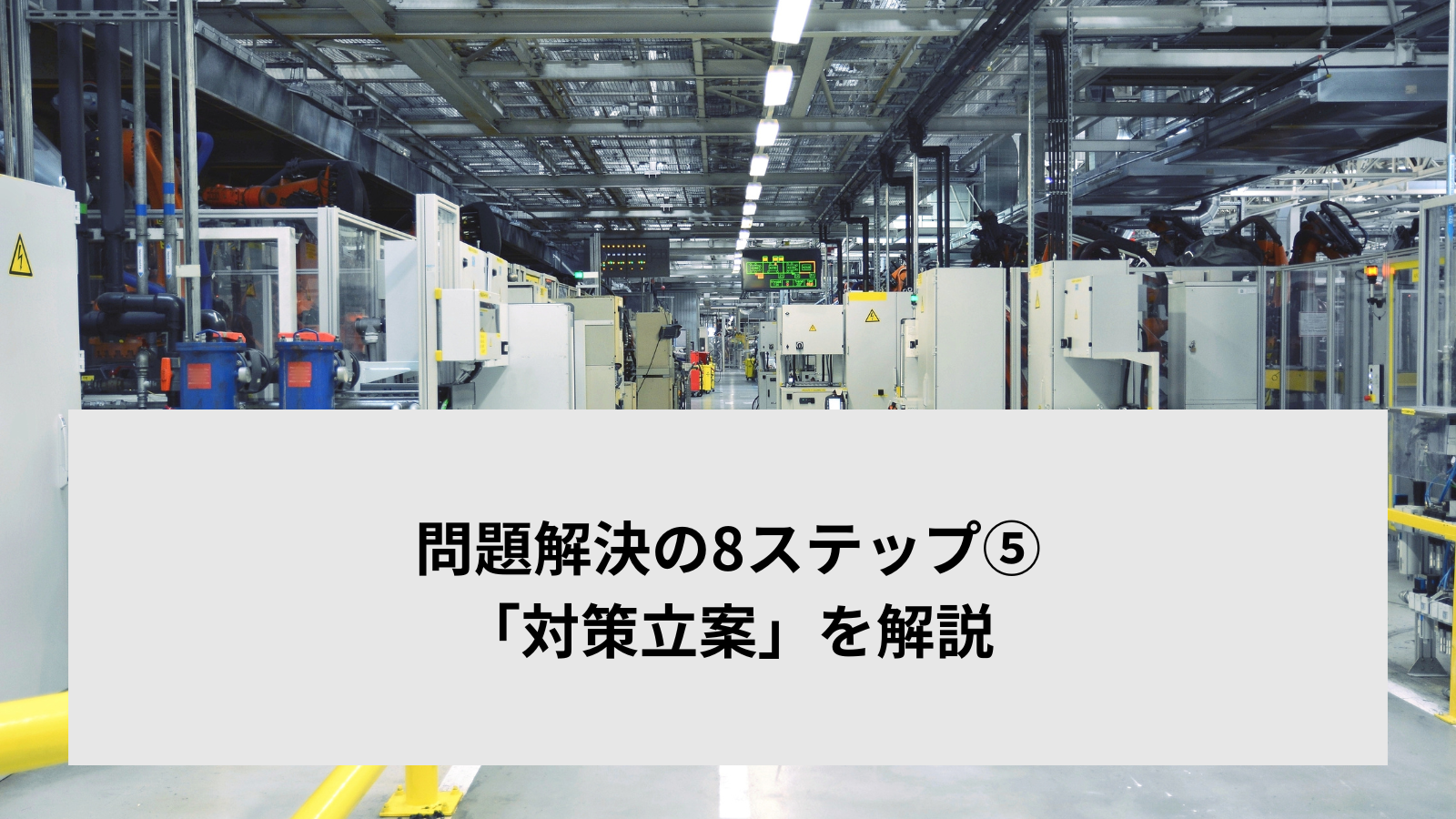OJT
連載記事「自律的な改善を継続させる」第1回「改善くらい自分たちでできる」 ~その先は出口の見えない挫折だった~
自律的な改善を継続させる人づくり・しくみづくり・風土づくりへの道として、ある企業を題材に計4回に分けて記事を公開します。
今回は第1回として、「自分たちで改善なんて出来る」と思って進めていた現場に限界を感じ、挫折を感じた部長のエピソードをお送りします。
次回以降の連載記事です。
第2回 反発、無関心な現場を変えたアプローチ ~プロジェクト成功に欠かせない、現場巻き込みの手法とは~
第3回 「25年変われなかったのに……」 〜諦めを覆した問題解決の8ステップの秘密は「層別」にあり!~
第4回 改善は生産現場だけじゃない!~販売スタッフの行動も数値化 ムダ取りから接客を充実~
最高品質の中心を目指すものづくりへ
ここは明治時代から続く老舗の菓子メーカー。素朴な味わいの製品が全国的にも知られているが、その品質が一定ではないことに、経営陣は密かに危機感を抱いていました。
経営陣
「右肩上がりに業績が拡大する中、とにかく必要な生産量を達成することに精一杯。良品の枠内にあっても、形や大きさ、厚さ、焼き具合、味にばらつきがあり、品質が一定ではなかったのです。」
「また、私たちの商品は干菓子で賞味期限も長いですが、生ものを原料に使っているため、実際には時間とともに風味が落ちていってしまう。生産管理を徹底し、常に鮮度の高い、最高品質の状態でお客様に提供すべきであると方針を定め、『量から質へ』という体質改善に動き出しました。」
「そのために必要と考えたのは、現場が主体となって、最高品質という基準の中心に近づけていくものづくりです。」
これまでの同社は、スタッフ部門が決めたことを製造現場はそのまま受け入れてやるだけという中央集権的な体制でした。しかし、こうした″工程で品質をつくり込む″ものづくりへの転換には、現場で自律的に課題解決できる人材・組織への脱皮が不可欠だったのです。
「良い製品」とはどんなもの?
このような新たな方針に、製造部長は戸惑いました。
製造部長
「経営陣から、製品の品質をもっと良くしてくれと。しかし、良品の基準はちゃんとあって、その範囲に入るように製造しているのだから問題ないのでは?と突き返すと、基準の話をしているのではない、もっと良い製品をつくるように取り組んでくれという。私も困って『では、良い製品とは一体何ですか?』と禅問答のように混ぜ返したりして、全然会話が噛み合わない。」
「例えば、良品の大きさを基準の±10mmからもっと絞ろうとか、設計部署を通して基準を厳しく変えてくれれば製造部は従いますと伝えると、会長からはそういうことを言っているのではない、と正されてしまう。」
「今思えば、現場自身がもっと高みを目指して自律的に、能動的に良いものづくりに向かいなさいということなのですが、はじめは理解できていませんでした。」
″飲みたい水″に変わるまで
手探りながらも製造部長が先頭に立ち、ものづくりの転換にもがいている最中に、経営陣がOJTソリューションズのパンフレットを見せてきたことがありました。
経営陣
「トヨタ出身のトレーナーが指導するということで『生産効率重視』のイメージがあったのですが、営業さんに話を聞いてみると現場の『人づくり』を大切にしているとわかり、我々の求めるものと合うのではないかと感じました。」
参考程度の軽い気持ちで紹介しましたが、製造部長の答えはきっぱりと「ノー」でした。
製造部長
「正直なところ、『コンサルティング』の類にマイナスイメージを持っていましたし、また、『今のお前のやり方では駄目』と言われているような悔しい気持ちもありました。」
「それまで品質向上を目指して一緒にやってきた課長たちもいましたので、もう少し自分たちの力でやらせてほしいとお願いしました。」
経営陣は製造部長の意向を尊重しました。
経営陣
「嫌々やってもらっても意味はない。OJTソリューションズのサービスが自分たちにとって必要な″飲みたい水″になるまで待とうと考えたのです。」
口を開けて待っていた挫折
製造部長たちの独自の活動は5年の歳月を重ねました。しかし、残念ながら成果を得ることはありませんでした。
チームを作ってテーマを決め、QC手法を試したものの、書籍などから得られる知識だけでは″七つ道具″(品質管理における改善やデータ分析の手法のこと)を自分たちの現場に当てはめられず、活用できませんでした。「量から質への体質改善」は遠く、日々の生産量を何とかこなす状態が続いていました。
また、現場主体のものづくりに意識を変革することもできませんでした。製造部長は当時を思い返して以下のように話をしています。
製造部長
「例えば、若手の検査担当者に、この数字は何のために取っているのかと尋ねると、わかりませんと平気で答える。指示されたことの意味を知ろうともせずにただやっているだけ。そういった意識が現場に蔓延していた。私も現場出身。自分たちで工夫を重ねてつくることは楽しかったし、できたものには自信を持っていた。それに比べて、今の若い子たちは仕事を面白いと思ってくれていないのではないかと、相当悩みました。」
製造部長はいつからか、自力での取り組みに限界を感じるようになっていました。
経営陣は特に、現場のマインドが変わっていないことを問題視していました。
経営陣
「私たちが目指しているのは、夢と誇りを持っていきいきと働きながら、一人ひとりが最大限の能力を発揮する『人間性尊重企業』。なのに、できていない。中央集権的な体制は相変わらずで、考えることを奪ってしまっている現状に、これで良いのかと。部長以上が集まる朝会議でそんな話になった。指摘されて、製造部長はかなり落ち込んだと思います。長年続いたチャレンジがついに完全に行き詰まり、現場の課長たちも含めて、喉がカラカラの″飲みたい水″の状態になっていました。」
うつむく製造部長の目の前に差し出されたのは、5年前に断ったOJTソリューションズのパンフレットでした。
連載記事はこちらから。
第2回 反発、無関心な現場を変えたアプローチ ~プロジェクト成功に欠かせない、現場巻き込みの手法とは~
第3回 「25年変われなかったのに……」 〜諦めを覆した問題解決の8ステップの秘密は「層別」にあり!~
第4回 改善は生産現場だけじゃない!~販売スタッフの行動も数値化 ムダ取りから接客を充実~
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタ式リーダーに求められる2つの知識と3つの技能とは?
2025.09.26 -
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介
2025.09.05 -
問題解決の8ステップ⑧「標準化・再発防止」を解説
2025.08.22 -
問題解決の8ステップ⑥「対策実施」⑦「効果確認」を解説
2025.08.15 -
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
2025.08.08 -
問題解決の8ステップ④「要因解析」を解説
2025.08.01

PAGE
TOP