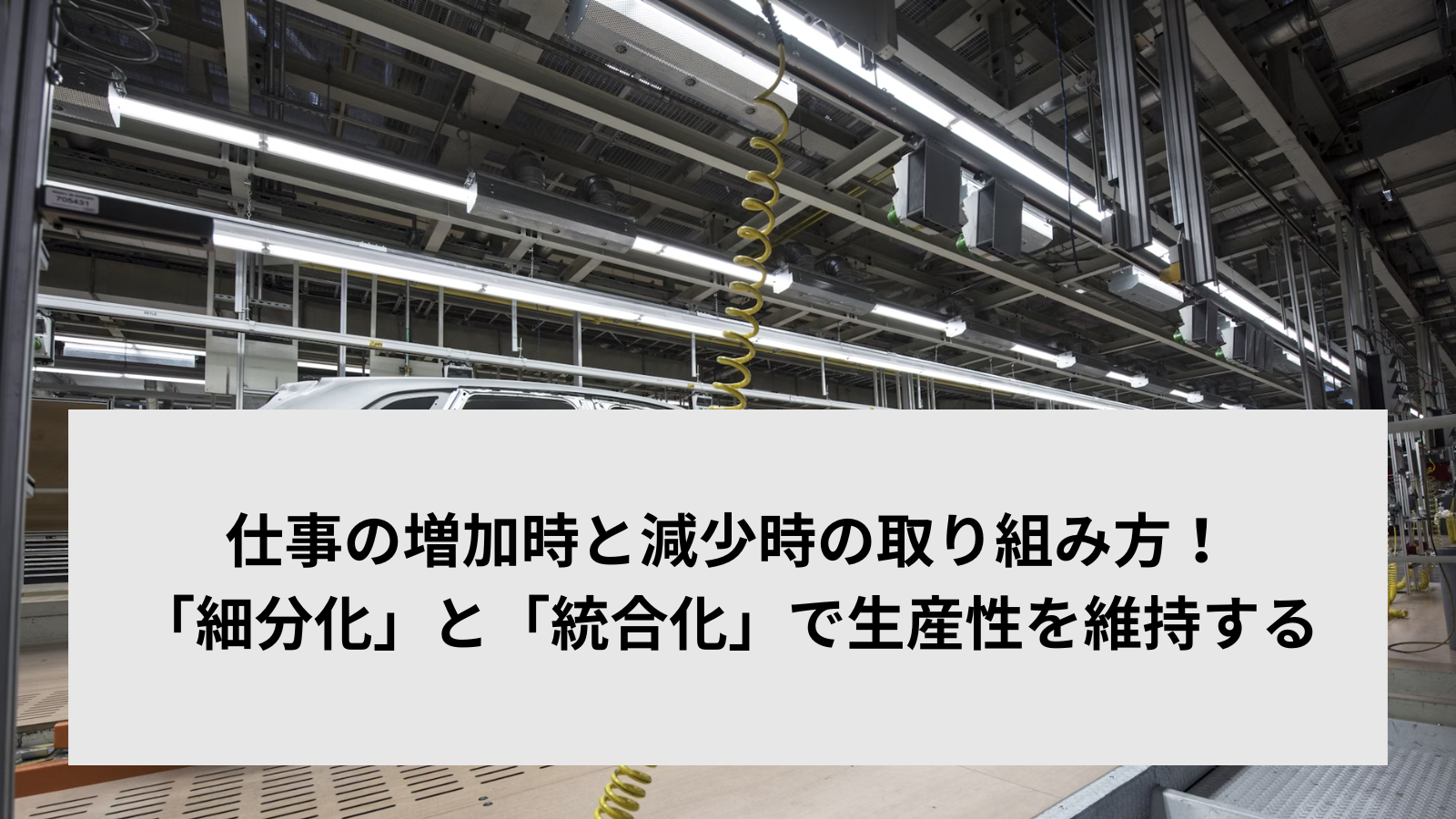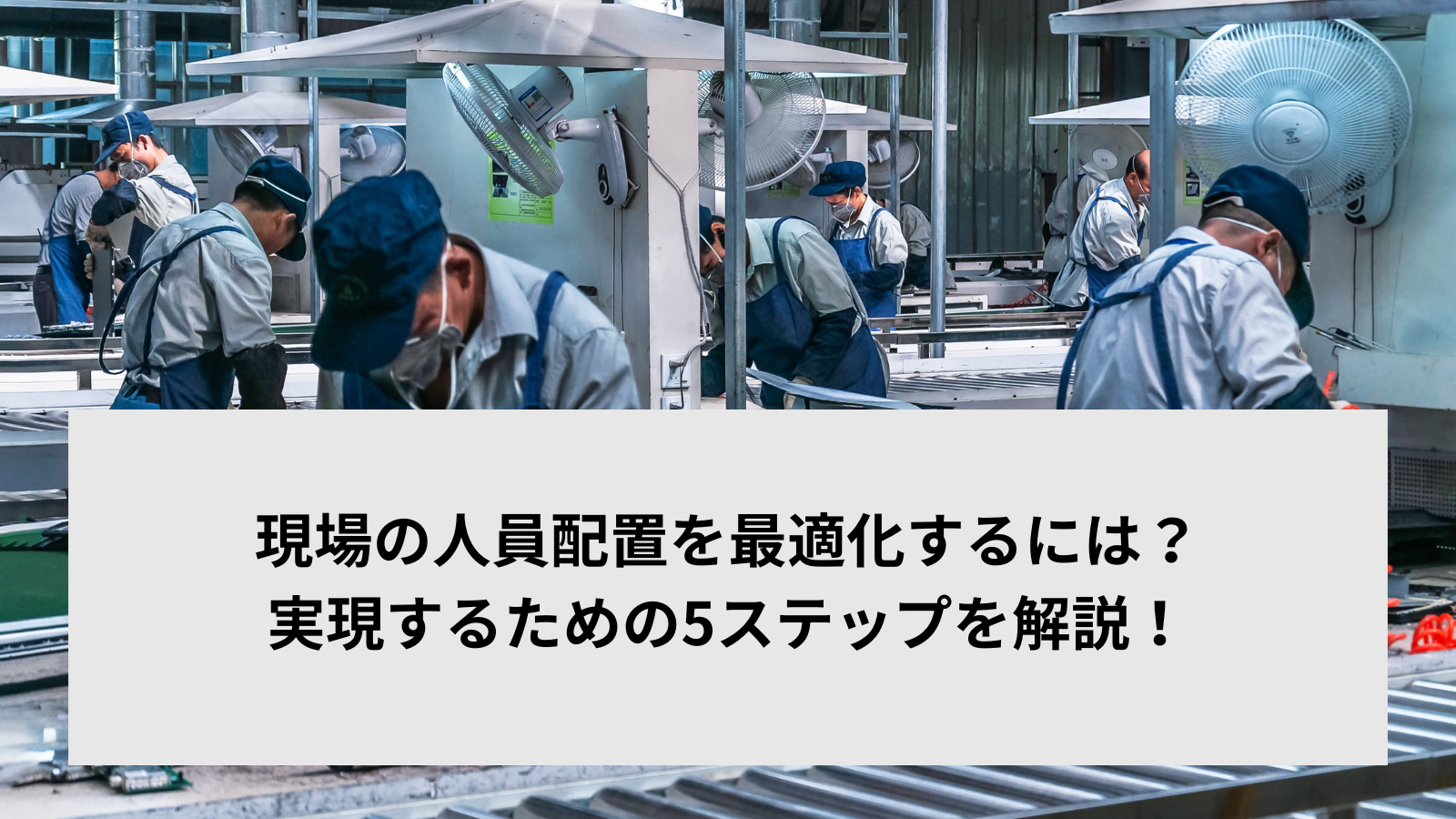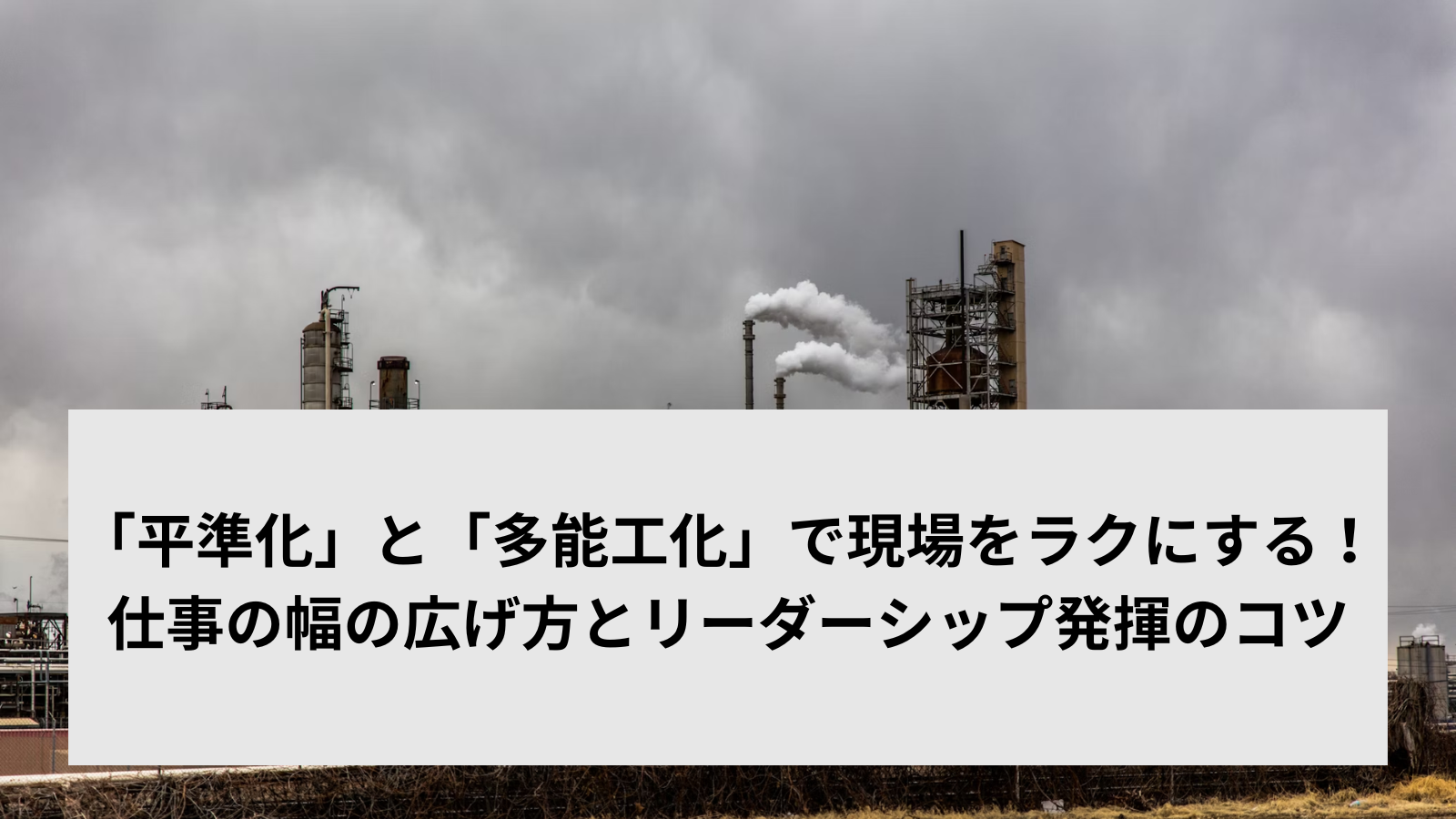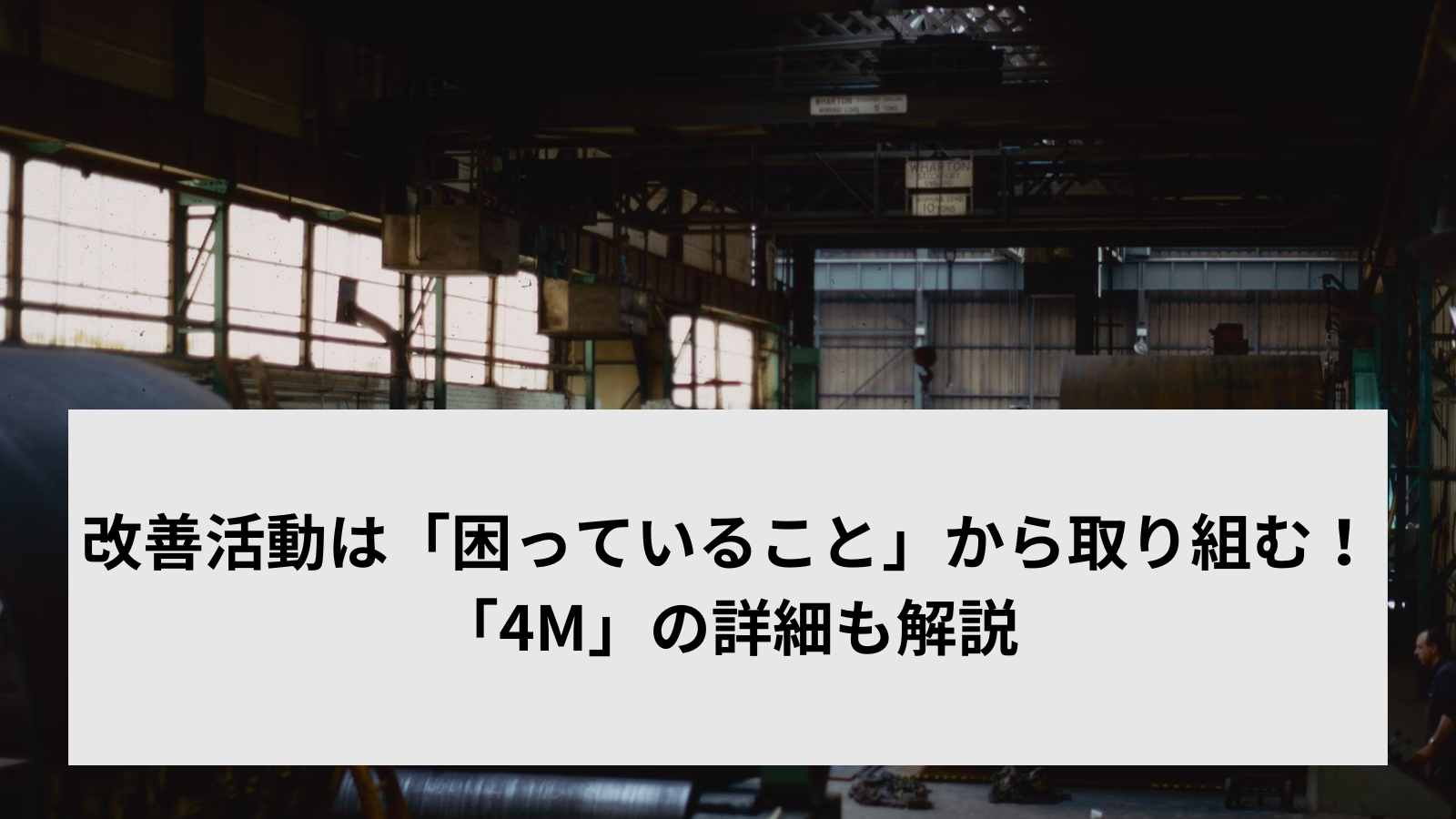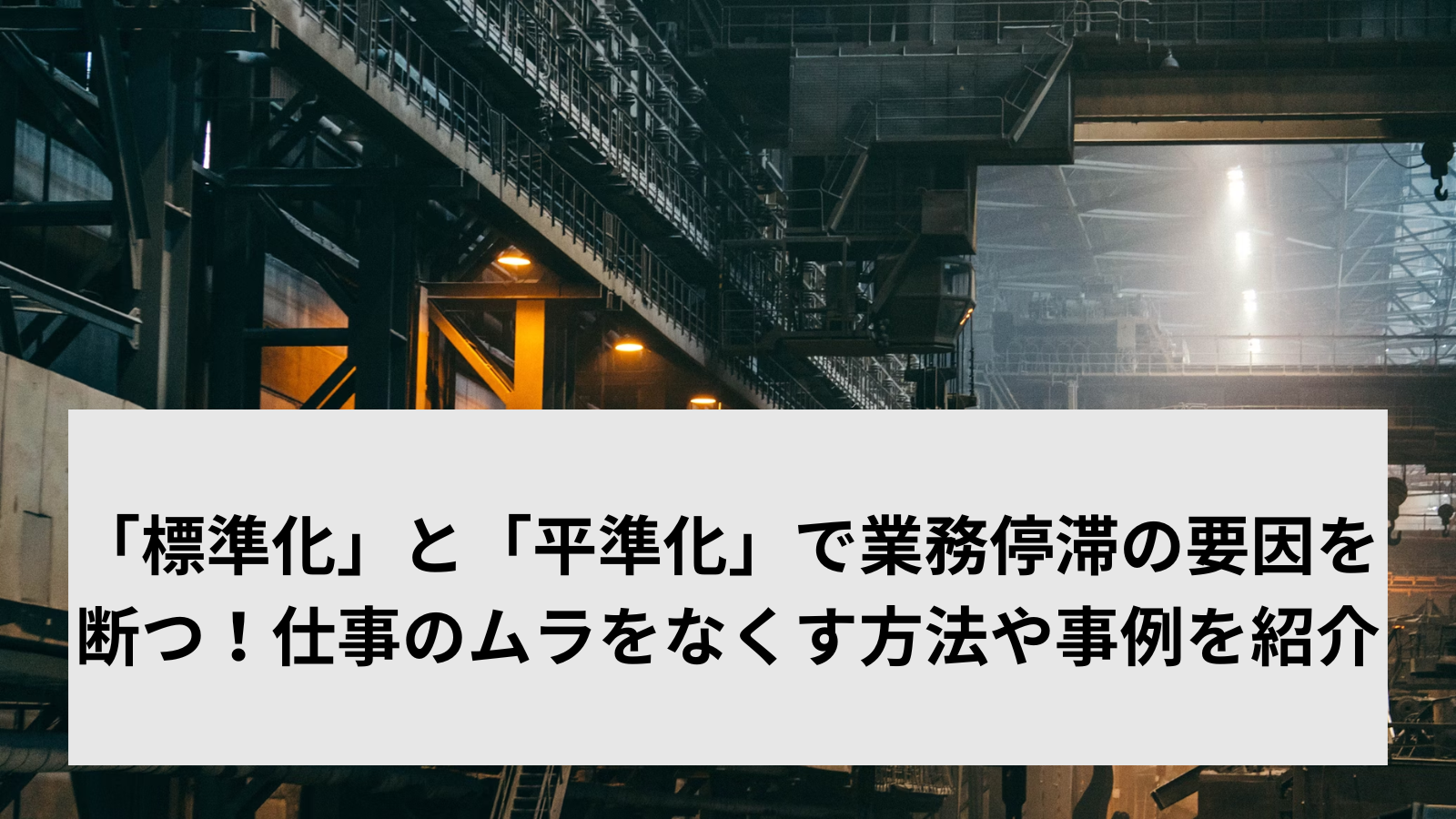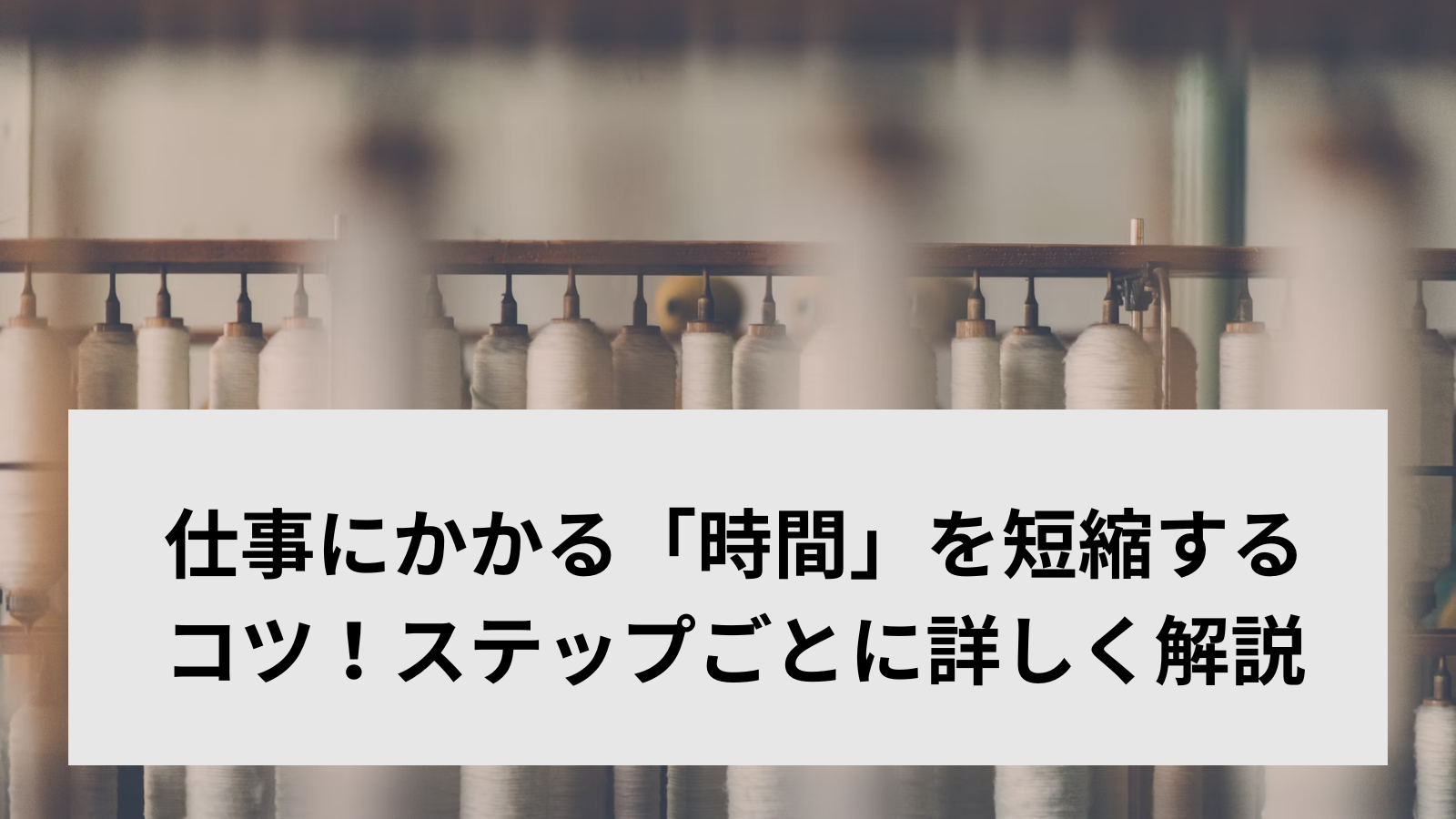生産性向上
仕事の増加時と減少時の取り組み方!「細分化」と「統合化」で生産性を維持する
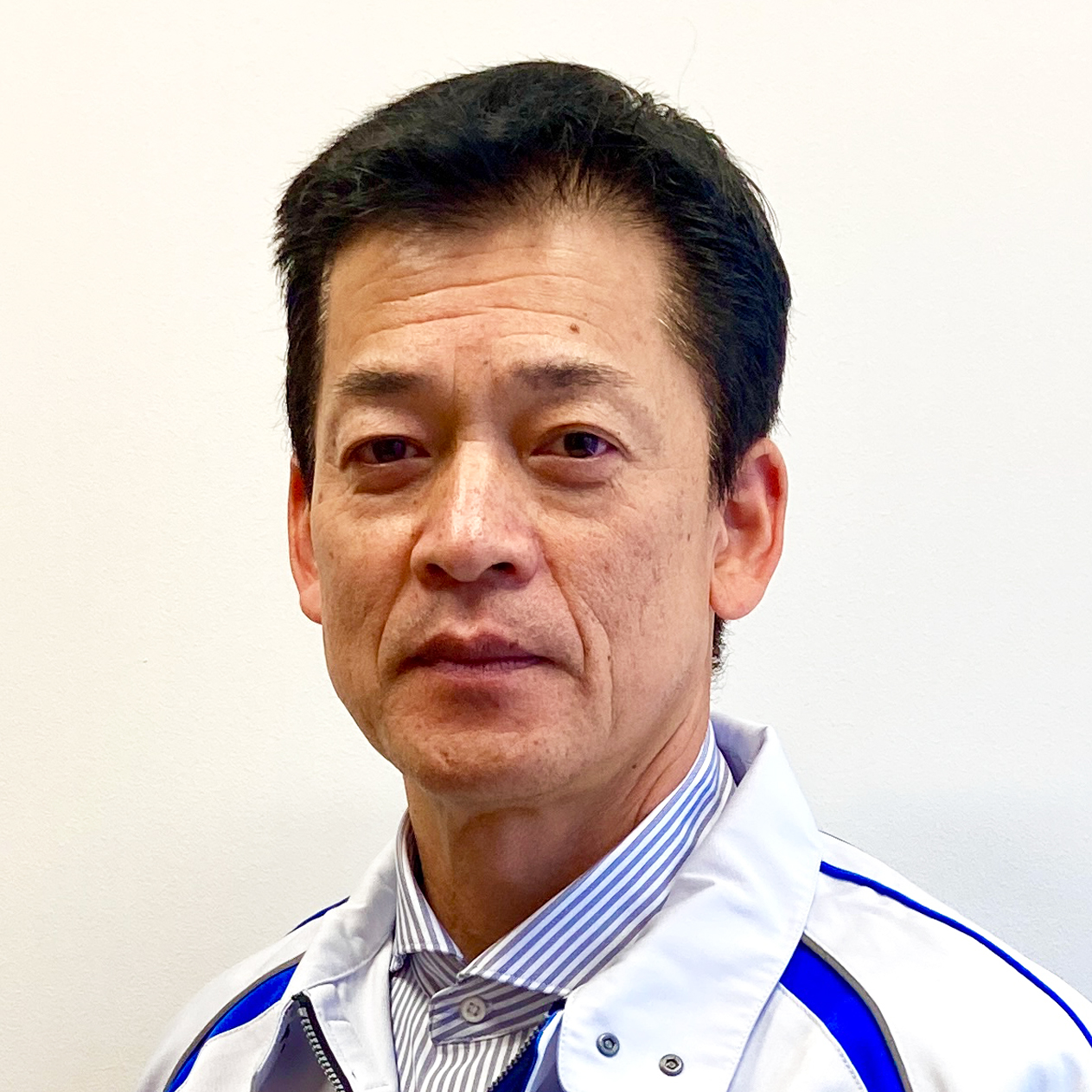
監修者
文室 義広
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて、製造現場の改善、販売店の事務系改善などの42年の経験をへてOJTソリューションズに入社しました。少林寺拳法で鍛えた「自他共楽」の精神を胸に、お客様の会社の社員になった気持ちで日々改善活動に伴走しています。
どのような業種でも、繁忙期と閑散期が存在します。それぞれの時期によって段取りを変える必要がありますが、トヨタでは、仕事が減っているときでも生産性(能率)は維持するという意識を大切にしています。
生産性を維持する具体的な方法は、仕事の増加時には「細分化」を、減少時には「統合化」をおこなうというものです。このような状況に応じた段取りの工夫により、生産性を落とさずに年間通じて安定した仕事ができるようになります。
また、減産時の改善努力は将来の飛躍につながるため、仕事が減っている時でも生産性を意識することは大切です。本記事では、仕事の増加時と減少時に取るべき段取りをはじめ、細分化と統合化を用いて生産性を維持する考え方をご紹介します。
減産期であっても「生産性」を維持する
どのような業界でも、安定した量の仕事が常に入ってくるわけではありません。例えば、自動車生産の場合でも世の中の景気がよい時期や、人気を呼ぶヒット車が生まれたときなどは、ラインをフル稼働させます。しかし、リーマンショックなどを筆頭に世界的に自動車の需要が大幅に減ったときは減産を余儀なくされ、ラインの稼働率も必然的に減ってしまいます。
トヨタでは、仕事の繁忙期はもちろん、閑散期であっても仕事の生産性を維持することに重きを置いています。トヨタの現場における生産性(能率)とは、部品1個あたりの基準時間に生産個数(不良以外の合格した数)をかけた数を、総工数(人員数×実労働時間)で割った数で表します。これを金額で表せば分子は売上であり、分母はコスト(人件費)になります。
常に生産率を算出したうえで評価の対象としており、現場で能率を上げることを「儲ける」と認識しています。生産性は増産時には分子の売上が上がるため自然と生産性も高くなりますが、減産時においてはダウンしがちなため、さまざまな方法で生産性を確保する必要があります。
仕事が少ないときは1人で複数の作業をする
減産期でも生産性を維持するには、「統合化」が重要なポイントです。具体的には、1人が複数の作業をこなせる体制にします。例えば、エンジンの製造過程には「加工」と「組立」の2つの工程があり、通常はそれぞれの作業を分業化していますが、減産期にはお互いの仕事を教えて、複数の工程をこなせるようにするのです。
このように多能工化すれば、人が減っても、複数の業務を同時並行で進めることができるうえ、それぞれの仕事の応援に入ることも可能になるため、生産性を落とさなくて済みます。
一方、仕事が多く入ってくる繁忙期は、膨れ上がっていく作業量を「細分化」するのが、生産性を上げるポイントです。例えば「加工」の作業を「加工A-1」や「加工A-2」に細かく分けてそれぞれに人を配置します。ひとつの作業を短い時間でこなせれば、つくれる量が増えて、生産性は高くなります。
減産時の改善努力は将来の飛躍につながる
統合化と細分化の考え方は、生産現場だけではなくオフィスにも応用できます。売上が好調で担当者1人につき作業量が増えている場合は、人員を増やすなどして仕事や顧客ごとに分業化を図ることが効果的です。例えば、顧客問い合わせに対応する人と顧客先を訪問して商談をする人に分けて生産性を維持すれば、売上向上につながるでしょう。
反対に売上が落ちていて、全体の仕事量が減っている場合は、今まで分業していた「新規開拓」「顧客先での商談」「顧客のアフターフォロー」といった仕事の統合を図れば、生産性を維持しながら利益を上げることも可能になります。
リーマンショックの時にトヨタは、生産台数が落ち込む一方で、改善をして生産性を維持する努力を続けていました。その後の回復局面で高い利益を生み出すことができたのも、苦しい減産期に改善努力をしてきたからと言えるでしょう。仕事が少ないときこそ生産性を意識して仕事をすることで、将来仕事が戻ってきたときに、より大きな利益を生み出せるはずです。
まとめ
繁忙期や閑散期に関わらず、トヨタでは生産性を維持することを大切にしています。そのために必要な方法のひとつが、仕事が増えたときの「細分化」、仕事が減ったときの「統合化」です。
統合化と細分化の考え方はオフィスにも応用できます。仕事量によって1人が担当する業務の範囲を切り替えれば、どんなときでも生産性を維持することが可能です。また、減産時に経験した改善努力は、再び繁忙期に戻ったときに大きな利益を得るきっかけになります。繁忙期や閑散期関係なく同じように仕事をしている方は、一度「細分化」と「統合化」の考え方を参考にしてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
現場の人員配置を最適化するには?実現するための5ステップを解説!
2025.03.07 -
「平準化」と「多能工化」で現場をラクにする!仕事の幅の広げ方とリーダーシップ発揮のコツ
2025.02.28 -
仕事の増加時と減少時の取り組み方!「細分化」と「統合化」で生産性を維持する
2025.02.21 -
改善活動は「困っていること」から取り組む!「4M」の詳細も解説
2024.12.20 -
「標準化」と「平準化」で業務停滞の要因を断つ!仕事のムラをなくす方法や事例を紹介
2024.11.29 -
仕事にかかる「時間」を短縮するコツ!ステップごとに詳しく解説
2024.11.27

PAGE
TOP