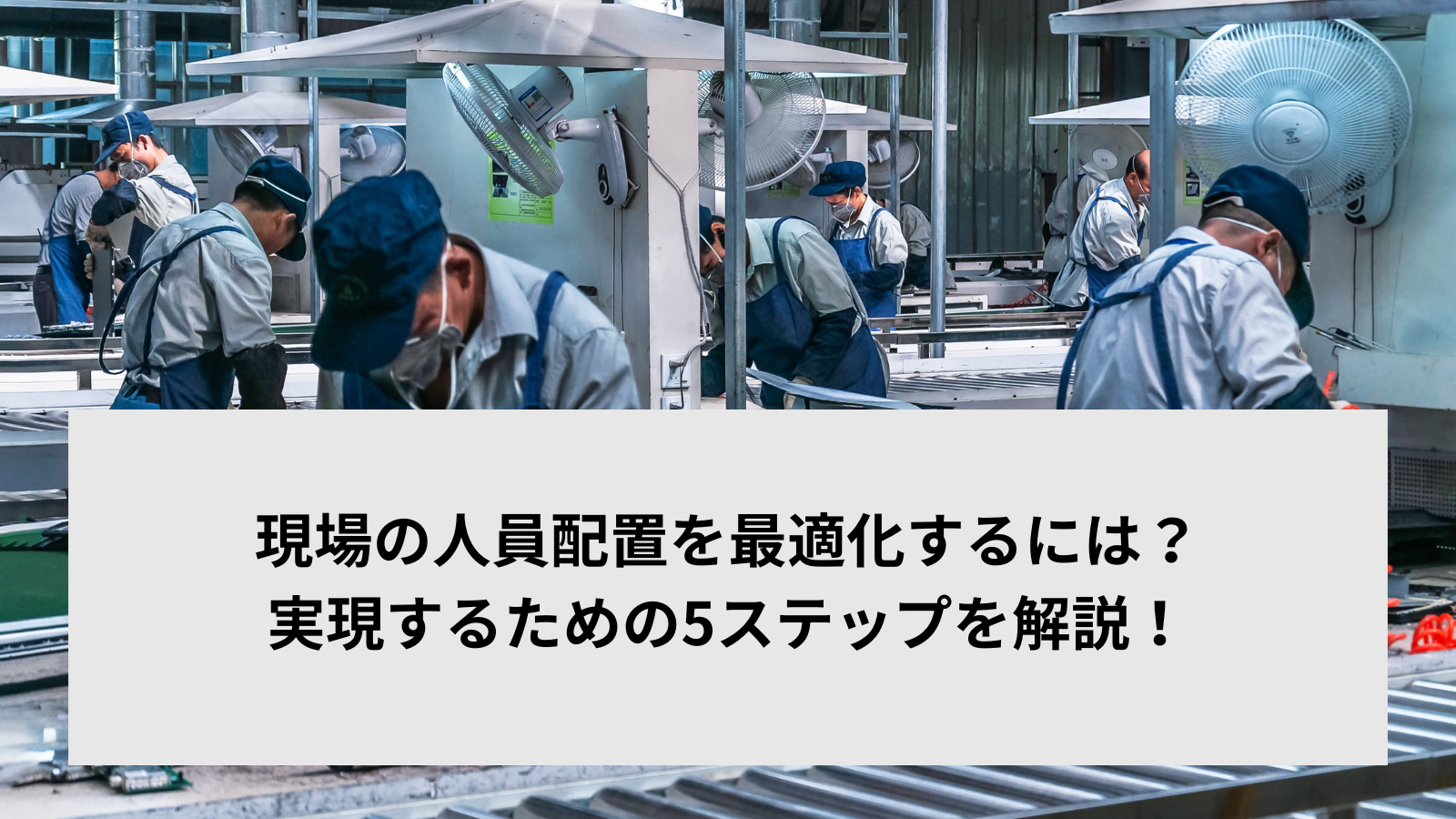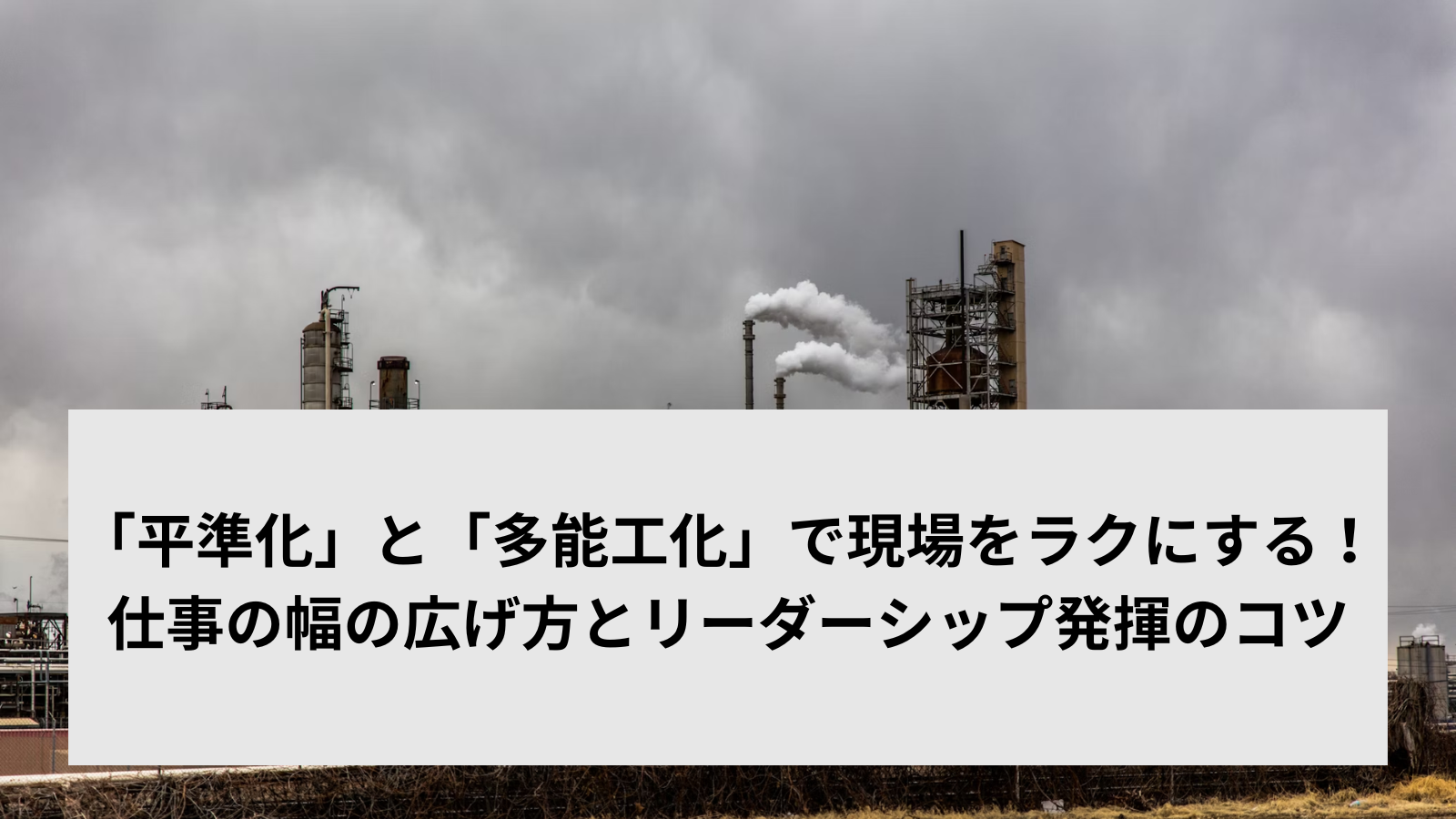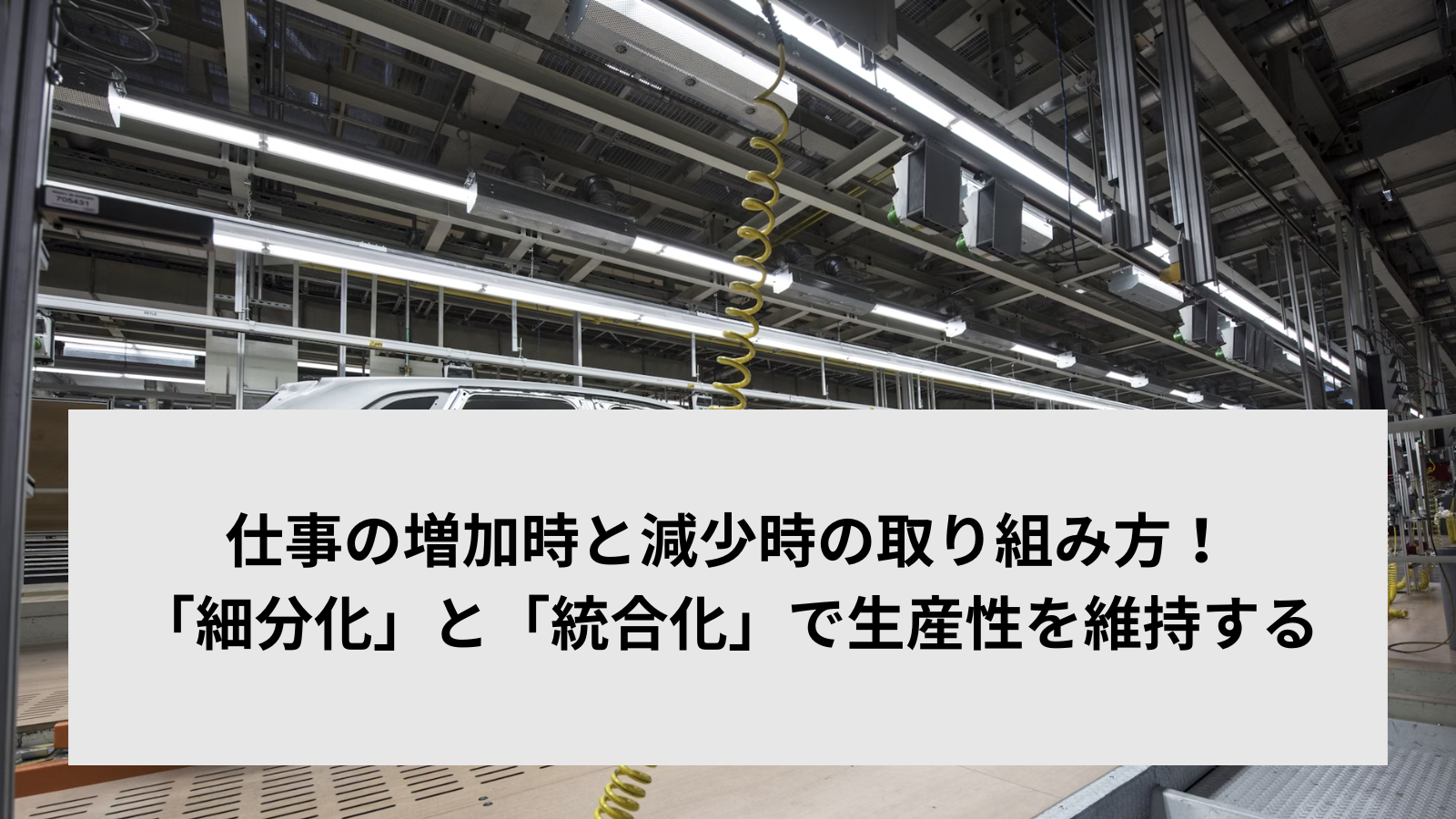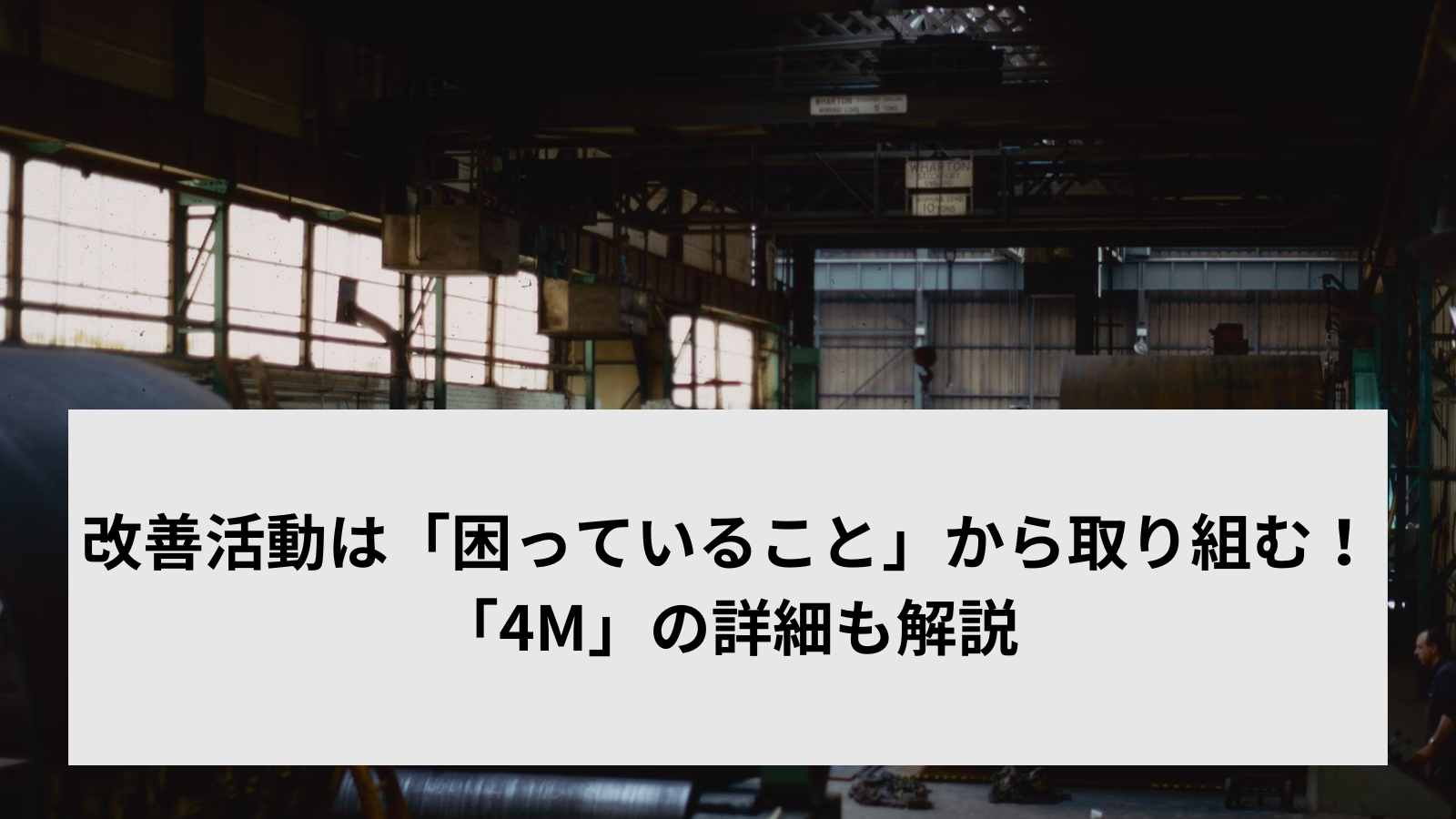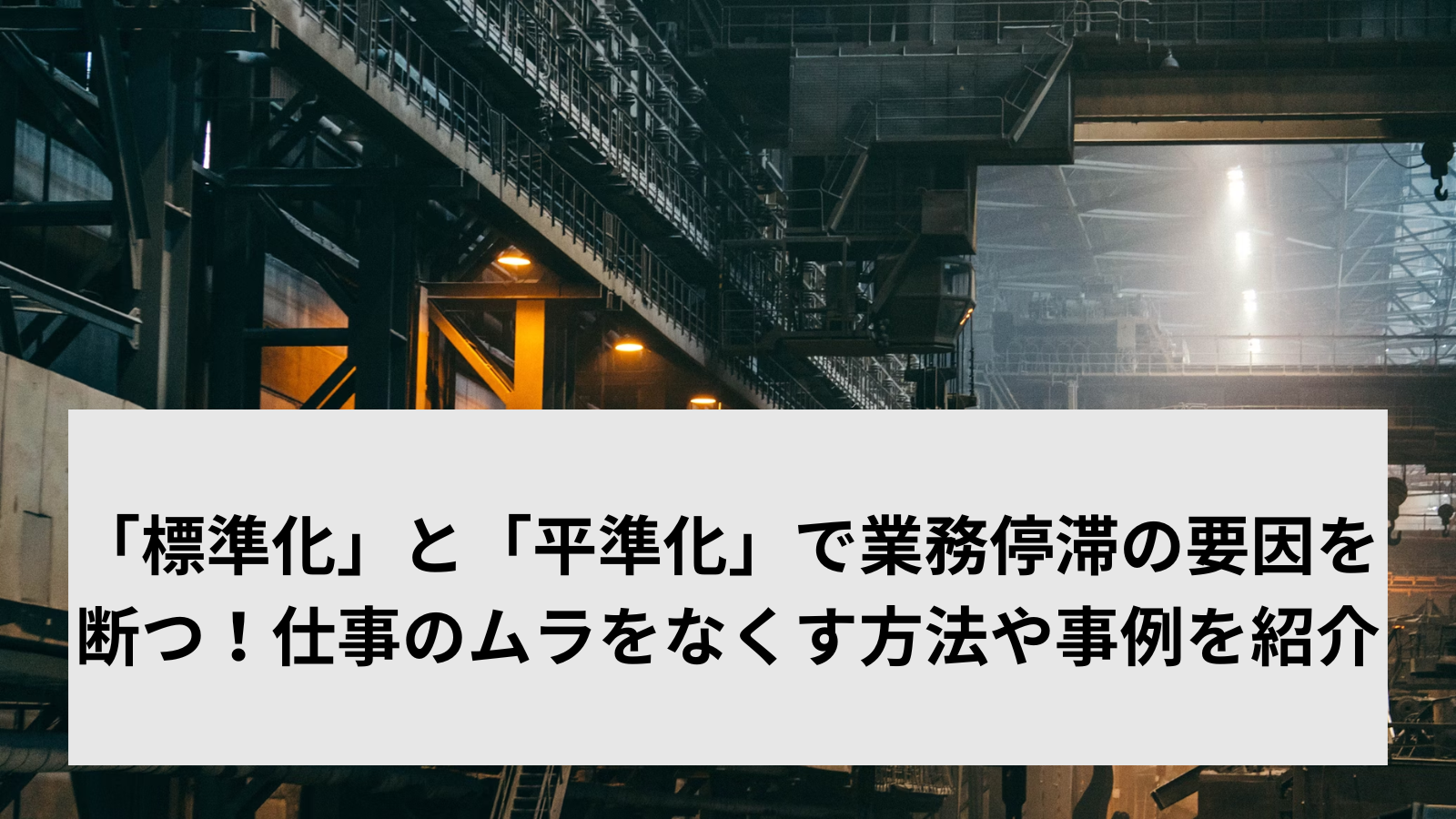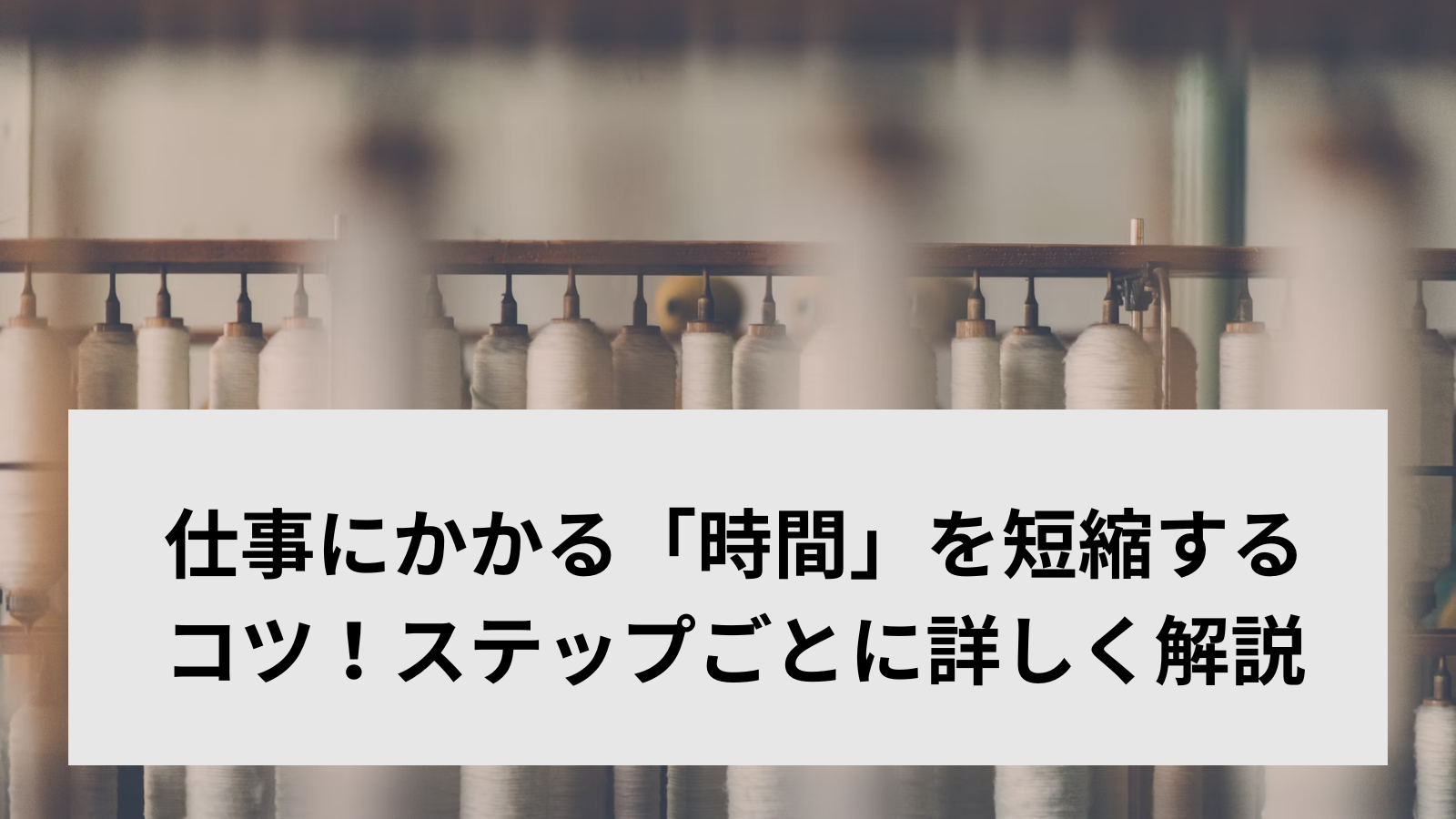生産性向上
現場の人員配置を最適化するには?実現するための5ステップを解説!
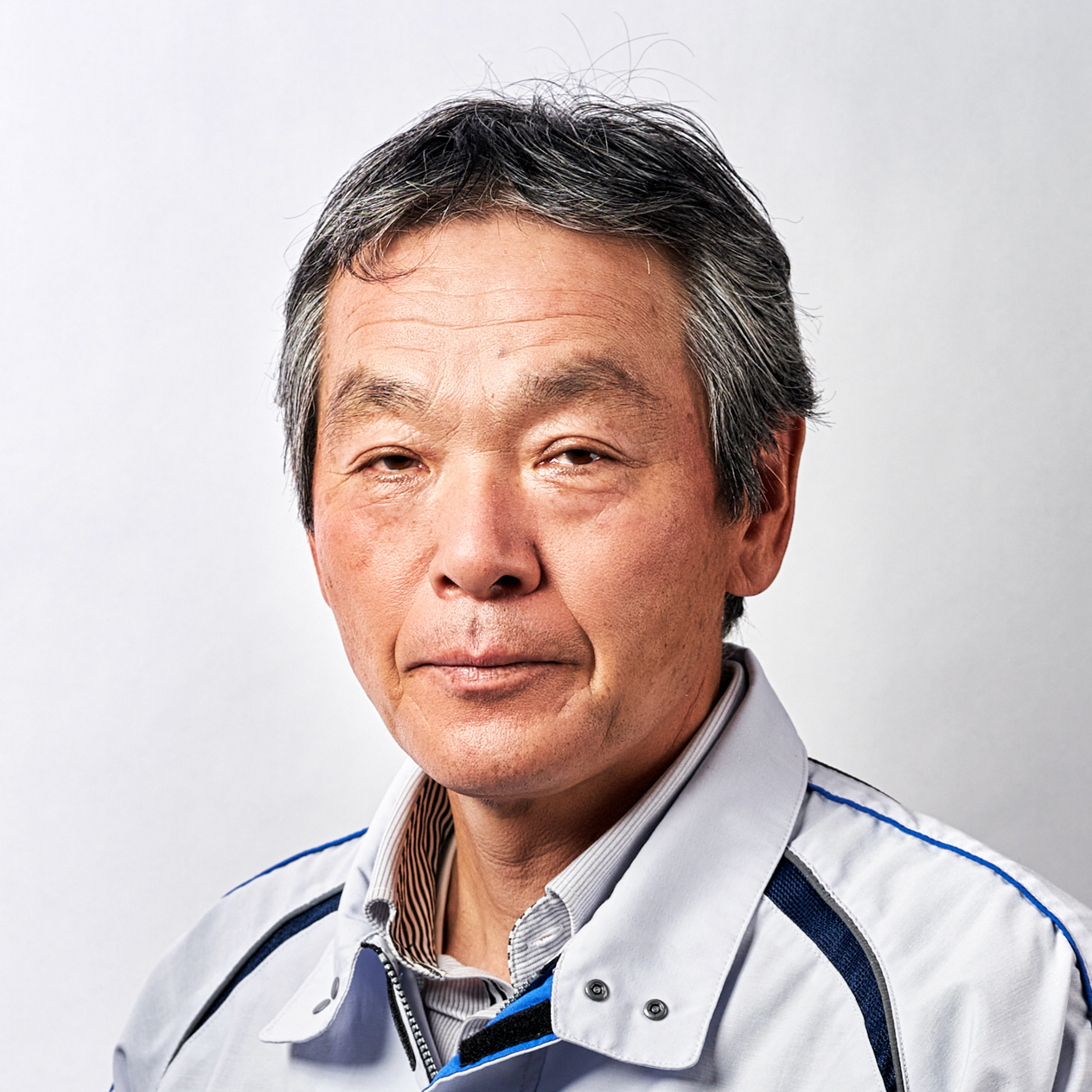
監修者
山本 昭則
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車のプレスにて39年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。改善活動には時に大変な場面もあります。それを乗り越える笑顔、会話を特に大事にしています。休日は趣味の山小屋づくりで精神統一をし、日々の仕事の英気を養っています。
現場から「忙しいので、すぐに人員を補充してほしい」といった要望が出たことがないでしょうか。これは最適人員配置の考え方ではありません。一方で、「この生産量だと、この技能を持った人が、何月までに何人必要です」といった要望を伝えられる管理監督者がいると、柔軟な人員配置が可能になり、収益やコストに大きく影響を与える武器になります。
本記事では、環境の変化などで生産量の増減があった際に、最適人員配置を実現するための方法を解説しています。
最適人員配置の考え方
最適人員配置とは、基準時間に応じた適切な人員配置のことです。
実現するためには、「基準時間」と「作業者の知識と技能」を明確に数値化する必要があります。この二つを数字と表で視える化したものをもとに、管理監督者が人員の配置を決めます。
「基準時間」と「作業者の知識と技能」を解説します。
基準時間
トヨタでは、ものを作るための製品基準時間が定められています。
ここでいう基準時間とは、付加価値を生む作業に必要な時間のことです。これを作るために、この工程で、何分何秒かかるかということを基準として明確にしています。
作業者の知識と技能
ものを作る工程には必ず知識と技能が必要になります。各工程に配置された作業者が独り立ちできているか、安心して任せられる能力を習得しているか視える化することも重要なポイントです。
最適人員配置を実現するための5ステップ
最適人員配置を実現するために、下記5つのステップを解説します。
- 「基準時間」と「個人の知識と技能」を視える化する
- 個人の山積みをつくる
- 組織の山積みをつくる
- 調整し振り分ける
- 要素ごとに移動させる
「基準時間」と「個人の知識と技能」を視える化する
まず一つ目のステップは、「基準時間」と「個人の知識と技能」を視える化することです。
作業ごとにかかる時間を計測し、基準時間を作成していきます。
そして、作業者の知識と技能を把握して視える化します。この際、例えば「Aさんは加工はこれくらいできるが、調整の習熟度は低い」「Bさんは加工はまだ経験がないが、調整は独り立ちできている」など、要素ごとに視える化しておくことが大切です。
個人の山積みを作る
二つ目のステップは、個人の山積みをつくることです。
一人ひとりの担当する作業量を視える化するために、担当作業についてステップ1で作成した基準時間を積み上げて棒グラフを作成します。例えば作業Aは200分、作業Bは150分、作業Cは50分の基準時間だとすると、作業ABCの担当者は合計で400分の作業時間が必要であることが明らかになります。
組織の山積みを作る
三つ目のステップは、組織の山積みをつくることです。
ステップ2で作成した個人の山積みの棒グラフを並べて、組織全体の作業負荷バランスを視える化します。この際、棒グラフには定時のラインを引いておくことで、負荷が集中してしまっている人や余裕のある人を見分けることができます。
調整し振り分ける
四つ目のステップは、調整して振り分けることです。ここから管理監督者が考えることになります。
ステップ3で作成した組織の山積みをもとに、作業負荷を平準化するよう振り分けます。感覚ではなく、グラフを用いて振り分けることで、平等な作業量調整が可能になります。
このステップを完了したら、一度作業を動かしてみましょう。
要素ごとに移動させる
五つ目のステップは、要素ごとに移動させることです。
ステップ4までの振り分けでは、すんなりうまくいくことは少ないため、都度調整していくステップになります。
このステップでは作業を分解し、要素ごとに移動させて作業を組み合わせます。そのために、最初のステップでおこなった作業者の知識を技能を視える化しておくことが重要となります。
個人の知識と技能を視える化するコツは、習熟度を4段階にわけて評価することです。
- レベル1:教えた
- レベル2:フォローが必要
- レベル3:一人でできる
- レベル4:指導ができる
このように段階分けすることで、全員の習熟度を同じ目線で評価することができます。また、作業を組み合わせるツールとしてだけでなく、育成計画に活用することも可能です。
最適人員配置を実際に取り入れるには
ステップを理解しても、実際に進めていくことは難しいです。現場からの反発があったり、作業が忙しかったりするとなかなか進みません。
トヨタでも現在の最適人員配置がいっぺんにできるようになったわけではありません。手始めに工程をしぼって、現場の理解が得られるような大きさから始めていくことがポイントです。
また、最適人員配置の実践を進めたある食品製造業の事例を紹介します。
この会社では、繁閑に応じた人員体制でコスト削減を実現することが課題でした。具体的には、繁忙期に必要な人員を確保している一方で、閑散期には多くの手待ちが発生してしまっている状況です。また、現場から感覚に頼った増員要請をされてしまうことも問題でした。
5ステップに沿って改善を進めていましたが、現場の意識の壁に苦戦しました。繁忙期にできていた作業量でも、閑散期の少ない作業量に慣れてしまうことで、現場はどうしても通常生産でも「忙しい」と感じてしまいます。
この会社では、管理監督者が粘り強く現場と話し合いながら改善活動を進めたことで、結果的に個人の作業負荷を徐々に平準化することができました。また、管理監督者が自信をもって必要人員を把握できるようになったことも大きな成果と言えます。
まとめ
最適人員配置は、基準時間に応じて適切に人員配置をすることです。
そのための第一歩として、基準時間と作業者の知識や技能を把握することから始めます。そのあとは山積み、振り分け、調整のステップを進めていきます。
また、管理監督者が現場を巻き込みながら率先してこういった活動を進めていくことが、なにより成功に向けて重要なポイントです。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
現場の人員配置を最適化するには?実現するための5ステップを解説!
2025.03.07 -
「平準化」と「多能工化」で現場をラクにする!仕事の幅の広げ方とリーダーシップ発揮のコツ
2025.02.28 -
仕事の増加時と減少時の取り組み方!「細分化」と「統合化」で生産性を維持する
2025.02.21 -
改善活動は「困っていること」から取り組む!「4M」の詳細も解説
2024.12.20 -
「標準化」と「平準化」で業務停滞の要因を断つ!仕事のムラをなくす方法や事例を紹介
2024.11.29 -
仕事にかかる「時間」を短縮するコツ!ステップごとに詳しく解説
2024.11.27

PAGE
TOP