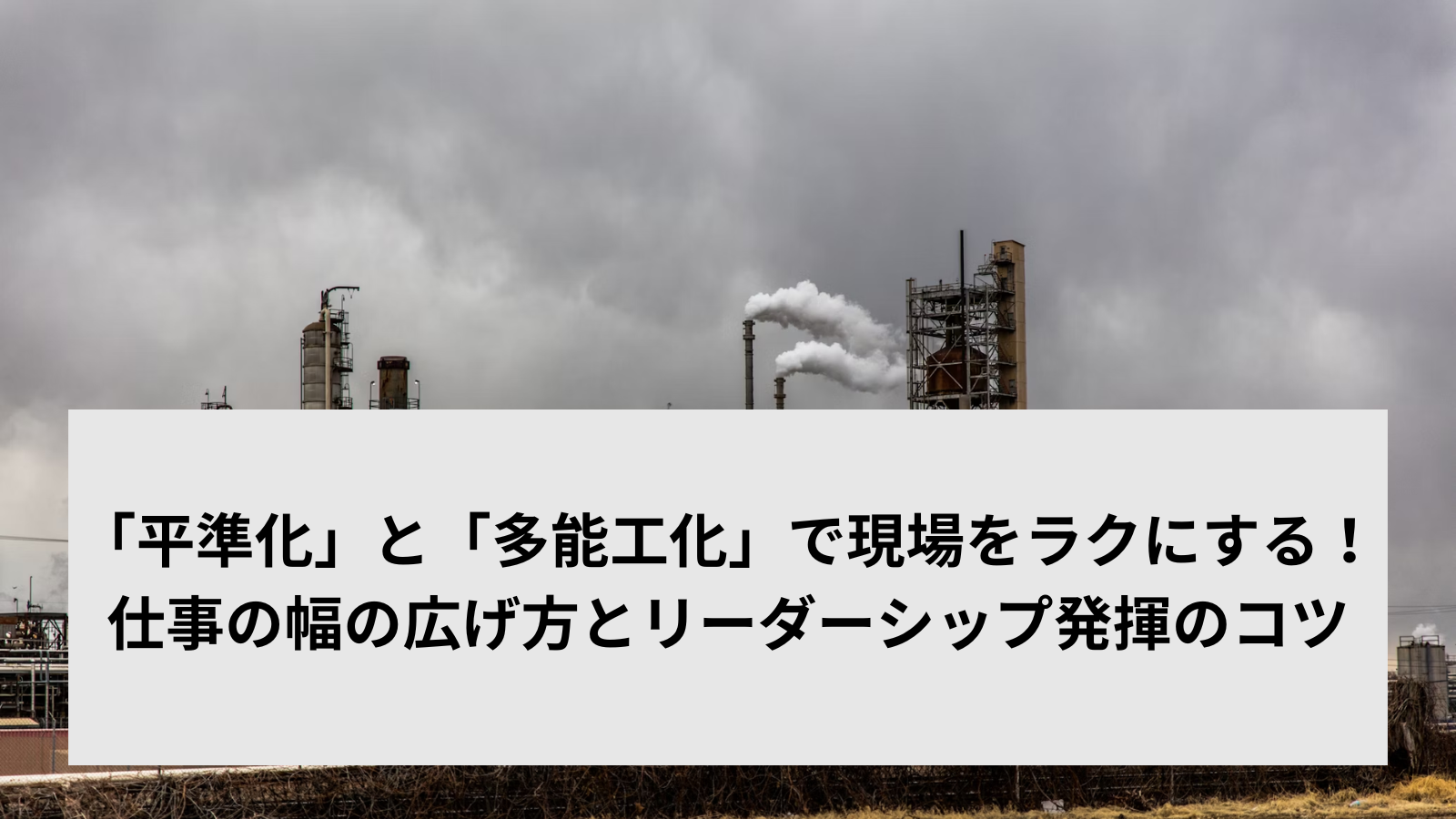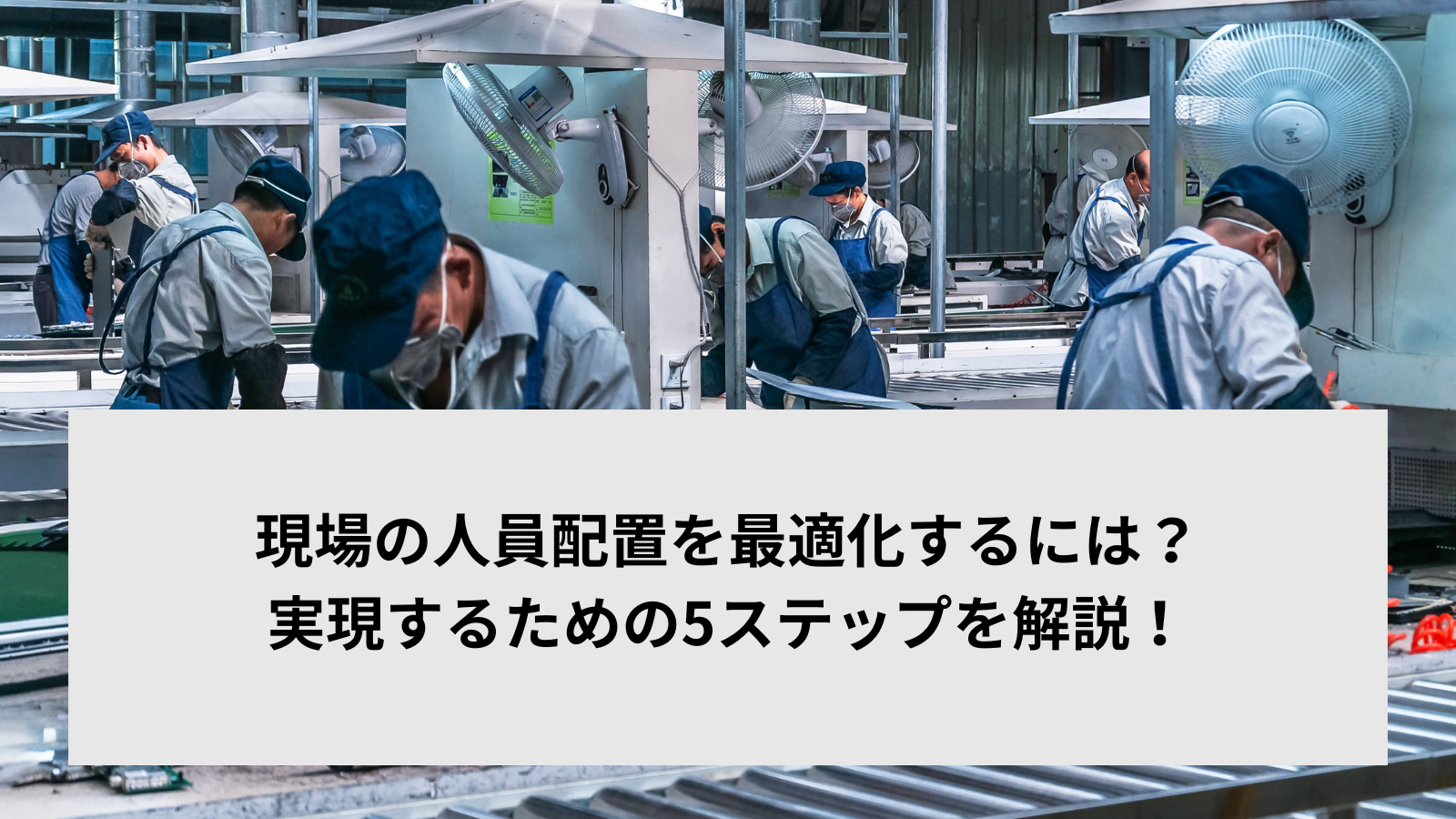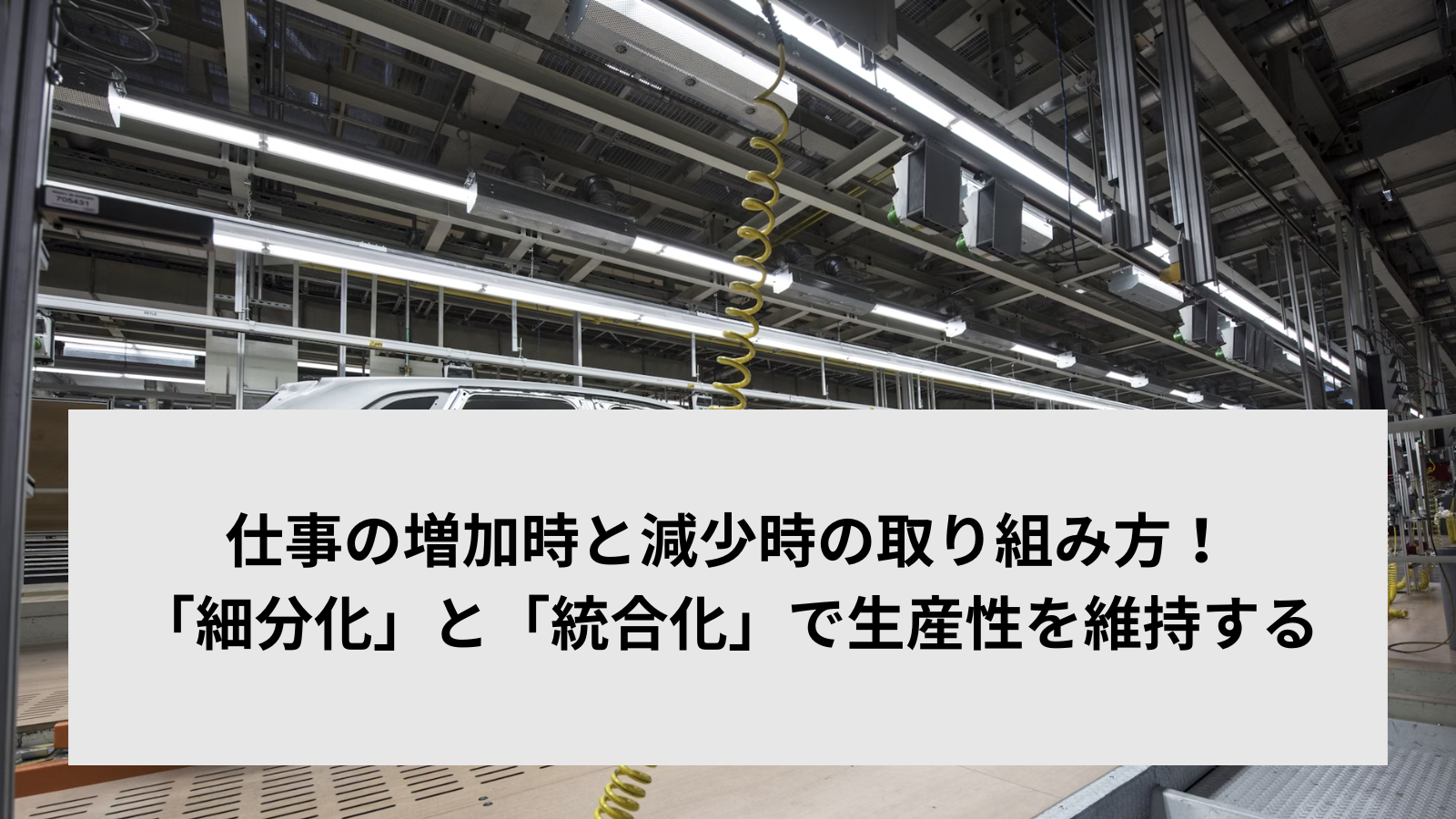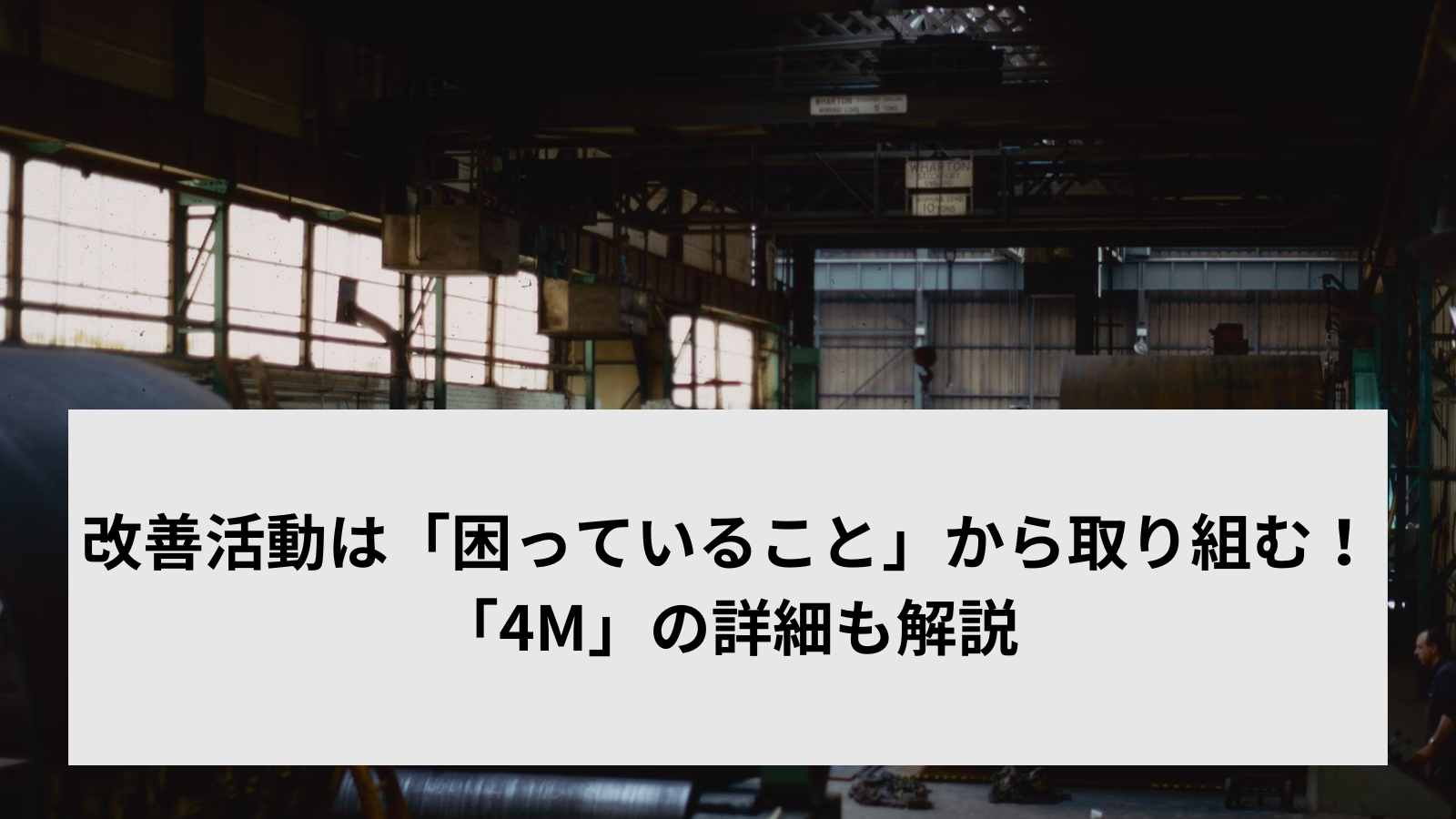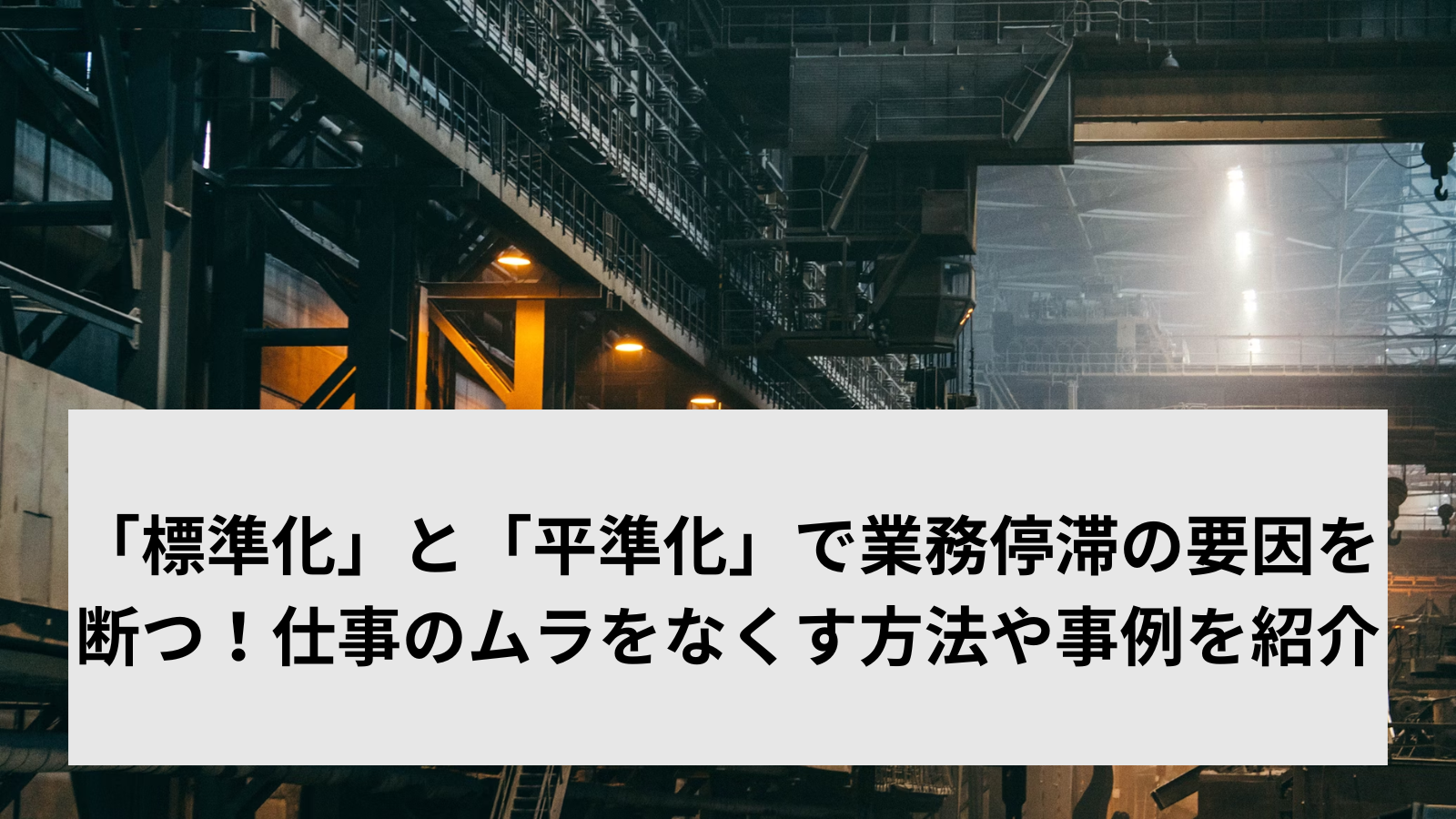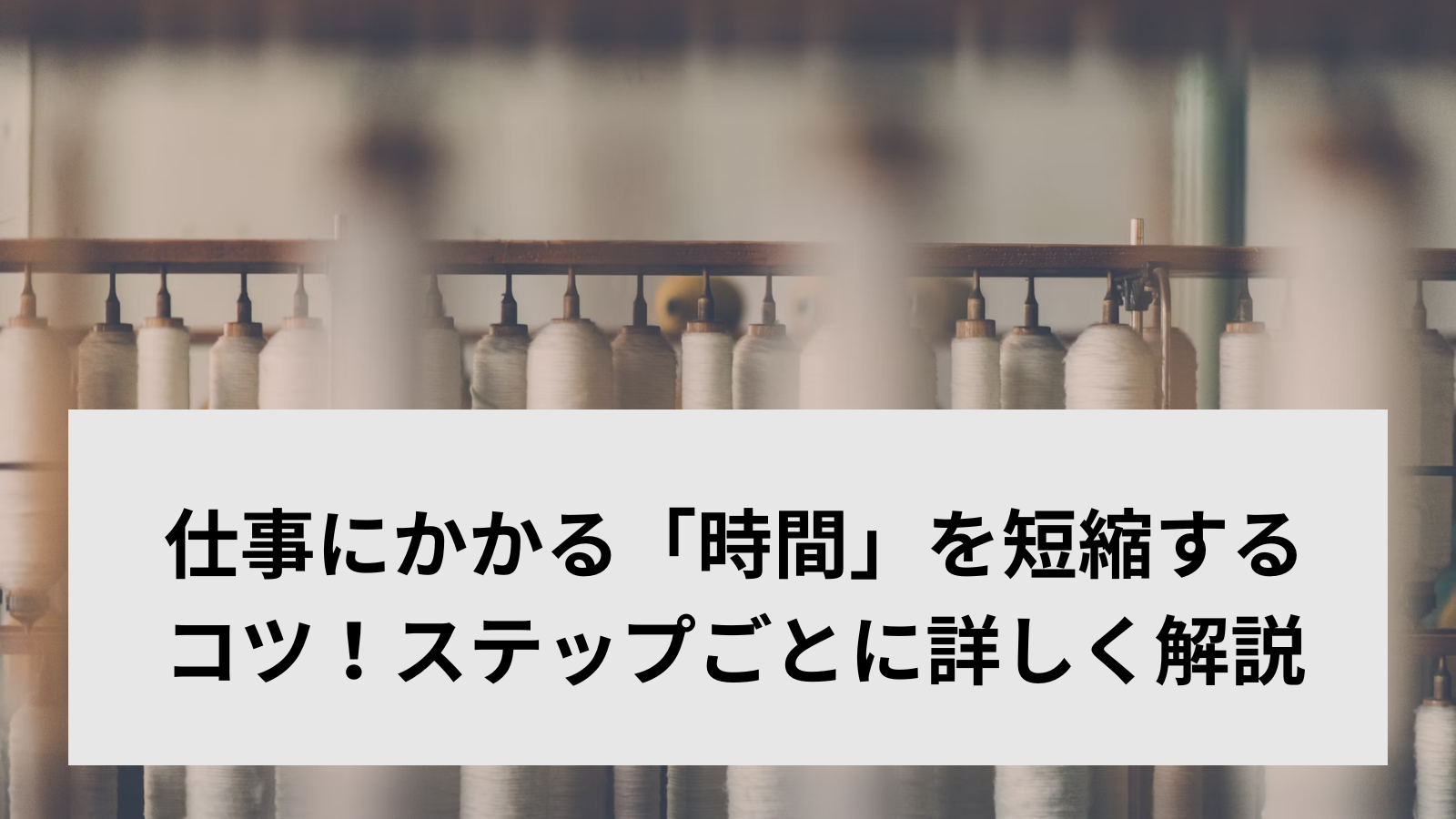生産性向上
「平準化」と「多能工化」で現場をラクにする!仕事の幅の広げ方とリーダーシップ発揮のコツ

監修者
三尾 恭生
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて42年の現場経験、管理職の経験を経てOJTソリューションズに入社しました。座右の銘は「不易流行」。変える勇気と変えない勇気を持つことが大事だと信じ、現地現物でお客様と伴走しています。
メンバーによって業務負担の偏りが発生しているという職場はよくあるでしょう。特に小規模なオフィスなど少人数で仕事を回している会社の場合、メンバーによって仕事の量や負担が異なることが多く、なかには大きな疲労や不満を感じている人もいるかもしれません。
トヨタでは現場をラクにするために、メンバーにかかっている業務負担の偏りをなくし、仕事の幅を広げることはリーダーの主な役割としています。これを実現する具体的な方法が「平準化」と「多能工化」です。「平準化」と「多能工化」を実践すれば現場がラクになるとともにメンバーの成長や職場の一体感にもつながります。本記事では「平準化」と「多能工化」のやり方やリーダーシップを発揮するコツをご紹介します。働きやすい環境づくりを目指している管理監督者の方はぜひご覧ください。
メンバーの仕事の負担を平準化する
どのような会社でも、メンバーによって仕事の負担は異なり、業務の偏りが発生している現実が少なからずあるでしょう。特に小規模な現場では限られた人材をムダ・ムリなく生かし、仕事の成果を創出していく必要があります。そのために取り組みたいのが「平準化」です。これは一人ひとりのメンバーの働く負担を均等にすることです。
生産現場で例えると、 どんどん仕事をこなして次工程へ流している工程がある一方で、仕事を受け取ったまま滞留している工程も存在します。滞留が発生している工程は作業に追いつけず時間に追われる一方で、次工程は待ちの状態になり、時間・人材ともにムダが発生してしまいます。このような事態を防ぐためには、仕事の流れがよくなるように、人員配置や作業改善、ひとつひとつの工程の区切りを変更するなどの工夫が必要です。
工程間の負担が平等になって仕事がラクになれば、時間に追われて急ぐ必要はなくなり、その結果ミスや不良も減らせて仕事のクオリティ向上につながります。
平準化の観点から職場の問題を見つける
生産現場だけではなくオフィス系の職場でも、リーダーとしての初めての経験は、自職場の小さなグループから始まることが多いと思います。その後、リーダーとしてステップアップしていくにつれ、自分が得意としている業務や専門性から離れた部下も抱えるようになります。もしくは、これまでとはまったく違う部署で組織長に任命されることもあるかもしれません。
自分の専門性が発揮できない場でリーダーとなったときは、平準化の視点から担当職場の問題を見つけ、現場をラクにするという意識が大切です。現場を客観的に見てみると、のんびりと作業している工程と、せわしなく動き回っている工程があることに気付くこともあるでしょう。このような忙しさの違いは人員の配置や工程のなかに存在するムダやムリが招いた結果です。リーダーは現場をよく見て、メンバーのがんばりをムダにしないよう平準化を図り、その調整役となる必要があります。
多能工化で職場をひとつにする
メンバーの仕事をやりやすくすれば、職場の意見が活性化されるメリットも得られます。仕事がやりやすくなれば、熟練者以外でも作業ができるようになります。誰でもできるように簡単な作業につくり込まれているのであれば、仕事のやり方を教える時間も短くて済み、職場内でローテーションをしやすくなります。
ひとつの工程や業務を担当するメンバーが固定されると誰が何をしているのかその内容がブラックボックスになっていることも少なくありません。また、本人にも慣れが生じて改善の余地があってもアイデアが出づらくなります。一方で、メンバー全員がいろいろな工程に携われるようになると、メンバーから自然と「ここはこのようにしたほうがいい」とさまざまな知恵が出てきます。自分の意見が反映されると、仕事の成果に貢献しているという達成感が持てるようになり、ひとりひとりの意欲向上にもつながるはずです。
トヨタでは、メンバーが多種多様な工程に携われるスキルを身につけることを「多能工化」と呼んでいます。多能工化ができるようになると、その職場内での応援が可能な体制が整います。つまり、生産変動への柔軟な対応が可能になり、強い職場が実現できるということです。また、メンバー自身も様々な業務経験を通して成果に貢献することができるので、職場の一体感や成長の実感にもつながります。
まとめ
メンバーにかかっている業務負担の偏りは、どのような職場でも発生しているはずです。メンバーにかかる業務負担の偏りを軽減し、一人ひとりの仕事の幅を広げることはリーダーの重要な役割のひとつと言えるでしょう。
現場をラクにし、メンバー全員が意欲を高めながら仕事をするためには「平準化」と「多能工化」を進めることがとても有効です。メンバー全員が働きやすい環境づくりをしたいとお考えの方は、ぜひ今回紹介した「平準化」と「多能工化」の考え方を参考にしてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
現場の人員配置を最適化するには?実現するための5ステップを解説!
2025.03.07 -
「平準化」と「多能工化」で現場をラクにする!仕事の幅の広げ方とリーダーシップ発揮のコツ
2025.02.28 -
仕事の増加時と減少時の取り組み方!「細分化」と「統合化」で生産性を維持する
2025.02.21 -
改善活動は「困っていること」から取り組む!「4M」の詳細も解説
2024.12.20 -
「標準化」と「平準化」で業務停滞の要因を断つ!仕事のムラをなくす方法や事例を紹介
2024.11.29 -
仕事にかかる「時間」を短縮するコツ!ステップごとに詳しく解説
2024.11.27

PAGE
TOP