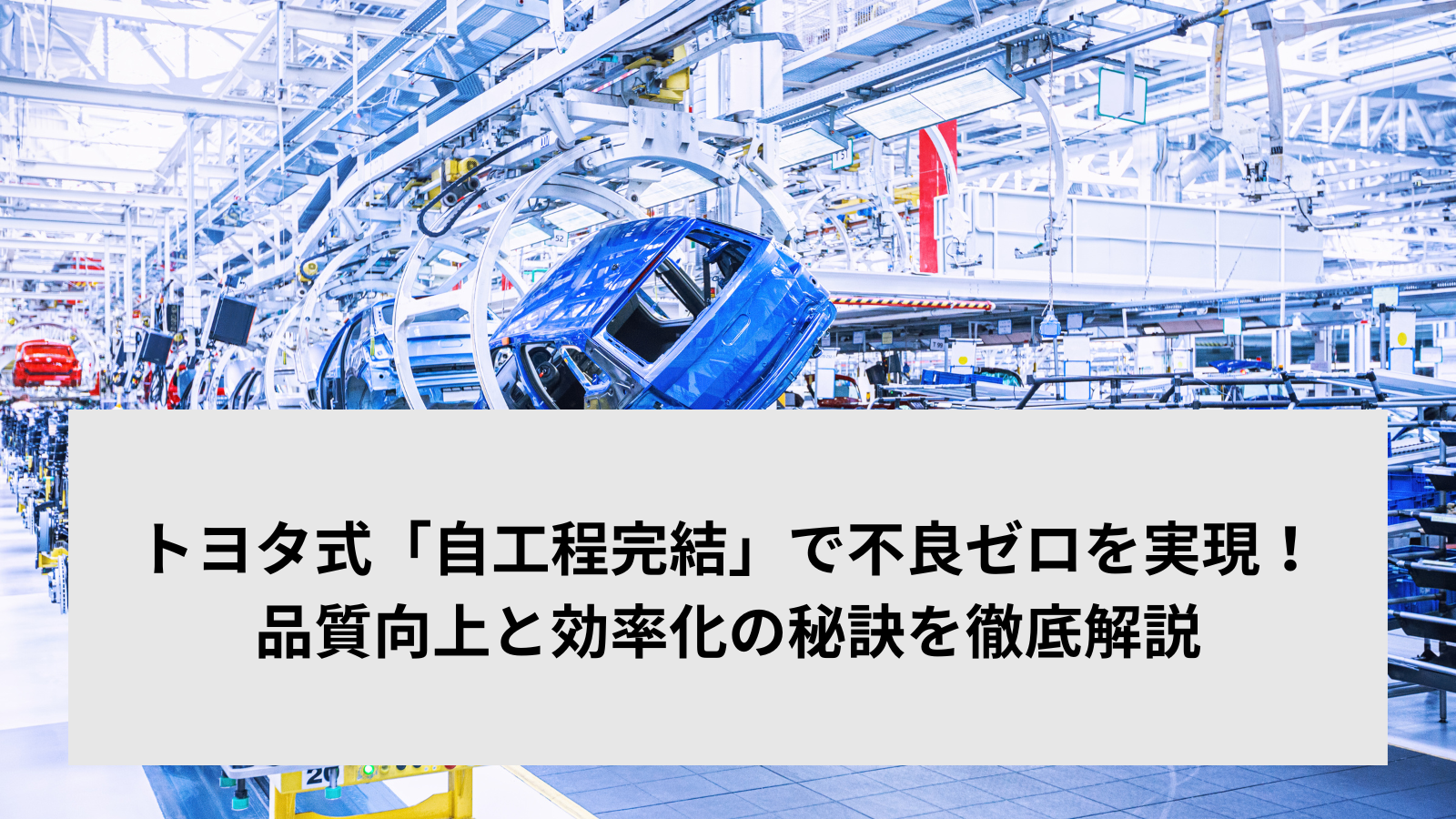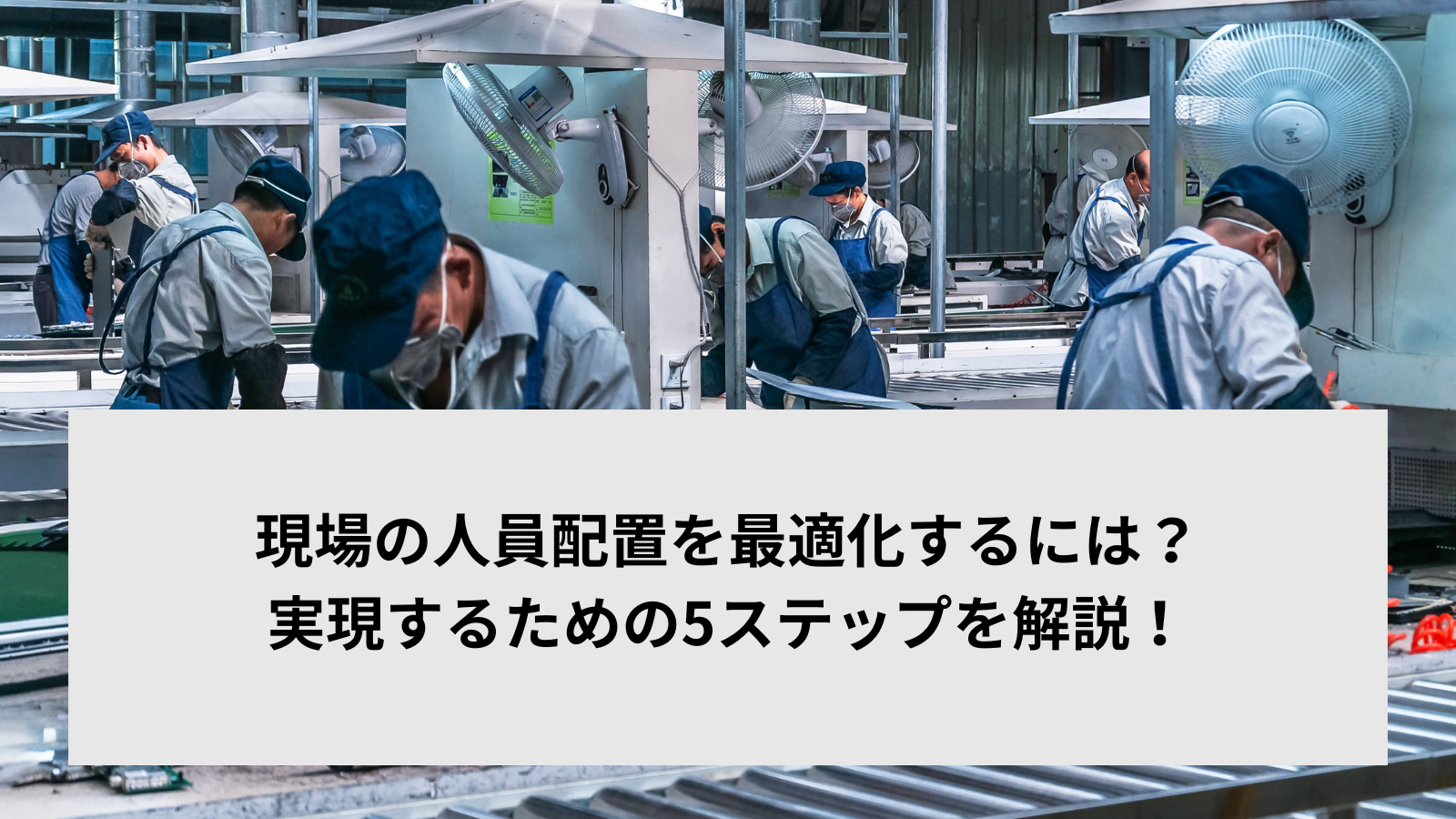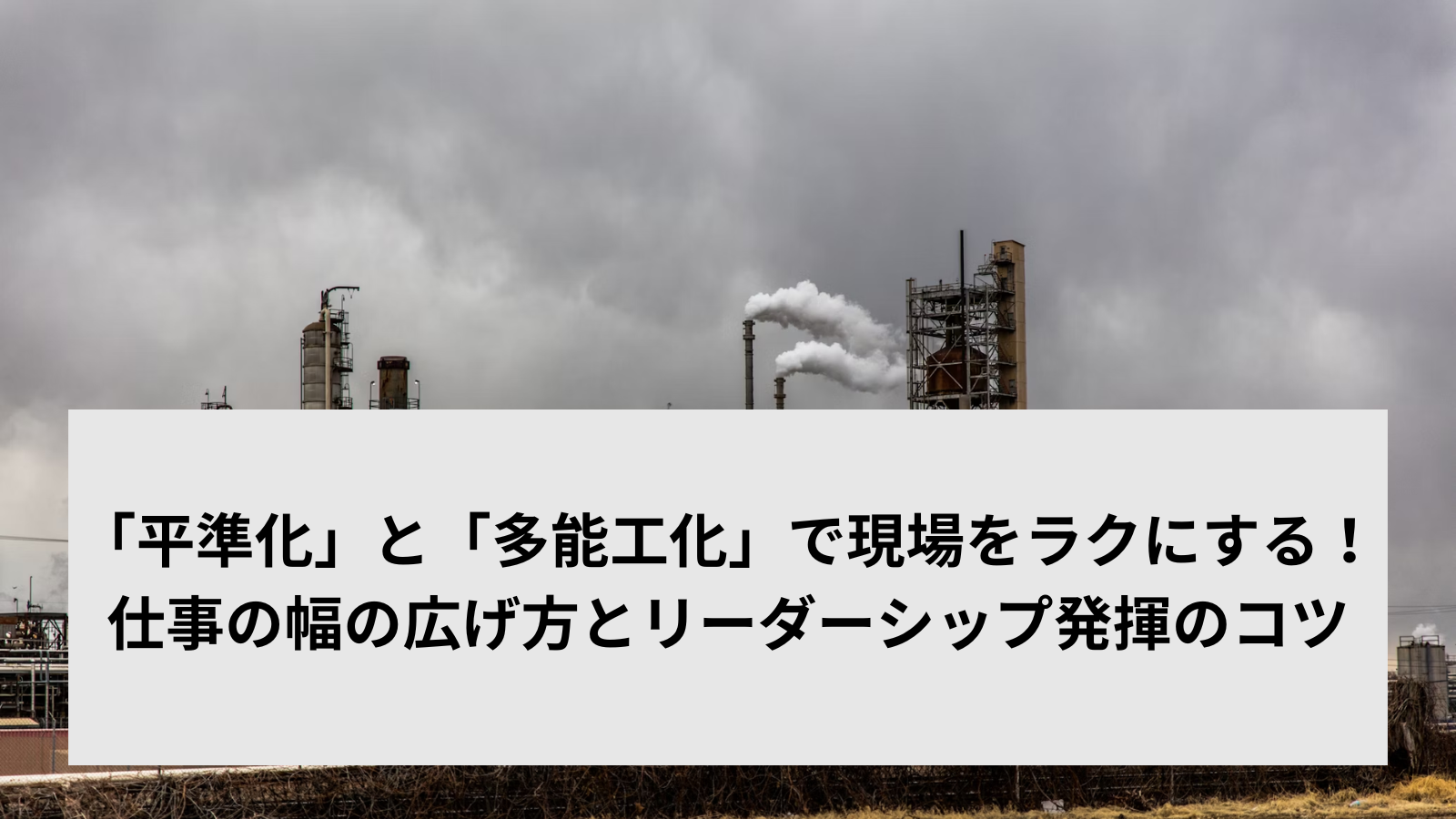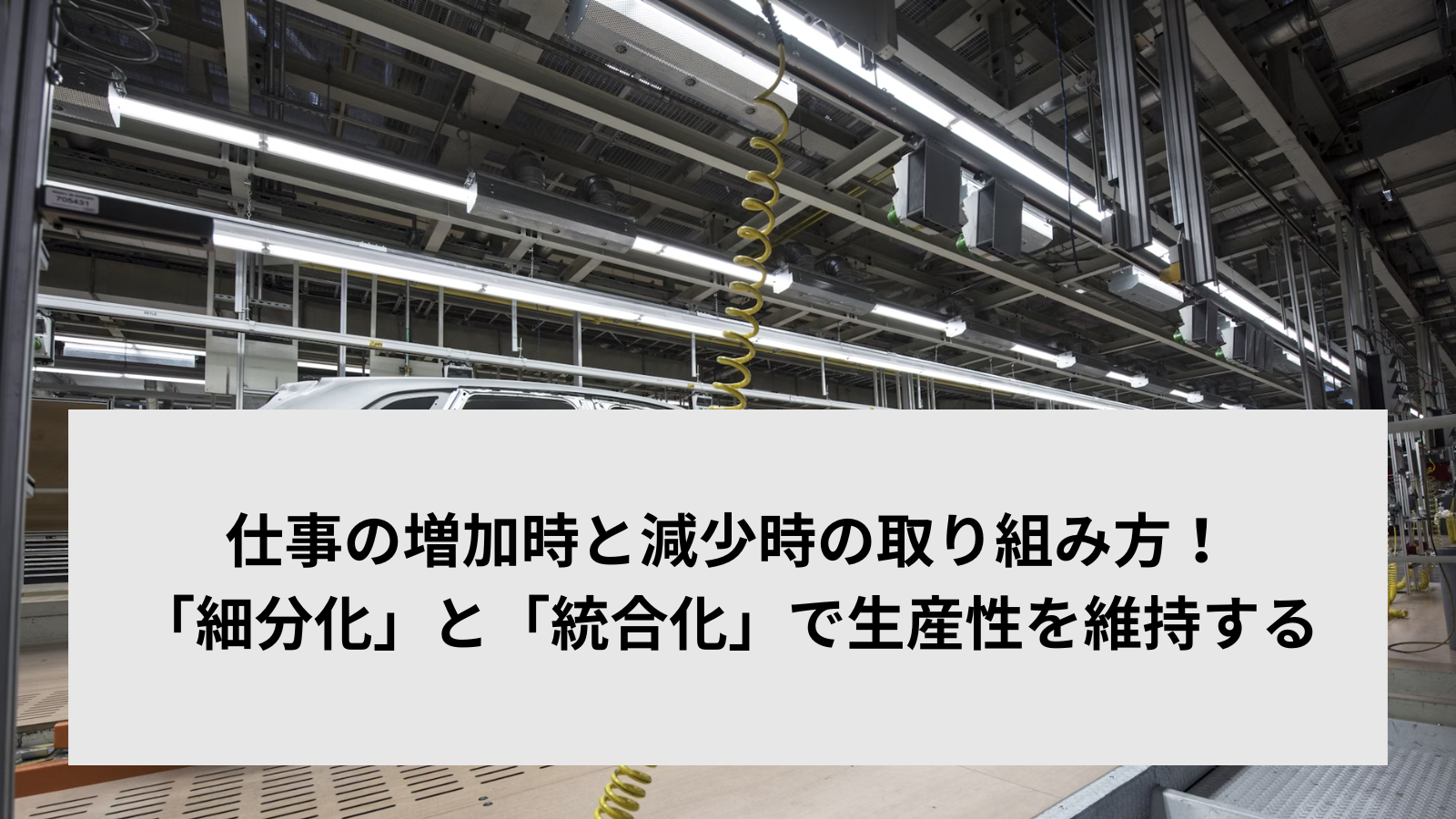生産性向上
トヨタ式「自工程完結」で不良ゼロを実現!品質向上と効率化の秘訣を徹底解説

監修者
丸山 浩幸
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。大阪府出身、トヨタ自動車の品質管理にて41年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。お客様の現場では「この改善、よかったで!」ともう一声の思いやりを大事に、仲間意識が高まるような改善活動ができるよう日々伴走しています。
製造現場でよく耳にする「不良」という言葉。製品の品質を損ねるだけでなく、手戻りやコスト増、顧客からの信頼失墜にもつながる深刻な問題です。
本記事で紹介するトヨタ式「自工程完結」は不良を減らすだけでなく、不良を出さないためのしくみです。製造業に限らず、サービス業や事務職場など、あらゆる業務に応用できる考え方です。
自工程完結の基本から、具体的な進め方までを詳しく解説します。
自工程完結とは?
「自工程完結」とは、自分の工程で責任を持って品質を保証することです。この考え方は、トヨタ生産方式の柱の一つである「自働化」が原点となっています。トヨタにおける「自働化」とは、不良を作らない、そして異常があればラインを止めるしくみのことを指します。
この考え方は、かつてトヨタが品質問題に直面した際、「不良ができてから直す」のではなく、「不良そのものを作らない」という考え方を徹底するために生まれました。
自工程完結は、製造現場だけでなく、正しい仕事を効率的に進めるためのプロセスとして、すべての業務に応用可能な考え方です。
自工程完結を徹底するメリット
自工程完結を組織にしっかりと根付かせることで、さまざまなメリットが得られます。まず、工程ごとに品質保証がなされるため、最終検査に頼らずとも不良品を出さない生産が可能になります。これにより、最終検査で不良が見つかり、その原因特定に時間がかかるといった問題を回避できます。
また、万が一不具合が発生した場合でも、各工程で品質が確保されていれば、原因の特定が容易になり、迅速な対策が可能です。このように問題の早期発見と対応が進むことで、現場全体の問題解決能力が向上し、次なる改善活動への意識も高まっていきます。
さらに自工程完結を徹底するには、作業者一人ひとりが自分の仕事の良し悪しを自ら判断し、対処する力が求められるため、日々の業務を通じて問題を見つける目が養われ、継続的な改善が促進されます。こうした取り組みを繰り返すことが人材育成にもつながり、結果として高いレベルの工程づくりが可能になります。
自工程完結を進めるための3つのステップ
トヨタには「後工程はお客様」という大切な言葉があります。これは、自分の仕事の次の工程で作業する人を「お客様」ととらえることで、後工程が求める最高のアウトプットを提供しようという意識を持つことを意味します。
この「後工程はお客様」の考え方をもって、自工程完結の導入を進めます。具体的には、以下の3つの具体的なステップが必要です。
1. 良品基準を決める
まず、自分の次の工程(後工程)がどのような状態の部品や情報、アウトプットを求めているのかを明確にします。これが自分の工程で目指すべき品質の「基準」となります。
2. 作業の手順標準を作る
定めた良品基準を満たすために、具体的な作業手順や標準作業を明確に作成します。これにより、誰がおこなっても一定の品質が保たれるようになります。
3. 正常異常の判断基準を決める
作成した手順や標準にしたがって作業がおこなわれた際に、それが「正常」なのか「異常」なのかを判断するための明確な基準を設定します。これにより、作業者自身がその場で品質の良否を判断し、異常があれば対処できるようになります。
さらに、不良が作れないようなしくみ(ポカヨケ)を導入することで、より確実に不良を減らすことができます。例えば、部品の形状が左右で異なる場合、目視では判断しにくいことがありますが、異なる形状の部品がセットできないようなしくみを導入することで、間違いを物理的に防ぐ改善が考えられます。
ある現場での事例として、ナットのずれに関する後工程からの苦情がありました。目視チェックでは1mm程度のずれが判別できず、後工程でボルトが締まらないという問題が頻発していました。そこで目視チェックを廃止し、実際にボルトを差し込んでチェックする方法に変更したところ、後工程での不良流出がゼロになりました。
後工程からの不満や苦情は、「お客様からのクレーム」と同じです。チェックのしくみや基準を変えることで、品質レベルが向上し、効率的な業務改革につながります。まずは不良の発生を最小限に抑えることが重要ですが、最終的に目指すべきは「不良そのものを作れない状態」を実現することです。そのためには、常にその考え方を意識しながら業務に取り組むことが大切です。
まとめ:自工程完結で「仕事の質」を高める
「自工程完結」は、一つひとつの工程が責任を持ち、不良をつくらないという品質保証の考え方であると同時に、効率的に業務を進めるための非常に強力な手法です。この考え方を実践するには、まず自分の仕事の良し悪しを自ら判断し、適切に対処する力が求められます。
そのためには、後工程が求める基準を明確にし、それに応じた正しい作業手順を確立するとともに、正常と異常を判断するための明確な基準を設定することが不可欠です。加えて、「後工程はお客様である」という意識を持つことによって、自然と継続的な改善が促されるようになります。
このような取り組みを重ねていくことで、個々の作業者の目的意識が高まり、人材育成にも大きな効果をもたらします。品質を高め、効率を最大化する「自工程完結」は、どのような組織にとっても欠かせない考え方です。ぜひ自社の業務にも積極的に取り入れてみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
PQCDSMEとは?製造現場の7つの管理指標を解説
2026.01.30 -
ジャストインタイム(JIT)とは? 3原則とメリット・デメリットを徹底解説
2025.12.26 -
トヨタ式「自工程完結」で不良ゼロを実現!品質向上と効率化の秘訣を徹底解説
2025.09.12 -
現場の人員配置を最適化するには?実現するための5ステップを解説!
2025.03.07 -
「平準化」と「多能工化」で現場をラクにする!仕事の幅の広げ方とリーダーシップ発揮のコツ
2025.02.28 -
仕事の増加時と減少時の取り組み方!「細分化」と「統合化」で生産性を維持する
2025.02.21

PAGE
TOP