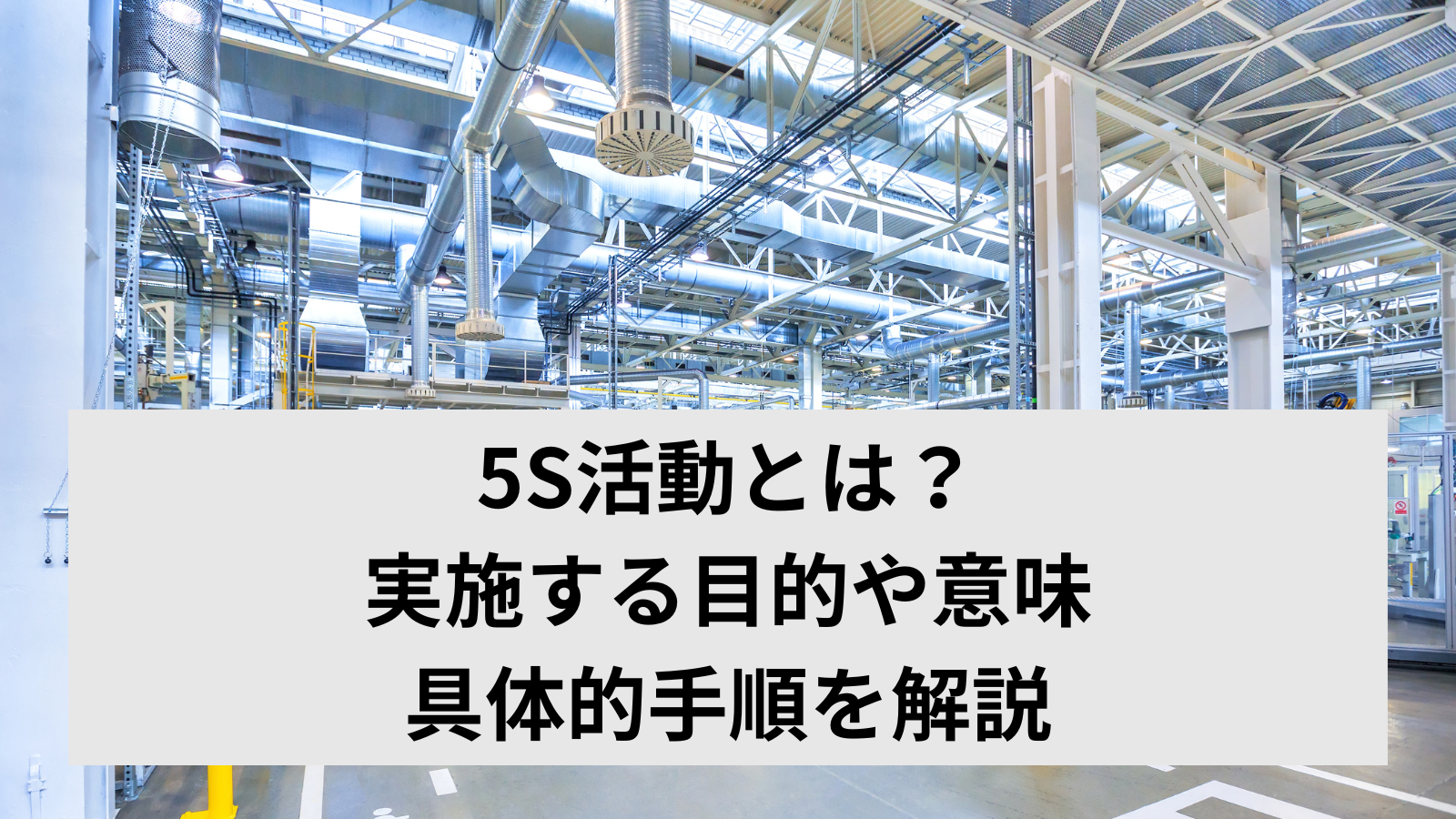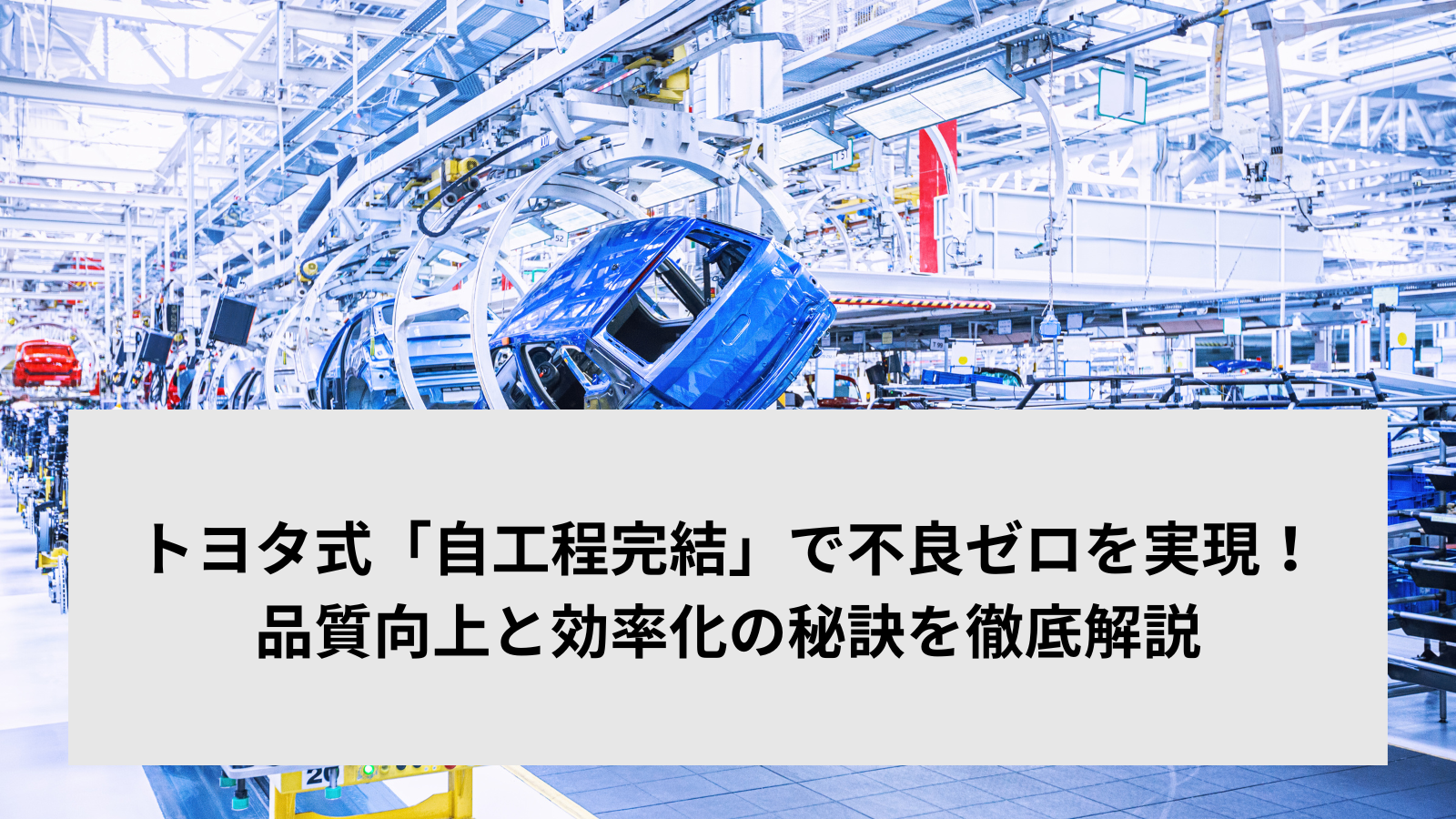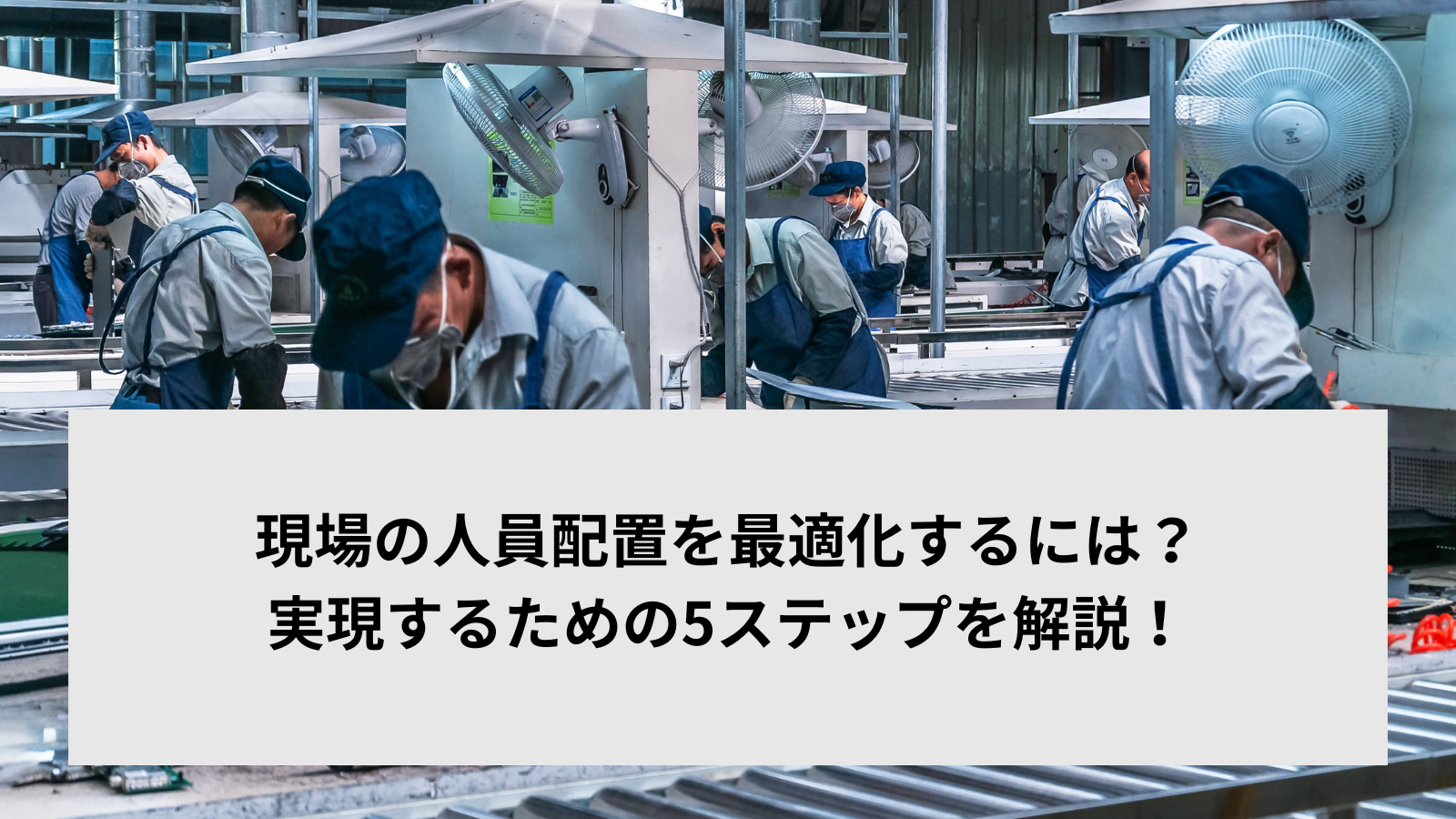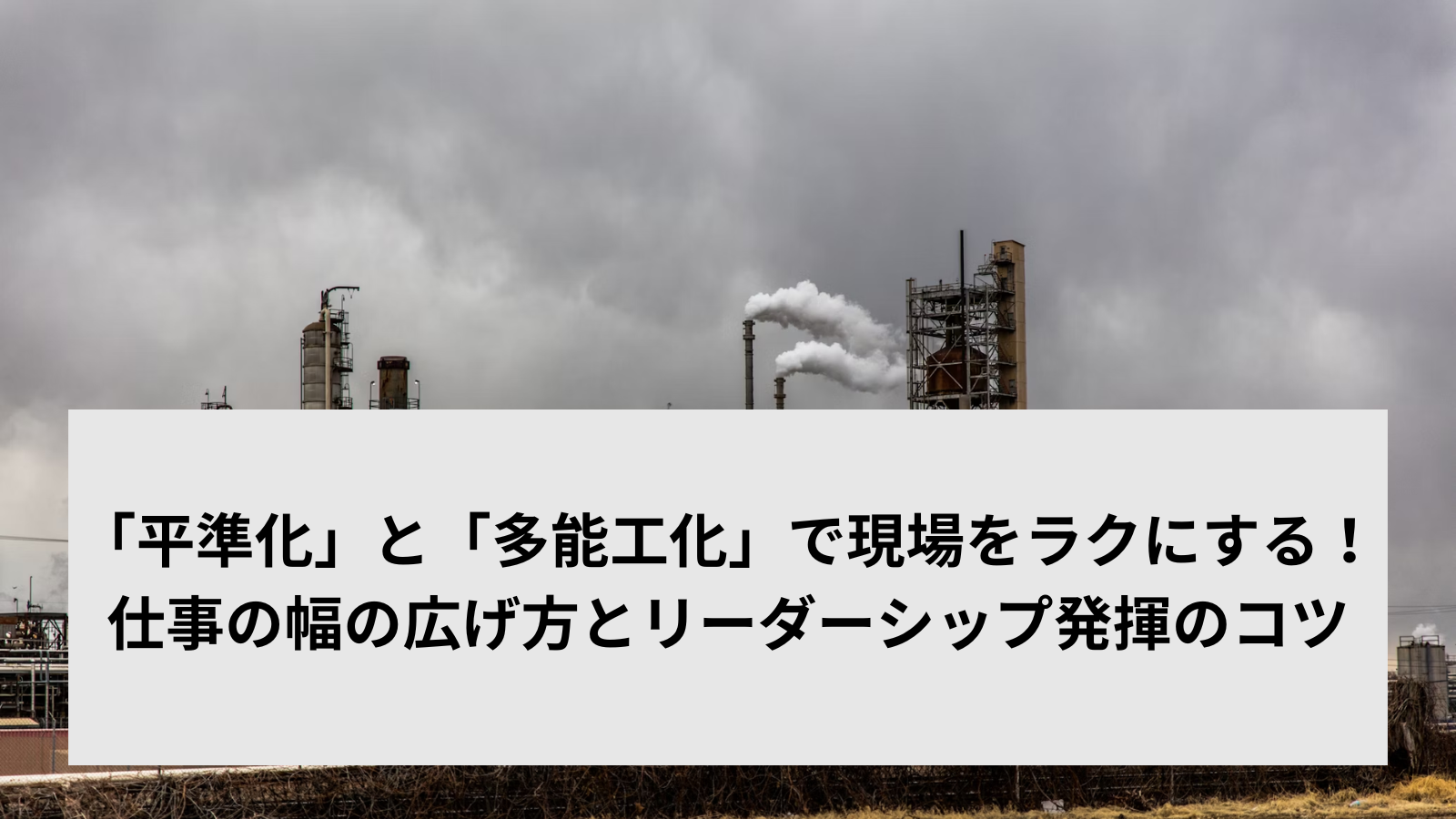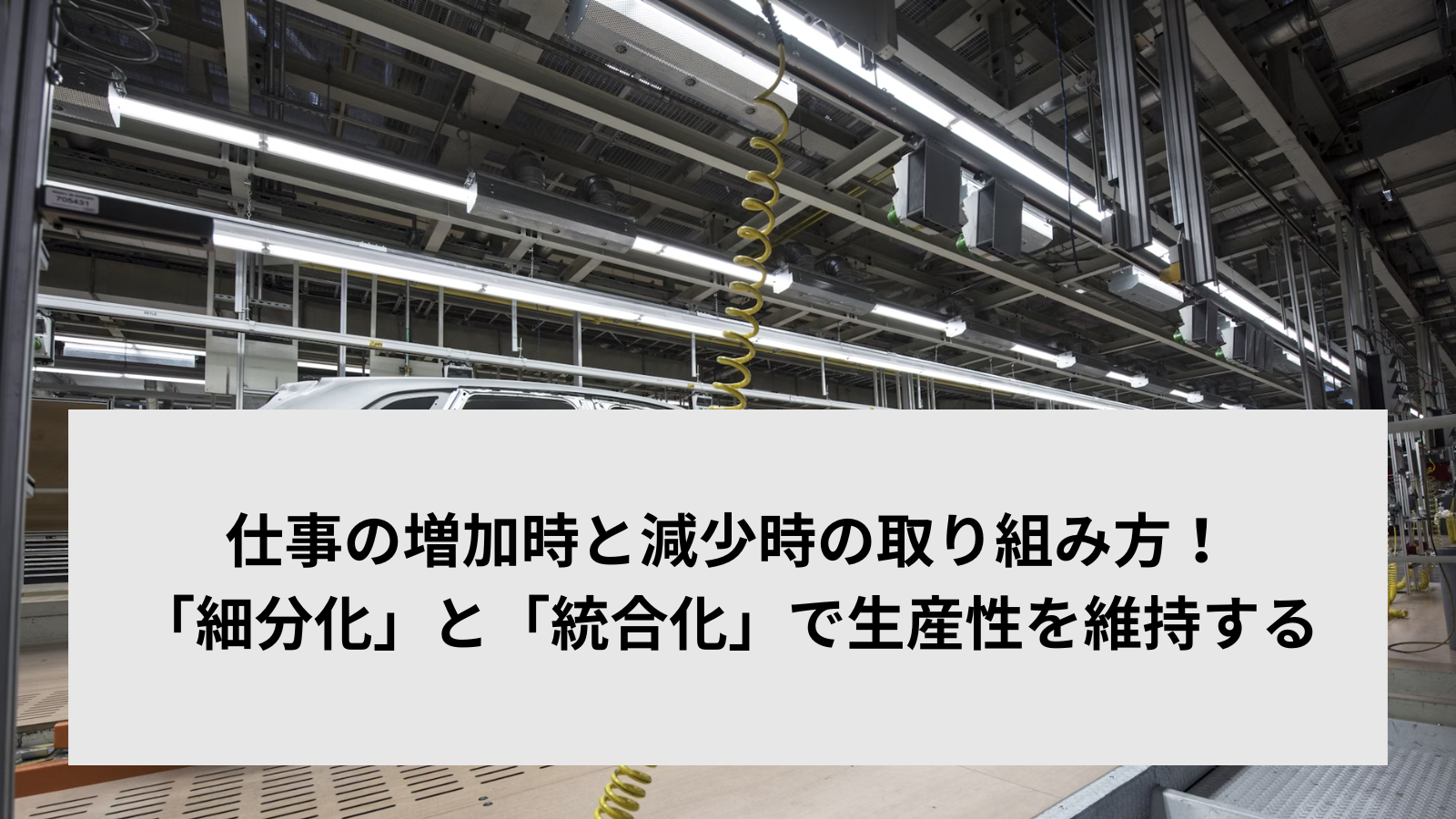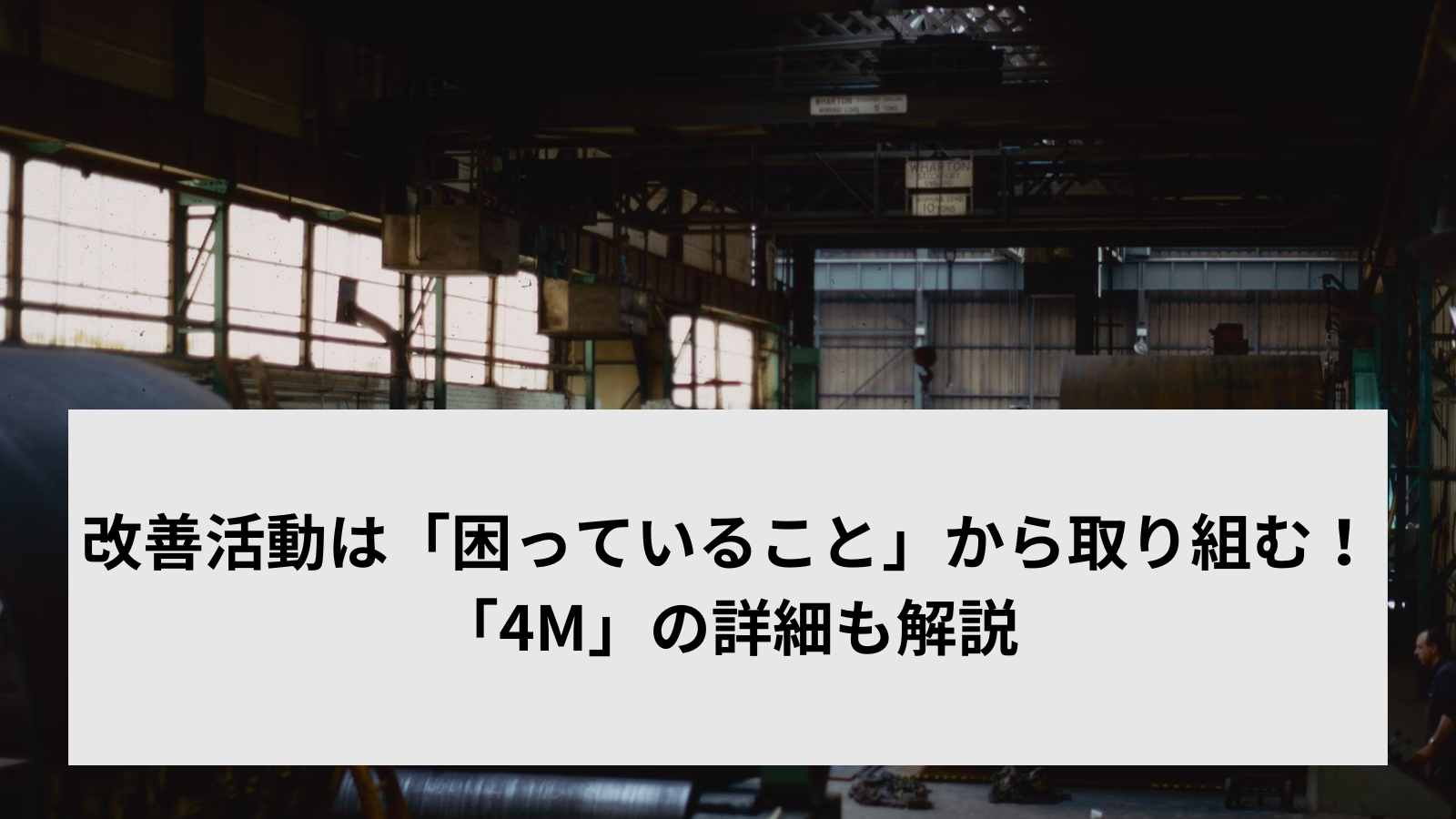生産性向上
5S活動とは?実施する目的や意味、具体的手順を解説
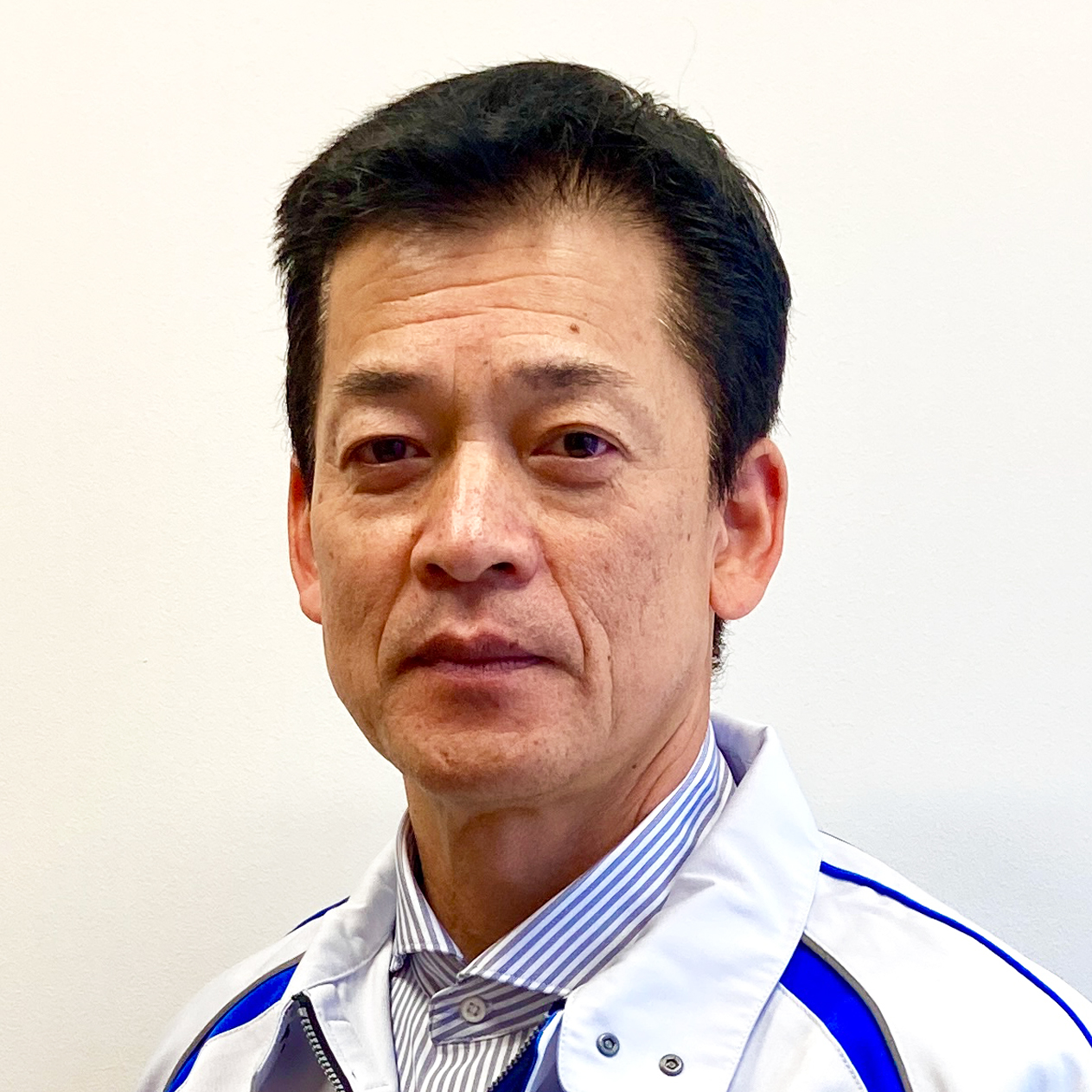
監修者
文室 義広
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて、製造現場の改善、販売店の事務系改善などの42年の経験をへてOJTソリューションズに入社しました。少林寺拳法で鍛えた「自他共楽」の精神を胸に、お客様の会社の社員になった気持ちで日々改善活動に伴走しています。
すべての改善の基礎は5S活動です。5S活動は企業の生産性や安全、そして人材育成に大きく関わってきます。5Sという言葉自体は知っていても、細かい意味は知らないという方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、5S活動の本当の意味から実施の目的、進め方の手順などを詳しく解説します。生産性を向上させたい方や、あらためて5Sについて学習したいという方はぜひ最後までご覧ください。
5S活動とは?
5Sとは、以下の用語の頭文字をとったものです。
- 整理(Seiri・せいり)
- 整頓(Seiton・せいとん)
- 清掃(Seisou・せいそう)
- 清潔(Seiketsu・せいけつ)
- しつけ(Shitsuke・しつけ)
それぞれの用語の意味を正しく理解し、5S活動の理解を深めていきましょう。
①整理(Seiri・せいり)
整理とは「いるものといらないものを区別し、いらないものを処分すること」です。よくある間違いは、整理と整列を混同してしまうことです。整列は「あるものを綺麗に並べなおすこと」であり、処分は伴いません。
整理の本質は不要なものを減らすことです。不要なものであふれた職場は探し物や片づけに時間を取られたり、作業スペースも狭くなって生産性が下がります。まずは整理でものを減らし、職場の景色を変えましょう。
②整頓(Seiton・せいとん)
整頓とは「必要なものを使いやすいように置き場を決めて明示すること」です。整理をして必要なものだけを残した後に、誰でも使いやすいように置き場を決めることが整頓です。例えば引き出しに「はさみ」と書いたシールを貼る。これも立派な整頓です。
整頓において重要なのが「3定(さんてい)」です。これは定位=どこに、定品=なにを、定量=いくつ、の3つの定の頭文字をとったものです。3つの定を明確にすることで、誰でも必要なものをすぐに取り出せる環境が整います。
③清掃(Seisou・せいそう)
清掃とは「定期的に清掃を行い、整理整頓(2S)の状態を点検すること」です。単なる掃除だけでなく、職場の異常に気付くための点検を含むのがポイントです。5Sの時間=掃除の時間と誤解されがちですが、清掃はあくまで5Sの一部、と考えるようにしましょう。
定期的に清掃をすると、設備の異常や安全上の問題に早期に気付くことができます。掃除をしつつ、普段と違う点がないか点検する習慣をつけましょう。
④清潔(Seiketsu・せいけつ)
清潔とは「整理・整頓・清掃のしくみをつくり維持すること」です。一度だけ気合を入れてものを処分する、清掃を年に1度だけがんばる、では意味がありません。一時的な取り組みではなく、日常的に維持される状態を目指します。例えばものを捨てる日を決める、置き場所のラベルを交換する日を決める、清掃の当番表をつくるなどが清潔のしくみです。
こういったしくみは職場の責任者が異動などで変わると崩れやすいため、継続的な運用が重要です。
⑤しつけ(Shitsuke・しつけ)
しつけとは「ルールを定め、自ら守り守らせること」です。しつけと聞くと強い印象を持つ方もいるかもしれませんが、定義を知るとイメージが変わるのではないでしょうか。ここでは誰がルールを定めるか、がポイントです。5Sに関するルールは、職場の従業員自身が決めることをおすすめします。職場のルールを自分たちで決めることで、守られやすくなるからです。
トップダウンで決めたルールは現場での納得感が得られにくく、守られにくい傾向があります。置き場や清掃の順番などは、現場の従業員が主体的に決めることで、ルールの定着につながります。
5S活動を行う目的
5S活動を行う目的にはさまざまなものがありますが、この記事では以下の3点に注目します。
- 生産性を高める
- 職場の安全性を高める
- 職場の連携を深める
5Sの本質的な目的は、職場の正常と異常を視える化することです。つまり「職場のいつもと違うところを発見しやすくする」ということです。例えばいるのかいらないのか不明の在庫がたくさんあった場合、今の在庫量が適正かどうかは判断できません。普段から整理ができていれば、在庫の異常な増加にすぐに気付くことができます。
もっと簡単な例を挙げてみましょう。整頓により、共用のはさみ置き場が決まっていたとします。もし業務終了後にそこにはさみが置いていなければそれは「異常」な状態で、紛失にすぐに気づけます。こういった職場の異常を視える化するのが5Sの本質です。これをふまえて目的を見てみましょう。
生産性を高める
ものが溢れ、どこに何があるかわからない汚い現場と、必要なものだけあり、いつでも誰でもものが取り出せる整然とした現場では、生産性に大きな差が生まれます。単純にものを探す時間や取りに行く時間が削減されるだけでなく、最適な配置で一定のリズムで仕事ができることはさらなる生産性の向上につながります。
職場の安全性を高める
ものが溢れていればつまずきや転倒の危険があり、在庫の長期保管、工具の長期使用による劣化は思わぬ災害の原因にもなります。例えば油を使用する設備があったとしましょう。清掃がなされていない場合、ただ通常稼働で発生する汚れなのか、それとも設備に異常があり漏れ出た油なのかは一見区別がつきません。このように、物理的な危険性だけでなく、正常異常の判断ができるという点においても職場の安全性向上に大きく影響します。
職場の連携を深める
なぜ5Sで?と思われるかもしれませんが、5S活動を通じて職場のコミュニケーションは増え、連携が深まります。例えば職場のなかでは、いるものといらないものの区別を個人や自部署だけでは決められないケースが数多くあります。
とある部署では不要でも、隣の部署では必要なものかもしれない。こういった捨てる判断をするのに、必然的に部署をまたいだ会話が必要になってきます。整頓で置き場を決めるときの会話、ルールを決める時の会話、5S活動にはコミュニケーションを深める機会が多く存在します。
5S活動を進める際のポイント
5S活動をするには、押さえておきたいポイントがいくつかあります。ここでは、活動を効果的に進めるために特に重要なポイントを3つ紹介します。
- 活動前:目的を周知する
- 整理:捨てる基準をつくる
- 活動全般:点数をつけて可視化する
活動前:目的を周知する
まずは「なぜ5S活動をするのか」を関係者に周知することが重要です。合わせて本記事にあるような5Sの定義を改めて伝えるのも効果的でしょう。収益面の効果だけでなく、作業がラクになる、探し物が減るなど、メンバーにとってのメリットを伝えることで活動へのモチベーションが高まります。
整理:捨てる基準をつくる
捨てる基準が曖昧だと、整理が進みません。捨てる基準はさまざまありますが、トヨタでは「使用頻度」で判断することが多いです。
例えば、使用頻度を①週一回、②月一回、③年一回などに分けてそれぞれの保管期限と場所を決め、③の期限を超えたら処分するといったルールをつくります。①②③を色分けして視覚的に分かりやすくするのもよいでしょう。基準を明確にすることで、迷わず整理を進めることができます。
活動全般:点数をつけて可視化する
5Sチェックシートを活用し、項目ごとに点数をつけることで、活動の成果が目で見てわかるようになります。前回から何点上がった、というように活動の頑張りを数値で実感することができ、逆に下がった場合は対策しなければという気持ちになれます。また、5S活動は部や課などチーム単位で活動することが多いでしょう。点数にすることで、いい意味での競争が生まれます。隣の課が○点だから来月までに超えよう、など5S活動のモチベーションにつながります。
5Sと安全活動との関係
5S活動は、職場の安全性を高めるうえでも非常に重要な役割を果たします。整理・整頓・清掃・清潔・しつけの各要素が、安全衛生活動と密接に関係しており、予防的な安全管理の基盤となります。
5Sと安全活動の連携例
・整理・整頓
通路や作業スペースの障害物を排除することで、緊急時の避難経路を確保し、転倒や衝突のリスクを低減します。
・清掃
床の油汚れや粉塵を除去することで、滑りやすい箇所や火災の原因となる物質を排除できます。清掃は単なる美化ではなく、異常の早期発見にもつながります。
・清潔
安全チェック項目を標準作業手順に組み込むことで、日常的な安全確認が習慣化されます。例えば、消火器の点検日を定期的に設定するなどのしくみづくりが有効です。
・しつけ
安全ルールの定着には、従業員自身がルールを理解し、守る文化を育てることが不可欠です。安全教育や危険予知(KY)活動を定例化することで、ルールの実効性が高まります。
このように、5S活動は、安全衛生活動と連携することで職場のリスクを事前に察知し、予防的な安全管理を実現できます。たとえば、5S巡回時に危険箇所を報告するしくみを設けたり、KYミーティングで5Sの改善提案を共有することで、現場の安全意識が高まります。
また、ヒヤリハット事例を5S教育に活用することで、実践的な学びにつながり、5Sが「きれいにする活動」から「命を守る活動」へと進化します。
よくある質問(FAQ)
5S導入・運用でよく寄せられる質問に、実務経験を踏まえて回答します。
5Sは製造業以外でも効果がありますか?
はい、あります。医療・介護・オフィス・小売・飲食など、あらゆる業種で成果が報告されています。
例えば、オフィスでは書類・ファイル、あるいは情報の流れを整理整頓することで業務効率が向上したり、医療現場では器材の5Sを徹底することで、看護師1人あたりの処置可能数がアップしたという事例もあります。業種に関わらず、「正常と異常の判断を容易にし、働きやすい環境を作る」という5Sの本質は共通です。
5S活動が続かない、形骸化する原因は?
「やらされ感」と「効果の実感不足」です。対策として、以下の取り組みが重要です。
①経営層のコミットメント
トップ自ら率先参加することで、組織全体の意識が変わります。
②小さな成功体験の積み重ね
まずは1エリアで試行し、効果を可視化することで、納得感が生まれます。
③継続的な評価・表彰
月次で優秀部署を表彰するなど、評価のしくみを取り入れることで、モチベーションが維持されます。
④改善提案の吸い上げ
現場の声を反映することで、自分ごと化が進みます。
また、チェックリストは形式的になりがちです。「なぜこの項目をチェックするのか」目的を明確にし、納得感を持たせることが継続のカギです。
5Sの教育・研修はどうすればいいですか?
段階的教育が効果的です。新人研修、OJT、全従業員向けの定期研修を組み合わせて継続的に実施するとよいでしょう。研修時は、図解や動画などの視覚教材を活用すると理解が深まります。
まとめ
本記事では、5Sの定義や目的、活動のポイントを詳しく解説しました。5S活動は実施そのものが目的ではなく、生産性を高め、安全で働きやすい職場環境をつくるための手段です。
- 整理は捨てること。いる/いらないを区別し、いらないものを処分すること。
- 整頓は置き場を決めること。使いやすいよう置き場を決めて明示すること。
- 清掃は、定期的に清掃し、整理整頓の状態を点検すること。
- 清潔は、整理整頓清掃のしくみを作り、維持すること。
- しつけは、ルールを定め、自ら守り守らせること。
5Sはすべての改善の基礎です。まずはいらないものを減らす「整理」から第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
ジャストインタイム(JIT)とは? 3原則とメリット・デメリットを徹底解説
2025.12.26 -
トヨタ式「自工程完結」で不良ゼロを実現!品質向上と効率化の秘訣を徹底解説
2025.09.12 -
現場の人員配置を最適化するには?実現するための5ステップを解説!
2025.03.07 -
「平準化」と「多能工化」で現場をラクにする!仕事の幅の広げ方とリーダーシップ発揮のコツ
2025.02.28 -
仕事の増加時と減少時の取り組み方!「細分化」と「統合化」で生産性を維持する
2025.02.21 -
改善活動は「困っていること」から取り組む!「4M」の詳細も解説
2024.12.20

PAGE
TOP