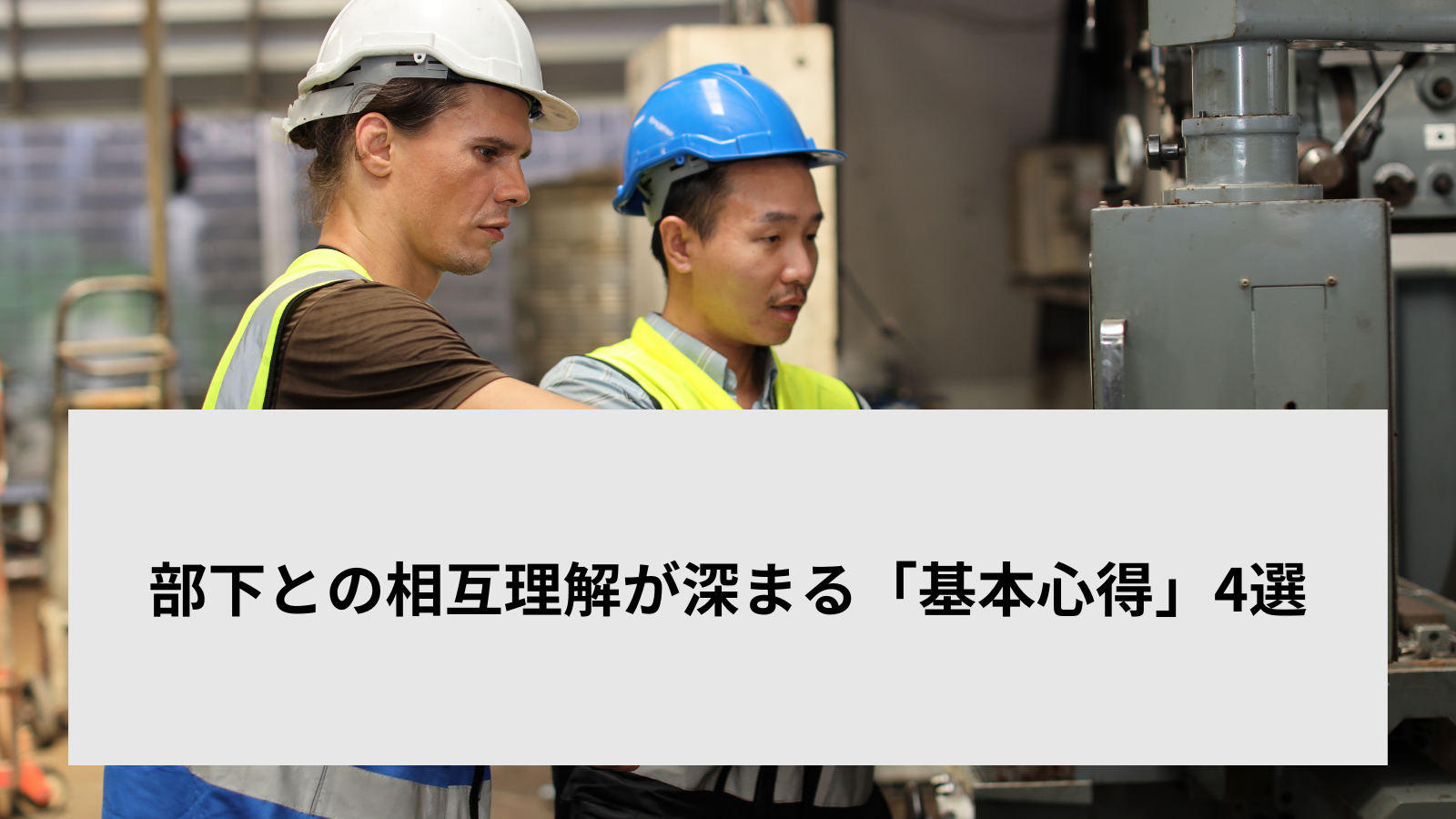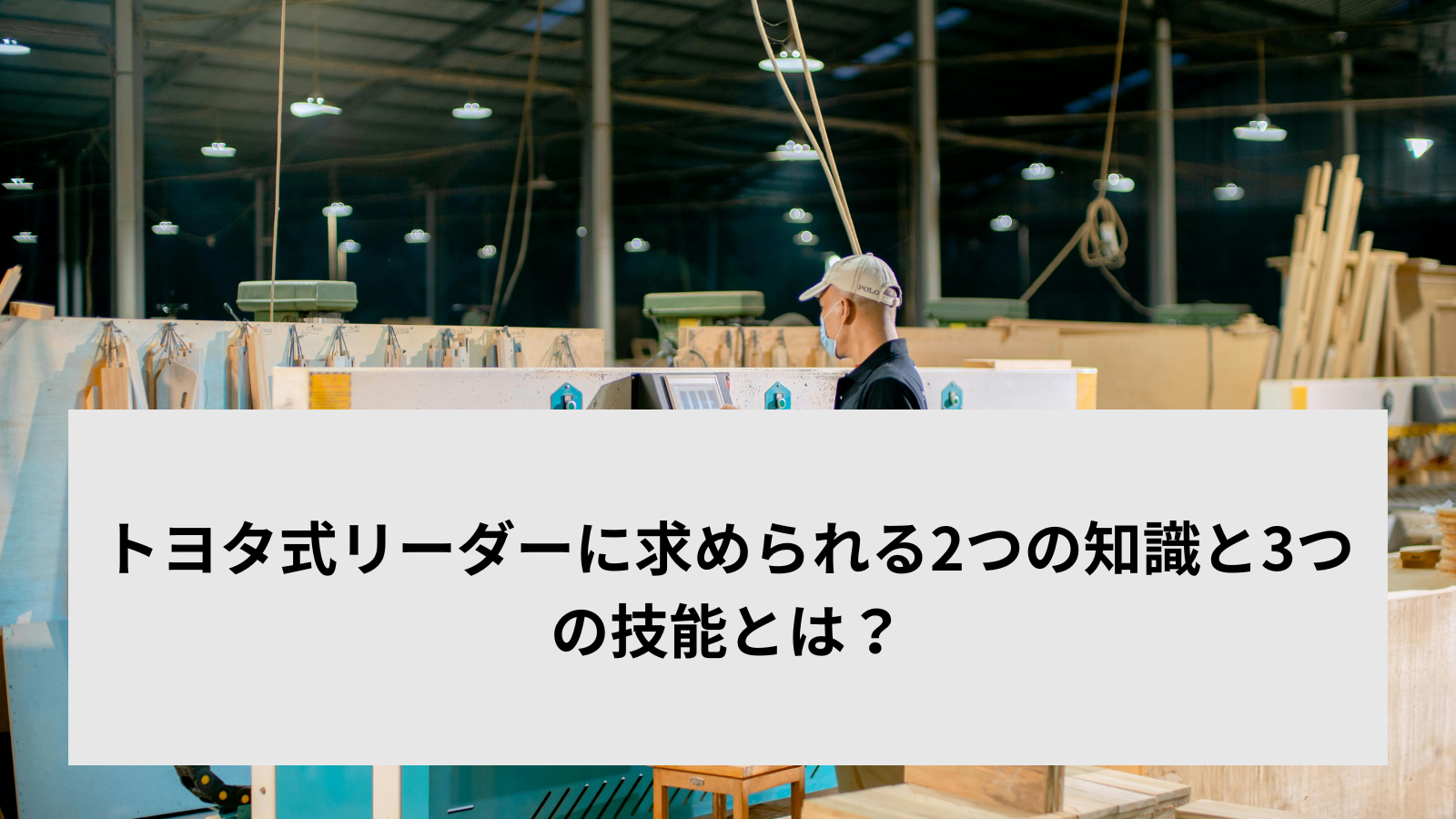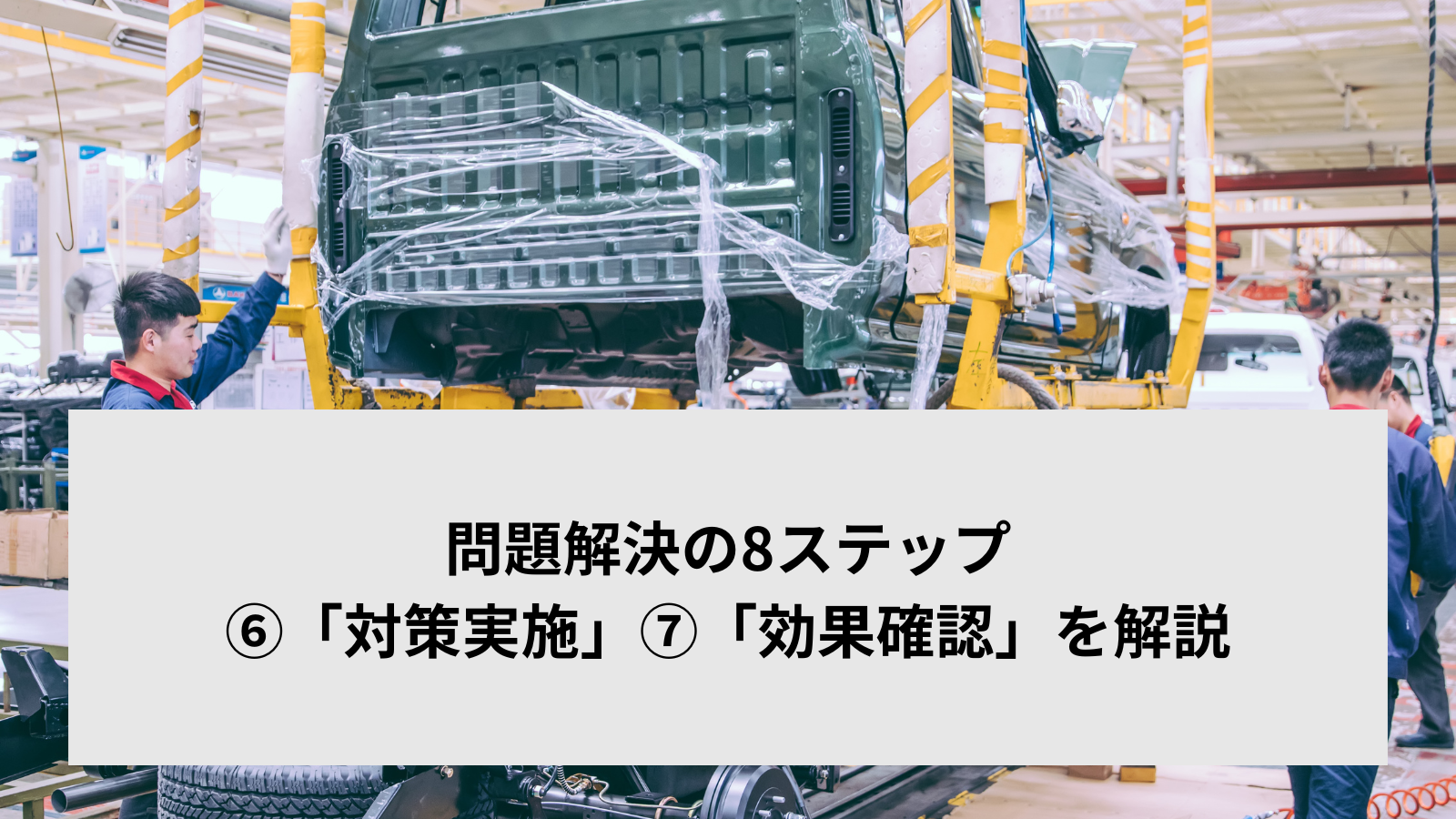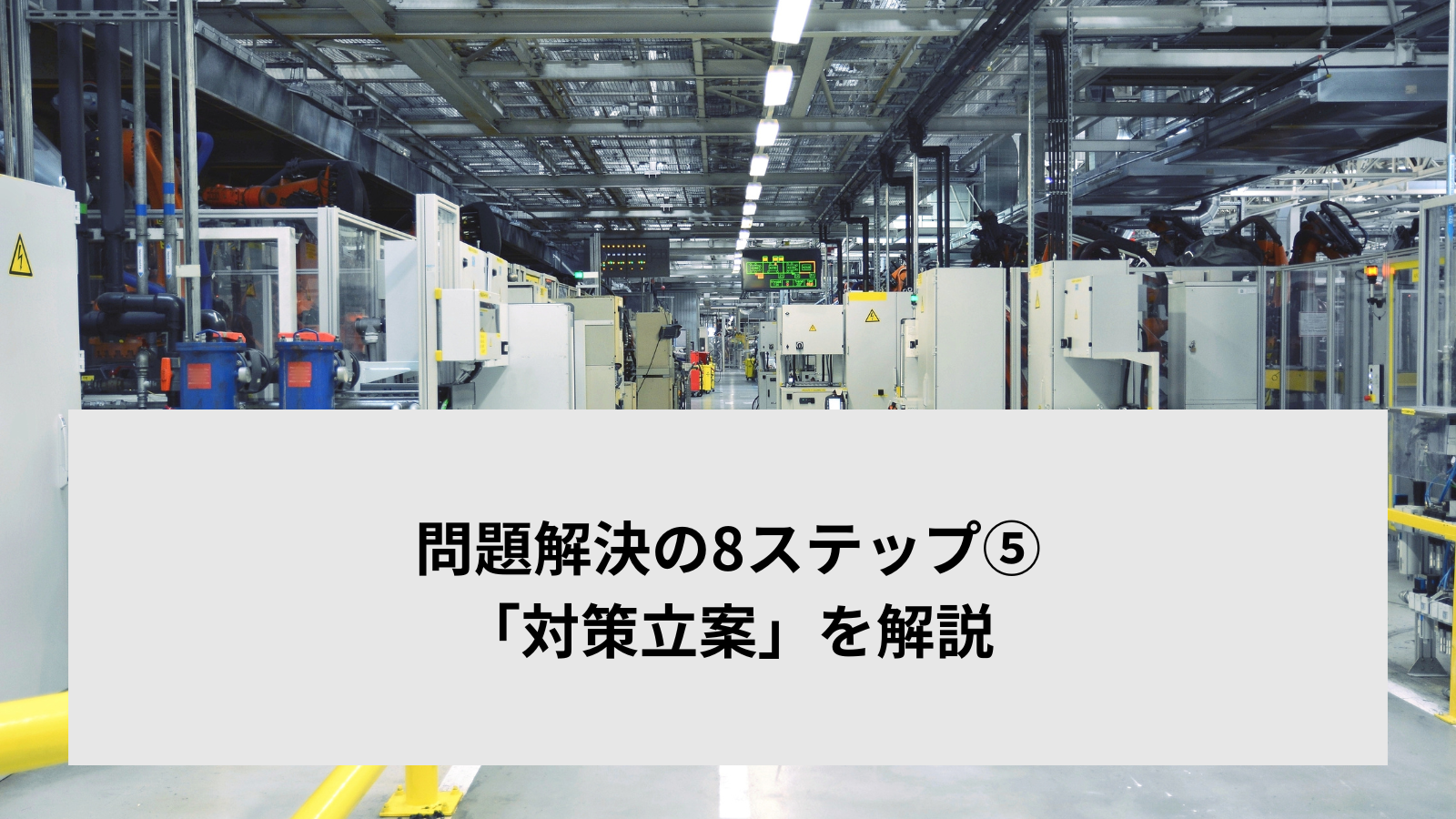OJT
部下との相互理解が深まる「基本心得」4選

監修者
丸山 浩幸
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。大阪府出身、トヨタ自動車の品質管理にて41年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。お客様の現場では「この改善、よかったで!」ともう一声の思いやりを大事に、仲間意識が高まるような改善活動ができるよう日々伴走しています。
本記事では、部下との相互理解を深めるために、トヨタの管理者が日頃から実践している「基本心得」をお伝えします。
お客様の現場で「部下が不満そうにする」「言うことを聞いてくれない」といった悩みをよく耳にします。トヨタでは「人との関係を良くするための基本心得」をもとに、部下と接する際の行動指針を明確にしています。この心得を事例も交えながら解説していきます。
人との関係を良くするための「基本心得」とは?
トヨタでは、「部下は個人として接するべき」という考え方が根底にあります。従業員一人ひとりの価値観や育った環境を尊重し、個人として接することで、その能力を最大限引き出すことが管理者やリーダーの役割です。そのための具体的な行動指針として示されたものが以下4つの「基本心得」です。
- 仕事ぶりがよいかどうか当人に伝える
- よいときは、ほめる
- 当人に影響ある変更は前もって知らせる
- 当人の力をいっぱいに生かす
それぞれの手法について詳しく解説していきます。
① 仕事ぶりがよいかどうか当人に伝える
これは、部下の仕事ぶりに対してこまめにフィードバックすることで、役割が果たせているかどうかを本人に伝えることです。これによって部下は「上司が見てくれている」と感じ、安心感を得ます。
そのために上司は、「相手にどうしてほしいか決めておく」ことと、「もっとよくやれるように導く」ことを実践します。
トヨタでは、会社方針を達成するためにメンバー一人ひとりが果たすべき役割を明確にしています。現場においても、5~6名からなる班のリーダーが各メンバーと話し合い、「どのような仕事をしてほしいのか」「どのような役割を担ってもらうか」を本人と一緒に決めていきます。その内容はリーダーから管理者へ報告され、管理者は報告内容をもとに現場巡回などを行って気づいたことをリーダーにフィードバックします。もっとよくやれるように現場メンバーを導いてあげるのは、リーダーの役割となります。
もし本人に伝えることを怠ると、部下の心理としては「このやり方はあっているのか」と不安を抱えてしまいます。上司が方向性を示し、しっかりとフォローすることで部下との信頼関係構築につながります。
② よいときは、ほめる
部下のよい行動や成果を見逃さず、ほめることが大切です。とはいえ、「ほめる」という行為は、コツを学んだり意識的に機会をつくらないと案外難しいものです。ここでは2つのポイントをお伝えします。
一つ目のポイントは「常日頃のよい仕事やおこないに気を付ける」ことです。メンバーの働きは、営業成績のように数値化できるものばかりではありません。例えば、日頃から休憩室の整理整頓をしてくれているなど、常日頃の目立ちにくい仕事やよいおこないに対してもしっかりと気を配ることが大切です。
ある管理者の事例では、1日に2回程度の現場巡回をおこない、そのときに「不良を発見してくれてありがとう、また頼むね」などとメンバーに声をかけていました。仕事が多すぎて巡回ができない管理者は、1日のスケジュールを紙に書いて視える化してみてください。隙間時間や削れる時間を見つけることができ、巡回の時間を捻出できます。
二つ目のポイントは、「適切な時期を逃さずほめる」ことです。仕事やよいおこないがあってから時間が経たないうちにほめることが重要です。また、機会があれば大勢が集まっている際にほめましょう。一人でいるときにほめられるのと、大勢が集まっているときにほめられるのでは、ほめられたうれしさの感じ方が異なってきます。
③ 当人に影響ある変更は前もって知らせる
異動や役割変更など、部下に影響のある変更事項は事前に説明し、納得感と心構えの時間を与えることが重要です。上司から突然、異動や役割変更などを言われて、「急に言われても納得できない」と不満を持った経験がある方もいると思います。前もって詳しい説明があれば、納得する時間と心の準備ができます。
また、一般的には現場メンバーに対する辞令は部長などの役職者から伝えることが多いと思いますが、トヨタでは部長などが直接説明するのではなく、部長は課長に、課長は工長に、工長は組長にと、段階を追ってそれぞれがしっかりと話し合ったうえで決めていき、最終的に一番気心の知れた組長が現場メンバーに説明をおこないます。
急な変更ほど不満につながりやすいため、日頃から丁寧な説明とコミュニケーションが不可欠です。
④ 当人の力をいっぱいに生かす
部下一人ひとりの適性や能力を把握し、それを最大限活かせる配置や役割分担をおこなうことが重要です。
ある現場の事例を紹介します。メンバーのAさんは、実作業は丁寧にできるものの作業スピードが遅く、前後の工程にも影響してしまうため全社的な残業につながってしまっていました。またそのことで、本人のモチベーションの低下にもつながってしまうといった問題がありました。
一方で、Aさんは改善の取り組みに対しては毎回会社から大きな評価を受けていました。そこで、今の実作業量を半分に減らし、社内改善を主業務とする配置転換をおこなった結果、改善したことが次々と社員全員に喜ばれ、本人のモチベーションにもつながり、いきいきと働けるようになりました。
管理者やリーダーはメンバーの隠れた才能や仕事に関連した得意なものを見つけ出し、そこをほめて伸ばすことが重要となります。しかし配置転換は人材不足などの理由で難しいケースもあるかもしれません。その場合は、工程業務をすべて知っている「リーダー」がカギとなります。リーダーがしっかりとバックアップしながら、全体のバランスを調整してあげることで、適切な配置が可能になります。
まとめ
部下との相互理解を深め、よりよい人間関係を構築するための行動指針として、トヨタには4つの「基本心得」があります。
- 仕事ぶりがよいかどうか当人に伝える
- よいときは、ほめる
- 当人に影響ある変更は前もって知らせる
- 当人の力をいっぱいに生かす
「基本心得」を実践するには、現場とのコミュニケーションが重要です。日頃から現場メンバーの細かい仕事や変化にも気付けるよう、現場巡回の時間を確保することも大切です。
これらの取り組みはトヨタが大切にしている人間性を尊重した働きやすい職場づくりにつながります。部下の心をつかむ接し方として実践してみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタ式リーダーに求められる2つの知識と3つの技能とは?
2025.09.26 -
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介
2025.09.05 -
問題解決の8ステップ⑧「標準化・再発防止」を解説
2025.08.22 -
問題解決の8ステップ⑥「対策実施」⑦「効果確認」を解説
2025.08.15 -
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
2025.08.08 -
問題解決の8ステップ④「要因解析」を解説
2025.08.01

PAGE
TOP