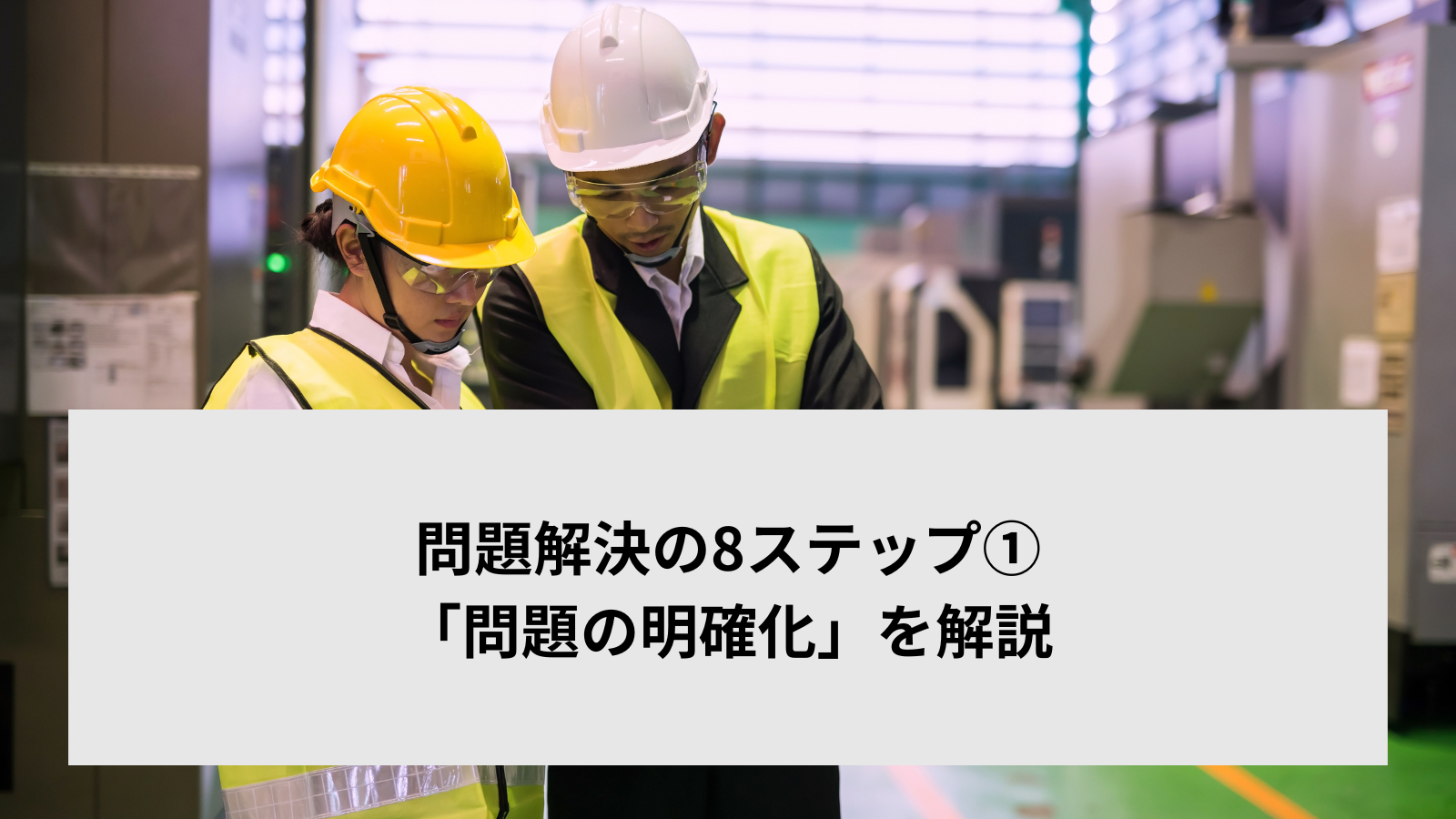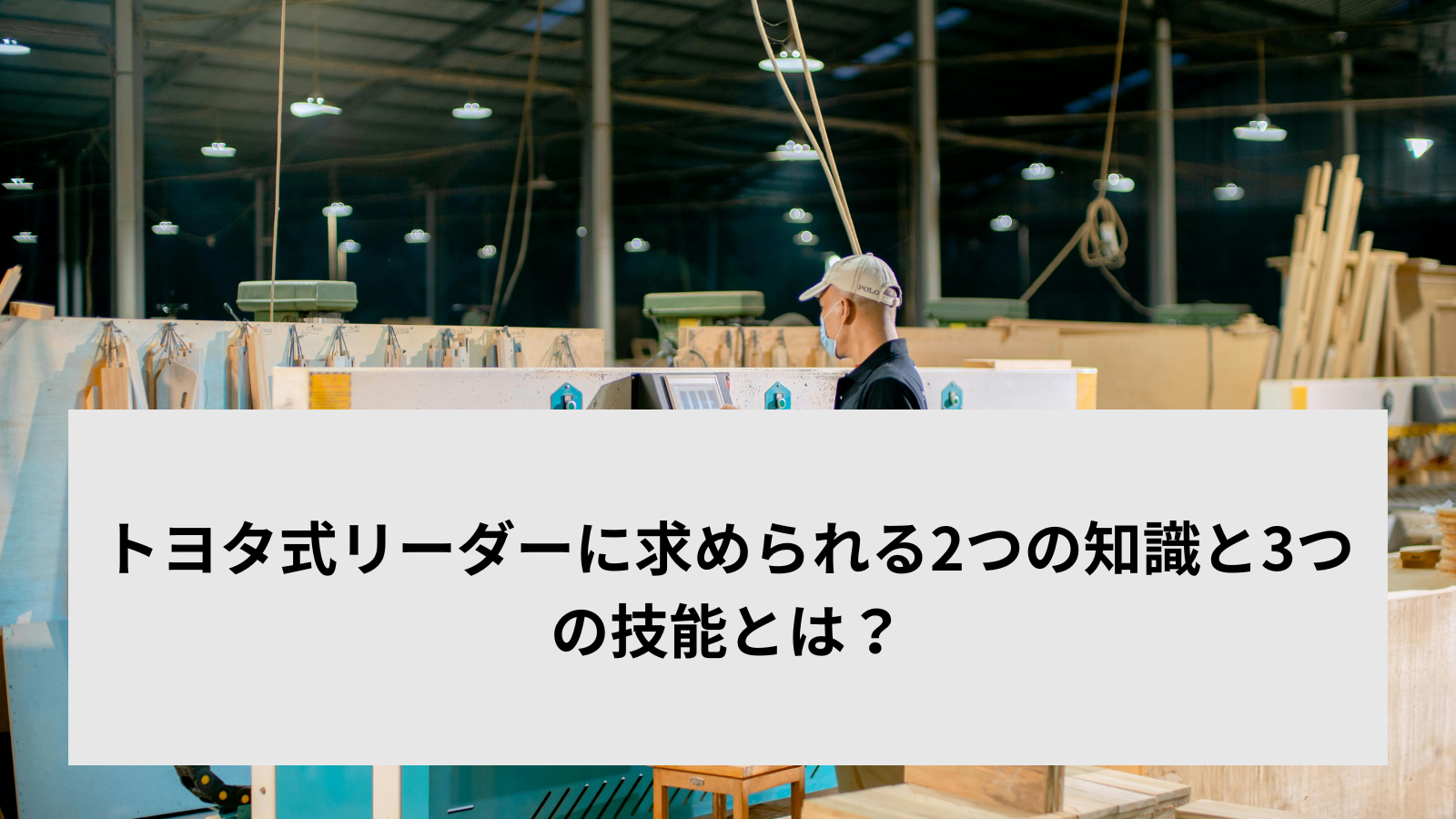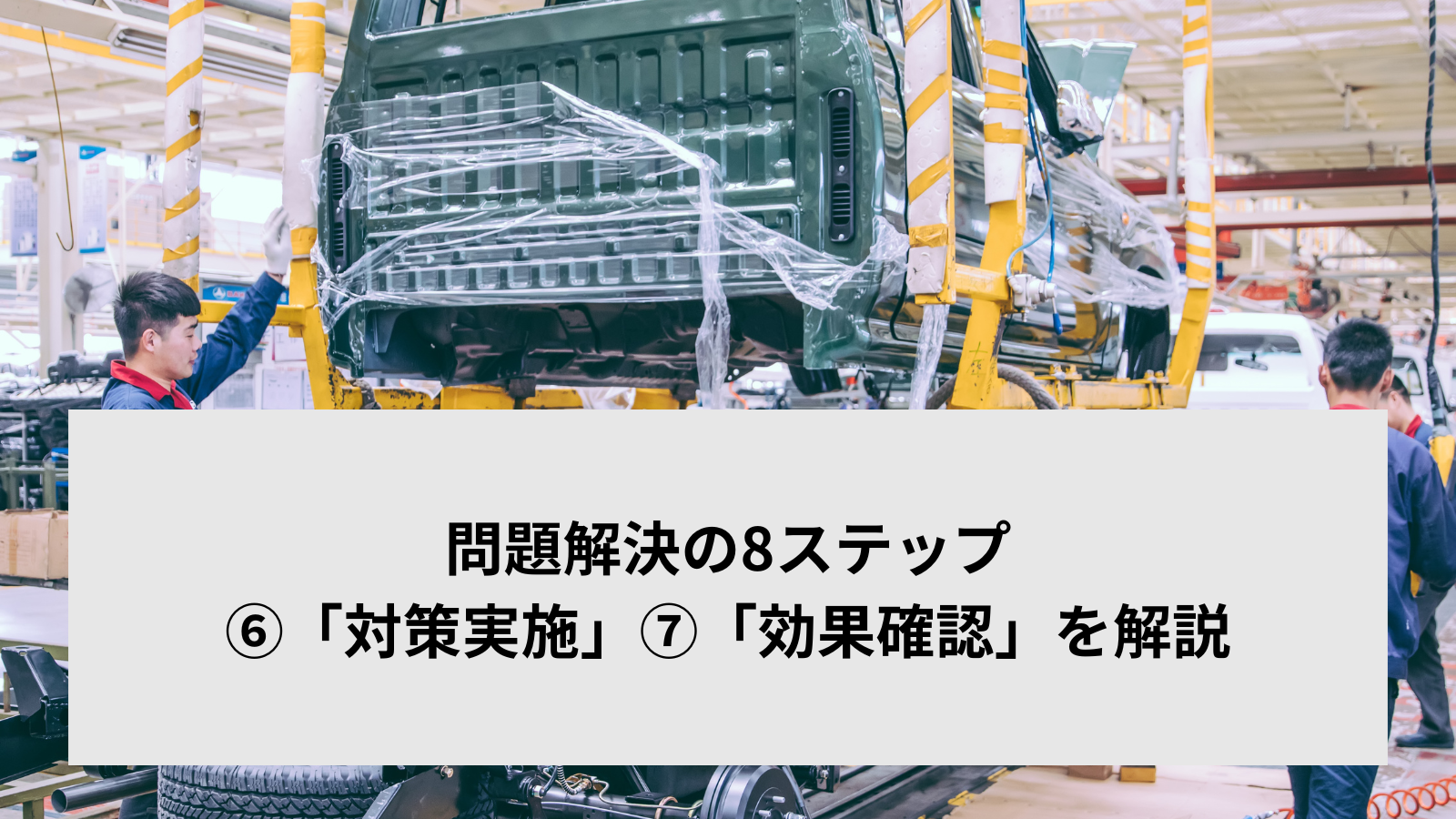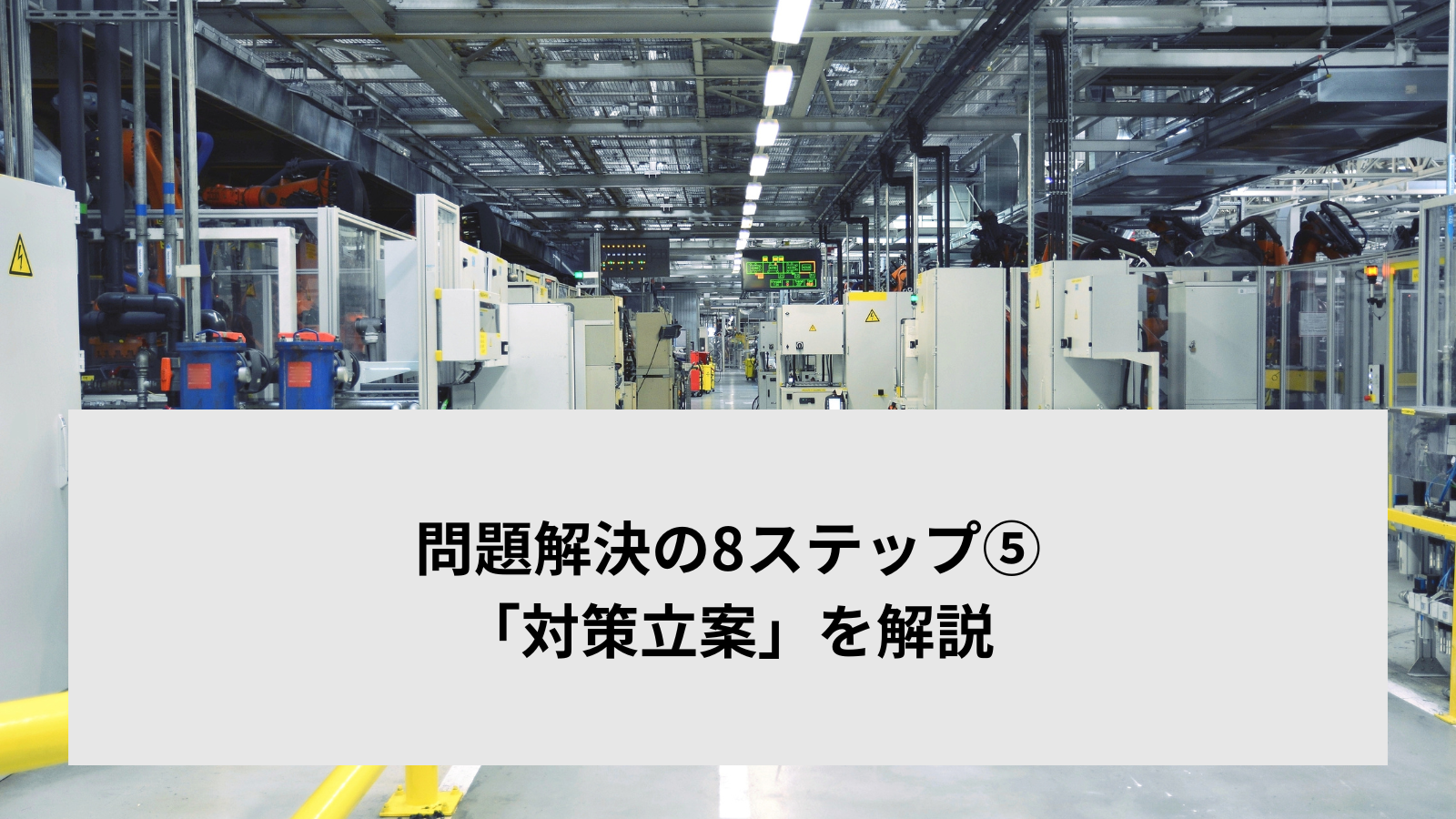OJT
問題解決の8ステップ①「問題の明確化」を解説

監修者
見城 吉昭
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車の機械加工にて39年の現場経験を積み、OJTソリューションズに入社しました。趣味の読書や旅行で自分の世界を広げながら、現場で働く人の声を大事に「働く人の心のための改善」に日々取り組んでいます。
「問題解決の8ステップ」は、トヨタで実践される問題解決の思考法です。8つのステップを踏むことで、解決までのプロセスを着実に進めます。
- 問題の明確化:何が問題かを考える
- 現状把握:現状を理解する
- 目標設定:何を目指すか決める
- 要因解析:なぜ起きるか考える
- 対策立案:対策案を考える
- 対策実施:対策を実行する
- 効果確認:効果を確認する
- 標準化・再発防止:後戻りを防ぐ
論理的な思考による一連のステップを踏むことで、勘や経験による思い込みを排除し、効率的に問題を解決することができます。
参照記事:問題解決の8ステップとは?トヨタの問題解決プロセスを解説
本記事では、8つのステップの「問題の明確化」について詳細に解説します。
解決すべき問題を明確にする基本プロセス
問題解決の最初のステップは、解決すべき問題テーマを明確にすることです。このステップ1と、次のステップ2の「現状把握」は非常に重要であり、このプロセスが問題解決の成否を決めると言ってもよいでしょう。
しかし、多くのケースでは、このステップを飛ばして、問題テーマや対策が先行してしまうことが少なくありません。これでは「本当の問題」を解決することはできません。
トヨタでは、「問題が何であるか」という切り口から十分に分析し問題を明確にしてから、その解決策を考えていきます。問題解決を「問題ありき」で進めると、実際に解決すべき問題ではない可能性が高く、結果として成果が上がらないことがよくあります。問題テーマを設定するには根拠が必要であり、根拠のない問題は実際には問題ではない可能性が高いのです。
また、設定する根拠を考える時に考慮することの一つとして、「企業理念」に照らして考えることも大切です。「仕事の目的」ととらえてもよいでしょう。設定するテーマが、企業理念の遂行に合致しているか?これを確かめ、企業の向かう方向性とベクトルが合っているかも検証しましょう。
「対策ありき」ではうまくいかない
「問題ありき」がうまくいかないことと同様に、「対策ありき」で問題解決に取り組むことも、うまくいきません。対策が先に決まってしまうと、対策を施すこと自体が目的となり、本来の問題が解決されない可能性があるからです。
例えば、流行や他社の成功を理由にした対策を先に決めてしまうと、その対策に合わせた問題を設定することになり、的の外れた問題解決につながる恐れがあります。
本来は「本当の問題」から「困っている状態」を経て「問題テーマを決定する」、そして「対策」というプロセスを踏まなければなりません。
「数字」でとらえる
解決すべき問題テーマを選ぶ段階では、「やりたいこと」ではなく「やるべきこと」に焦点を合わせるのが原則です。本来、問題解決は経営の視点から見て、足を引っ張っている問題を解決することが目的であり、それらは重要度も緊急度も高いため、苦痛をともなうものです。
やるべきことをテーマとして選ぶには、「想い」ではなく「数字」などのデータに基づいて問題をとらえることが大切です。例えば、クレーム数、不良率、作業時間、売上、利益率など、数字に異常があれば問題が発生している確かな証拠となります。このようなデータから、あるべき姿のレベル数値と現状の数値を明確にし、そのギャップ(差)を定量的に表すことが、問題を明確化するということです。
肌感覚で「最近、稼働率が悪い」「なんとなくクレームが増えたような気がする」と感じるだけでは、深刻な問題として意識できません。一方で、「稼働率が8%落ちている」「クレームが前年対比20%増えている」と数字でとらえることにより、「この問題と向き合わなければ」という意識が高まり、危機感を持って問題解決に取り組むようになります。
問題を発見する7つの視点
問題を正しく認識し、発見するためには視点が必要です。意識するとよい視点を7つ紹介します。
悩んだり困っていること
普段、自分や職場で悩んでいること、困っていることをすべて書き出すことから始めます。トヨタでは「問題発見シート」というツールを使い、職場のメンバー同士で意見を出し合います。例えば「クレーム品が多い」「顧客情報が共有されていない」「残業が多い」など、職場全体、個人レベルを問わず出された中から、重要な問題を決めていきます。
問題を見つける手がかりとして、製造業でよく用いられる「4M」の視点(Man:人、Machine:機械、Material:材料、Method:方法)で考えると、漏れなく整理しやすくなります。
上位方針との比較
会社や部署の目標や方針と、自分がおこなっていることや自分の部署の現状を比較することで、問題が見つかりやすくなります。例えば、会社の年間売上ノルマが前年比10%増であるのに、自分の部署の成績が3%増に留まっている場合、このギャップが問題となります。
後工程への迷惑
次の工程や上司、顧客からクレームや注意を受けた場合、それは明確な問題としてとらえる必要があります。特に顧客からのクレームは安易な対処療法ではなく、重要な問題として向き合うことで優先度の高い問題テーマが見つかりやすくなります。
基準との比較
「基準」とは、正常であることの判断軸となるもので、数値化が可能です。本来あるべき規格や仕様とズレが生じている場合は異常な状態であり、問題が発生しているととらえる必要があります。
標準との比較
「標準」とは、現時点で最もよいとされる作業のやり方や条件を指します。職場で定められた各作業のやり方や条件が守られていない場合、そこに問題がある可能性が高まります。
過去との比較
過去の数値や状態と比べて、現在の状況が悪化していないかを確認します。例えば、昨年の不良率が3%だったのに今年は5%に上昇していたら、そこに問題があるととらえることができます。
他部署との比較
社内の他部署と数値や状態を比較することで、自分の部署のやり方に問題がないかを見つけ出します。例えば、書類の記入ミスが他部署と比べて際立って多い場合、自部署のやり方に問題がある可能性が高いといえます。
これらの視点を通じて問題をとらえることは、経験や勘に頼らず、客観的なデータや数字に基づいて論理的に思考・分析し、効率的に問題解決をおこなううえで重要です。
問題テーマを絞り込む3つの視点
職場には常に複数の問題が潜んでいるものです。それらが同時に発生したり、見過ごされているケースも少なくありませんが、すべての問題を一度に解決しようとするのは現実的ではありません。
トヨタでは、問題解決は基本的に一つの問題テーマに絞り込み、一つずつ順番に解決していくことを基本としています。絞り込む際は、次の3つの視点から評価することが多いです。
- 重要度:問題が及ぼす影響の範囲と大きさ
「重要度」とは、その問題がどの範囲に、どれくらいの大きさで影響を及ぼすかという視点です。影響の範囲で例えると、製品の品質やサービスの低下など、職場内ではなくお客様に迷惑をかけるような問題は「重要度が高い」と判断すべきです。
また、品質の悪化、原価の上昇、納期遅延といった問題は、企業の信用を損ねたり、経営を圧迫したりするなど、その影響が計り知れないほど大きくなる可能性があります。これらは速やかに対処すべき問題といえます。 - 緊急度:ただちに手を打たないとどうなるか
「緊急度」とは、その問題に対してただちに手を打たなかった場合、どのような悪影響が及ぶかという視点です。例えば、もし放置したままでいると「目標が未達成で終わってしまう」「生産変動に対応できない」「お客様のクレームにつながる」といったケースは「緊急度が高い」と判断できるでしょう。 - 拡大傾向:放置した場合の不具合の広がり
「拡大傾向」とは、もしその問題を放置してしまったら、不具合がどれだけ広がる可能性があるかという視点です。
例えば、ある部署で特定の不具合が多発していて、このまま対策を打たなければ、類似の不具合が他の部署でも発生する危険性がある場合は、早急に対処しなければならない「拡大傾向」が高い問題と見なされます。
複数の視点から問題を評価する
これらの3つの視点(重要度、緊急度、拡大傾向)を使って、複数ある問題テーマを総合的に評価することが重要です。評価は「◎(高)」「〇(中)」「△(低)」などの記号を用いておこない、「◎」が多いものから優先的に取り組みます。
なお、指標はこの3つに限定する必要はなく、例えば「実現可能性」などその職場で重視する項目に置き換えてもよいでしょう。ポイントは、複数の視点から判断することです。そうすることで具体的に問題の大きさを浮き彫りにできます。
問題テーマ選定の理由をデータで明確にする
問題テーマを選定する際は、その理由を明確に説明できることが不可欠です。この理由が曖昧だと、問題の重大性が認識されず、問題に対する危機感も薄れてしまう可能性があります。
トヨタでは、問題テーマを選定する際に、以下の3つのポイントをチェックします。
- 「なぜこの問題テーマを取り上げたのか」を明確に説明できるか。
- 前述の「重要度・緊急度・拡大傾向」の3つの視点から理由を挙げられるか。
- 重要度・緊急度・拡大傾向を「データ」で示せるか。
例えば、「クレーム品の発生を減らす」という問題テーマであれば、「工場別でワースト1位」(重要度)、「このままでは目標を達成できない」(緊急度)、「さらに悪化する可能性が高い」(拡大傾向)といった現状を具体的なデータで示し、裏付けを取ります。
オフィスワークなど、データ化が難しい職場でも、できる限り定量化する工夫をすることで、問題が明確になり、その重大性を共有しやすくなります。例えば、残業時間を減らす問題であれば、期間ごとや部署ごとの残業時間のデータを用意します。
データで示されることで、メンバーは「やらなければならない」と腹落ちし、モチベーションを持って問題解決に取り組むことができます。
すでに問題が明確な場合は
実際の現場では、機械の不具合や売上目標の未達など、問題テーマがすでに明確である場合もあります。このように問題が目の前で起こっているとき、すなわち「発生型問題」であれば、問題発見の一部ステップをスキップすることもあります。
しかし、その場合でも、「なぜ数ある問題の中からその問題を選んだのか」を明確にしておくことが重要です。また、複数人で問題解決をおこなう場合は、情報共有のためにもステップ1(問題の明確化)を飛ばさない方がメリットが大きいです。
問題の種類や緊急度、取り組む人数に応じて、ステップに取り組むかを決めるとよいでしょう。
まずは「自分の頭で考える」環境をつくる
問題解決に取り組むことは、特に初心者にとって、解決すべき問題テーマの選定からして難しく感じられるかもしれません。しかし、誰もが試行錯誤を繰り返しながら、徐々にそのスキルを習得していくものです。
まずは「思いつき」から思考を始める
問題解決に慣れていない人が最初の一歩を踏み出す際には、まずは“思いつき”でもいいから問題について考えます。もちろん、”思いつき”だけでは本当の問題解決にはつながりませんが、問題解決に対して苦手意識がある人にとって、何よりもまず「自分で考えてみる」ことが重要です。
自分の頭で知恵を絞ることで、初めて問題が見えてきます。難しそうだと感じても、まずはメモを取るなどして、頭を働かせてみましょう。自分の頭で考えることこそが、問題解決が上達する最初のステップとなります。
私生活の身近な問題でトレーニングする
また、問題解決に抵抗を感じる場合は、仕事以外の私生活の分野で問題テーマを見つけてトレーニングすることも有効です。トヨタでは、新入社員のうちから問題解決の考え方を徹底して教育されますが、仕事の内容をあまり理解していない段階では、仕事以外のテーマを選んで問題解決に慣れ親しんでもらいます。
例えば、「ボウリングで高スコアを上げる」というテーマで問題解決の基本を学んだ新入社員もいました。トヨタのモットーである「現地現物」に沿って、実際にボーリング場に頻繁に通うことで、問題解決に対する興味を持つようになりました。
このように、自分が興味のある身近なテーマで問題解決のステップを学ぶことも、慣れるための一つの方法です。
リーダーは「人を責めず、しくみを責める」環境をつくる
従業員の問題解決力を向上させる側の経営陣や上司は、部下が自らの頭で考えられるような環境を整え、フォローする姿勢を忘れてはなりません。
人は都合の悪いことを隠したり、面倒なことは手を抜こうとするものです。部下が問題解決に取り組むなかで、直視したくない問題に直面することもあるでしょう。
そのような時に、上司が「なぜ、こんな状態になっているんだ!」「今まで何をしてきたんだ!」と感情的に怒ってしまえば、部下は萎縮し、問題を隠そうとするようになります。これでは、問題解決をするための「考える力」は育まれません。
重要なのは、「人を責める」のではなく、その問題を引き起こしている「しくみ」に焦点を当てることです。そして、上司と部下が一緒になって問題解決に取り組む姿勢が必要となります。このような環境があって初めて、従業員一人ひとりが安心して「自分の頭で考え」、問題解決に主体的に取り組めるようになります。
まとめ
問題解決の出発点は、「本当の問題は何か」を見極めることにあります。問題解決の8ステップにおける第一のステップ「問題の明確化」は、全体の成否を左右する極めて重要なプロセスです。経験や勘、あるいは対策ありきで動き出してしまうと、根本的な課題を見誤り、結果的に時間と労力を浪費してしまうことになりかねません。
正しい問題設定のためには、数字や客観的な事実に基づいて問題をとらえ、複数の視点から評価し絞り込むプロセスが必要です。「なぜ今この問題に向き合うのか」という理由を定量的に示すことで問題が明確になり、取り組む重要性を共有することができます。
本質的な問題解決には時間と手間がかかりますが、それこそが真の改善への道です。焦らずに丁寧に、一つひとつのプロセスを積み重ねていくことで、再発を防ぎ、継続的な成果につながっていきます。まずは自分の周りの「違和感」や「困りごと」から、ぜひ実践してみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタ式リーダーに求められる2つの知識と3つの技能とは?
2025.09.26 -
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介
2025.09.05 -
問題解決の8ステップ⑧「標準化・再発防止」を解説
2025.08.22 -
問題解決の8ステップ⑥「対策実施」⑦「効果確認」を解説
2025.08.15 -
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
2025.08.08 -
問題解決の8ステップ④「要因解析」を解説
2025.08.01

PAGE
TOP