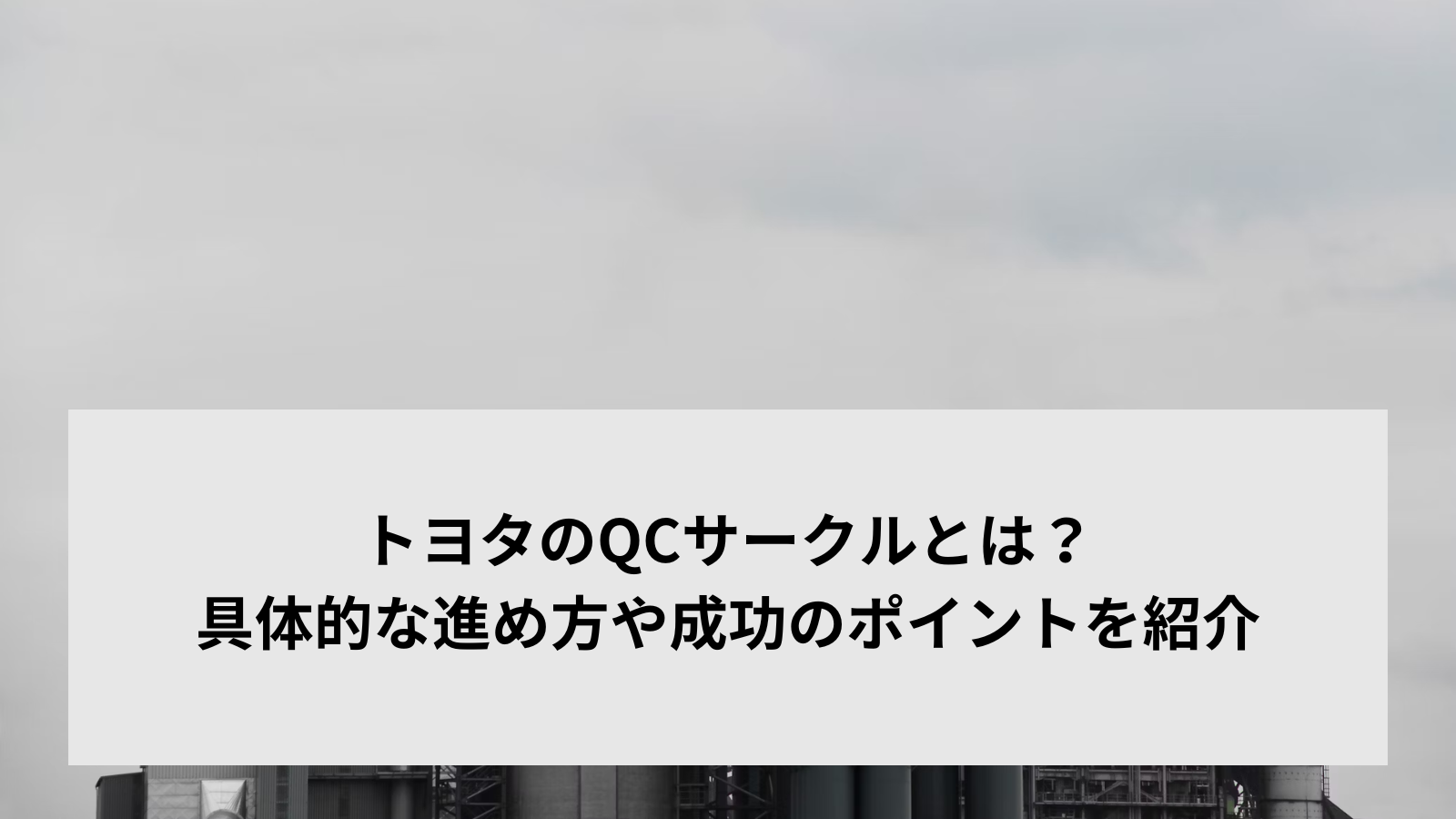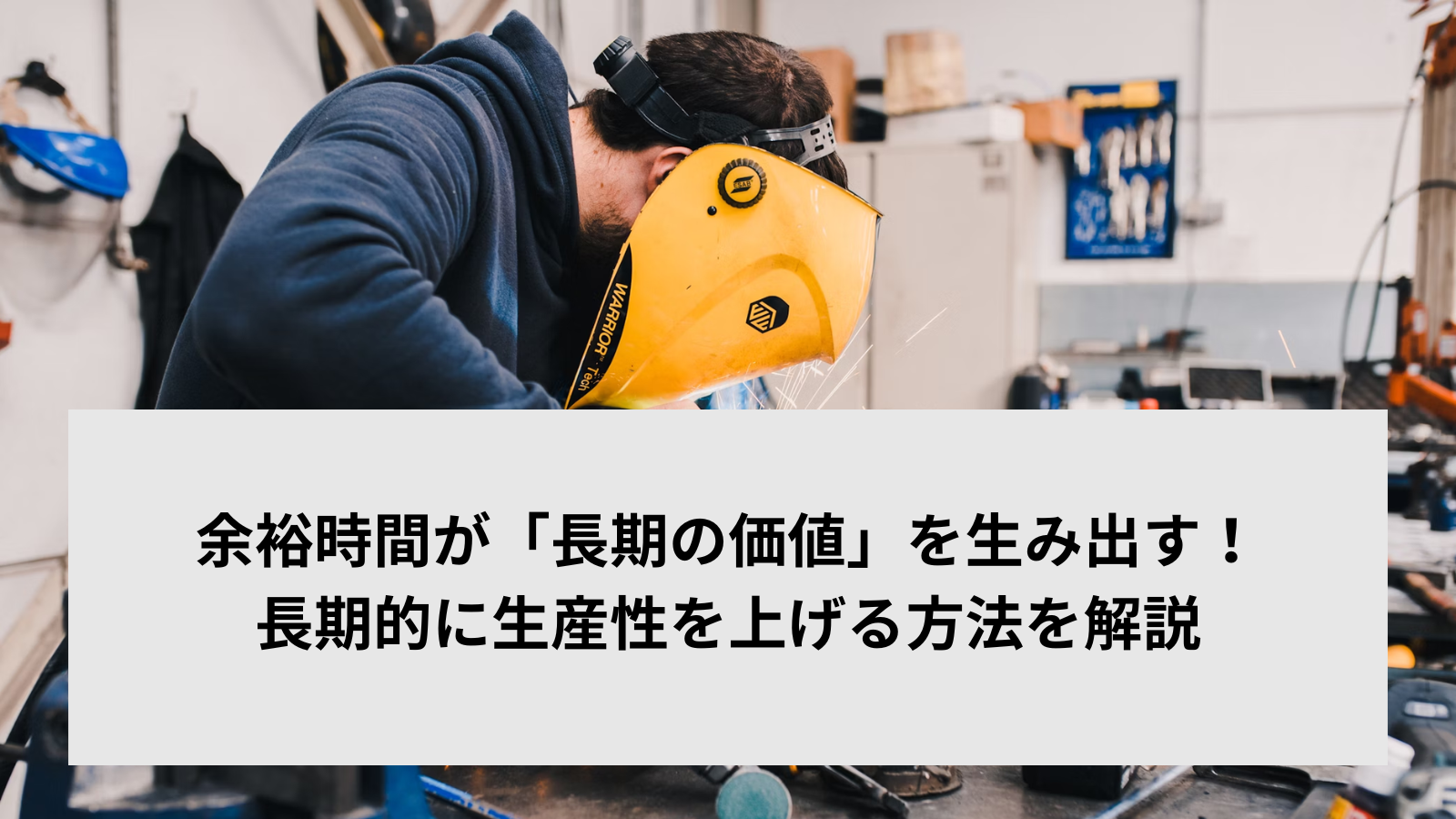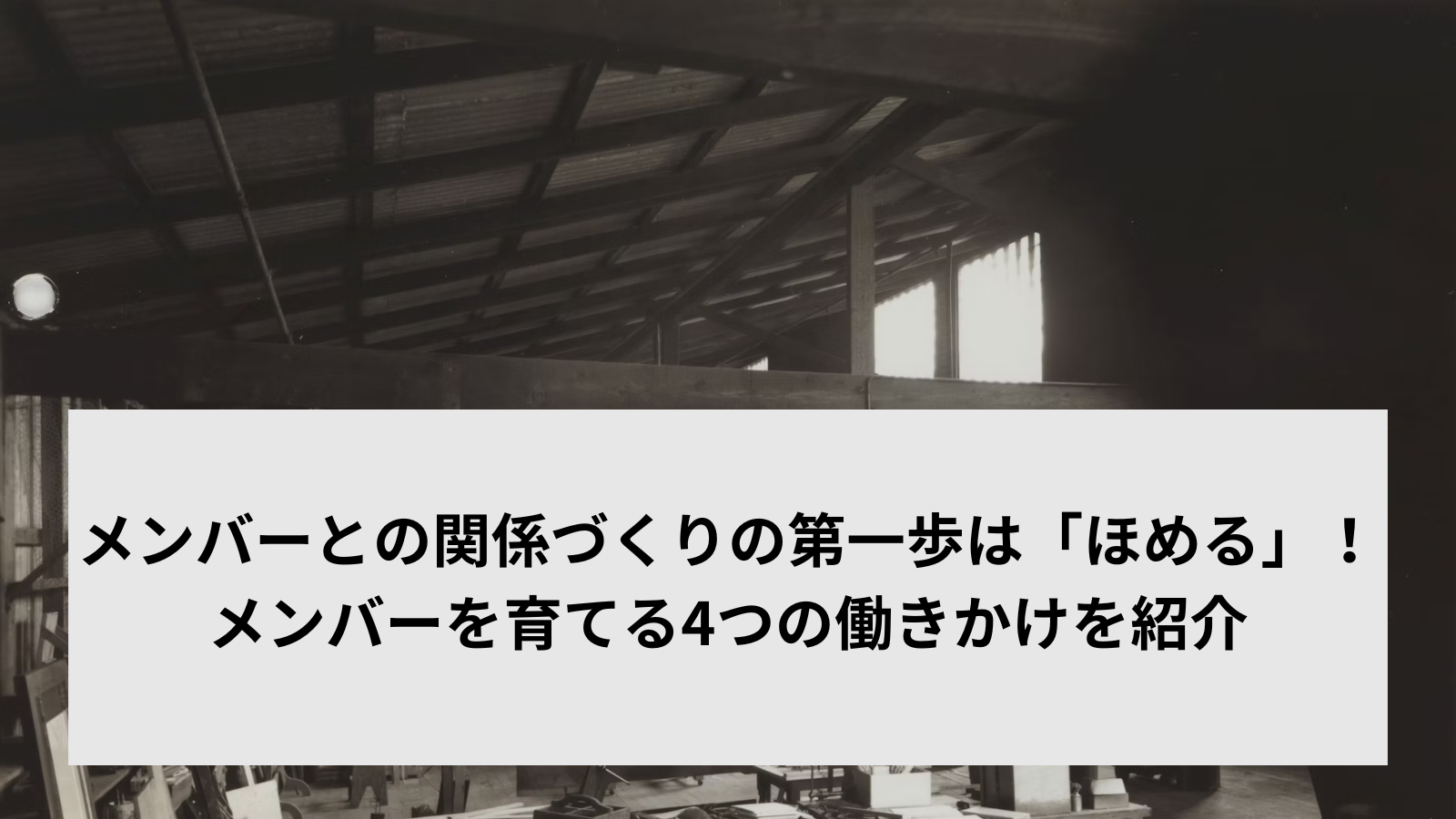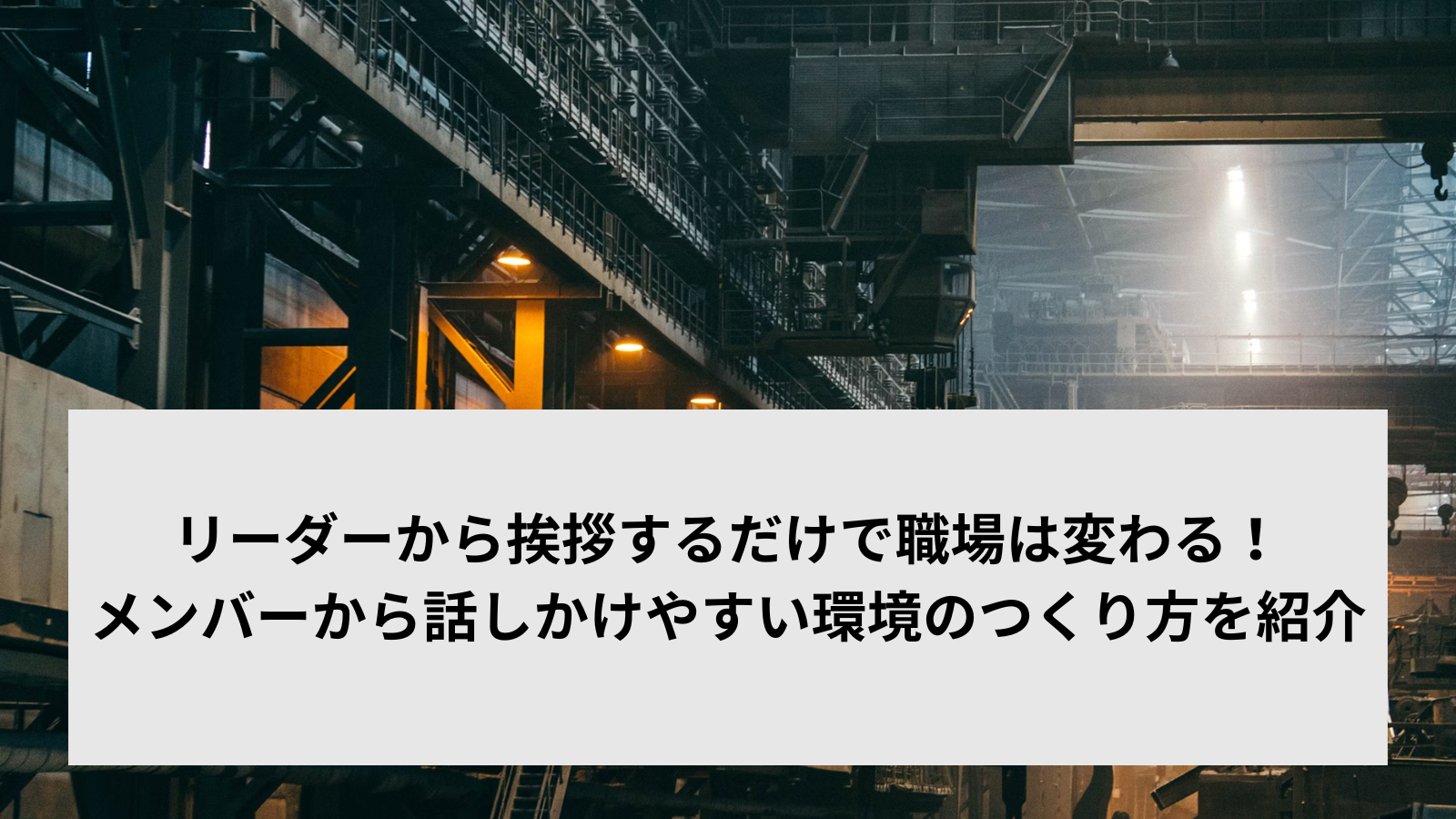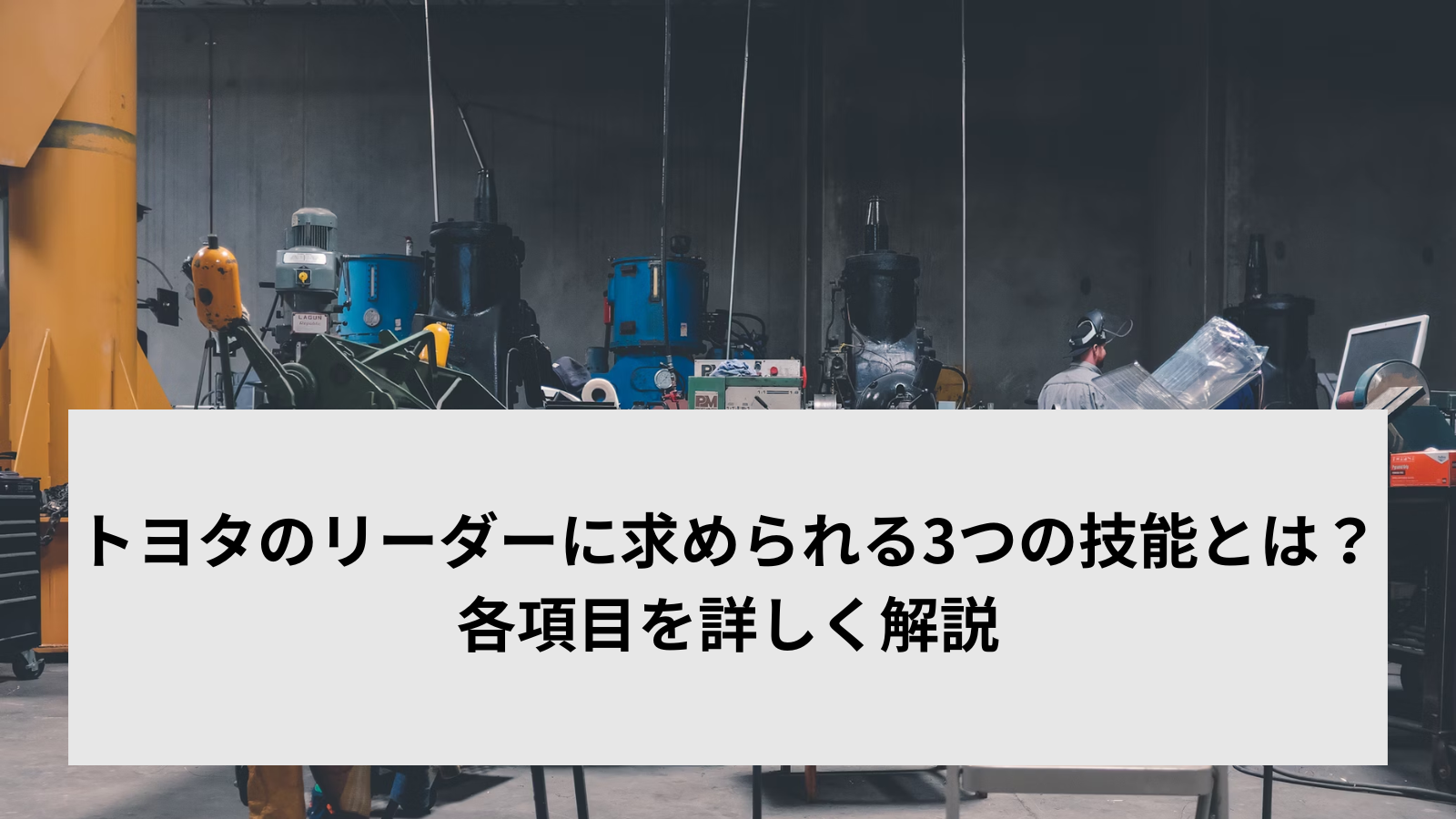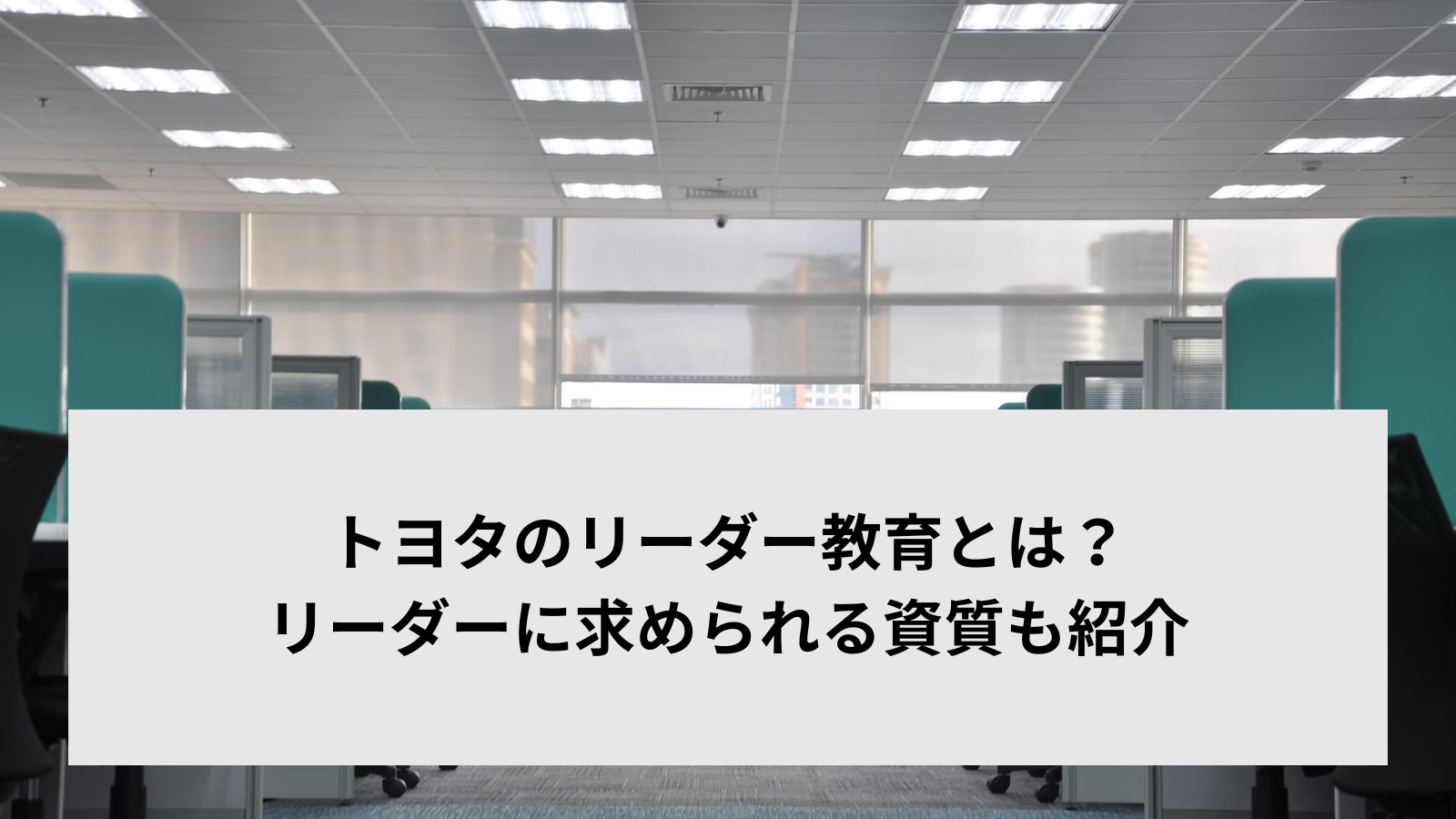人的資本経営
トヨタのQCサークルとは?具体的な進め方や成功のポイントを紹介

監修者
丸山 浩幸
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。大阪府出身、トヨタ自動車の品質管理にて41年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。お客様の現場では「この改善、よかったで!」ともう一声の思いやりを大事に、仲間意識が高まるような改善活動ができるよう日々伴走しています。
トヨタでは「QCサークル」という小集団の改善活動をすべてのメンバーを対象におこなっています。サークル数は5000以上、活動年数は60年以上と長い歴史を持つ重要な活動です。トヨタにおけるQCサークルの大きな特徴は、「職場の活性化」に目的を置いていることです。
多くの企業がQCサークルに取り組んでいるものの、マンネリ化や形骸化によりうまくいかない現状にお悩みかもしれません。本記事ではトヨタのQCサークルの概要をはじめ、具体的な進め方や成功のポイントを紹介します。
トヨタのQCサークルとは?
そもそも、QCサークルとは全社的な品質管理活動の一環として、現場の従業員が自発的に小グループで行う改善活動のことをいいます。
トヨタのQCサークルは、1961年より取り入れられた歴史の長い取り組みで、参加対象は全従業員です。5000以上ものサークルが存在し、職場で発生している自分たちが改善したい問題をテーマにした活動で、その大きな目的は「職場の活性化」です。
多くの企業でもトヨタのようにQCサークルを取り入れているものの、なかなかうまくいかずお悩みの方も多いかもしれません。トヨタではQCサークルをうまく稼働させるために、「目的の持たせ方」と「経営・管理層の関与のしかた」に重きを置いています。マンネリ化や形骸化してしまっている企業の方は、まずこれら2点がどのようにおこなわれているか、一度振り返ってみてください。
QCサークルの目的は「職場の活性化」
QCサークルをおこなう際は、目的をしっかりと理解する必要があります。多くの企業ではQCサークルに金額的効果を求めすぎている現状があります。金額的効果は、経営視点ではたしかに重要ですが、求めすぎるとやらされている感が生まれ、次第に衰退していってしまうため注意が必要です。
トヨタにおけるQCサークルの目的は「職場の活性化」です。
サークルの中で、①問題意識を共有し、②仲間意識を醸成、③問題解決できる人材育成をする。こういった活動を通して職場を活性化することを目指しています。それぞれの内容を詳しくご説明します。
問題意識の共有
一つ目の問題意識の共有とは、職場で実際に起きている問題をメンバー同士やメンバーと上司が共有することです。案外、隣で作業をしている同僚の困りごとを把握できていないケースは多くあります。
それぞれのメンバーが何に困っていて、どのようにしたいのかを知れば、職場の進むべきベクトルが合ってきます。他のメンバーの困りごとを共有し自分事にすることで、何か問題が起こってもチーム全体で取り組めるようになります。
仲間意識の醸成
二つ目は仲間意識の醸成で、まずはサークルを貴重なコミュニケーションの場と考えることが大切です。全員が同じ課題に取り組み、議論を交わしながら成功も失敗も共有すれば、自然と仲間意識が生まれやすくなります。
ひとりひとり異なる立場やキャリア、仕事内容を問わず、メンバー全員がひとつの問題に対して一丸となって取り組むことができるはずです。
問題解決人材の育成
三つ目の問題解決人材の育成は、QCサークルを通じて職場で発生した問題を適切に解決できる人材を育成する取り組みです。
トヨタのQCサークルは、「問題解決の8ステップ」に沿って進められます。問題解決の8ステップとは、段階を踏んで論理的に問題解決する手法のことをいいます。例えば、1回目はテーマの選定、2回目は現状把握、3回目は目標設定と、段階を踏んで進めていくことで、自然と問題解決のステップが身につきます。
また、トヨタのQCサークルは、QC委員会や事務局、管理職が現場のQCサークルを支え、現場の活動が組織の活性化を生み出すという概念で推進されています。金額的効果も大切ですが、目的をあくまで「職場の活性化」に割り切って取り組んでみると現場の見え方や評価の仕方も変わってくるはずです。そういった点においても人を育てる有効な手段となるでしょう。
役割と進め方
トヨタでは職層に応じて、QCサークルにおける役割が決められています。例えば、工場長がQC委員長、部長が世話人、課長が副世話人…と続き、実際の活動メンバーに至るまでそれぞれの役割があります。
職位に応じた役割につく前には研修を受け、QCサークルへの関わり方やアドバイスの仕方、運営の仕方を学びます。つまり、職場の組織がそのまま改善活動の組織として機能していることになります。
それぞれの役割につく前には研修を受け、QCサークルへの関わり方やアドバイスの仕方、運営の仕方を学びます。職位に応じた役割があることにより、それぞれのメンバーがやるべきことをスムーズに行えるのがトヨタのQCサークルの特徴です。
経営・管理層の関与の仕方
サークルには自主性が必要ですが、ただ報告会で感想を言うだけだったりまとめた資料を見たりするだけではメンバーのやらされ感は払拭できません。経営・管理層などの上層メンバーには、「自分たちのことを見てくれている」と思わせるような適切なフォローや評価が必要不可欠です。
トヨタではサークルのレベルを把握するしくみも整えられており、「職場活性化の度合い」と「サークルの能力」の2軸でレベルが視える化されています。レベルに応じて何を重点的にサポートするか、どんなアドバイスをするか、というかかわり方の指針が会社として定められているため、全員が適切な関与ができるようになっています。
こうしたことに加え、管理監督者は自分の経験や体験を踏まえてアドバイスしたり、実際に現地現物で見たうえで指導を行うことも大切です。このように、レベルに応じた適切なフォローと経営・管理層の泥臭い関わりがトヨタのQCサークルの大きな特徴です。
QCサークルを成功させるために「プロセスをほめる」
QCサークルをいきなり大きく成功させるのは現実的ではありません。そこで、今すぐにできる簡単なポイントを一つお伝えします。それは、「プロセスをほめること」です。中間地点でも報告会でも問題ないので、結果だけではなく過程をしっかり見てほめることが大切です。
また、ほめ方も大切で、「〇〇さんのここの気づきと進め方がいいね」など具体的にほめるだけでも、メンバーの意欲は大きく変わってきます。どんなに小さなことでも、よいと思ったことは素直にほめると、やらされ感の払拭につながり、サークルのレベルも上がっていくはずです。
まとめ
QCサークルを成功させるためには、目的の持たせ方と経営・管理層の関与の仕方が重要です。
メンバーのやらされ感を払拭するには、金額的効果のためだけではなく、まずは職場の活性化をゴールにすることを意識するとよいでしょう。
また、経営や管理層の関わりとして大事なことは、活動体制を整え、適切な関与を行うことです。QCサークルの進め方でお悩みの方は、まずは「プロセスをほめる」ことから始めてみてはいかがでしょうか。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタのQCサークルとは?具体的な進め方や成功のポイントを紹介
2025.02.28 -
余裕時間が「長期の価値」を生み出す!長期的に生産性を上げる方法を解説
2025.02.21 -
メンバーとの関係づくりの第一歩は「ほめる」!メンバーを育てる4つの働きかけを紹介
2025.01.10 -
リーダーから挨拶するだけで職場は変わる!メンバーから話しかけやすい環境のつくり方を紹介
2025.01.10 -
トヨタのリーダーに求められる3つの技能とは?各項目を詳しく解説
2024.12.27 -
トヨタのリーダー教育とは?リーダーに求められる資質も紹介
2024.12.27

PAGE
TOP