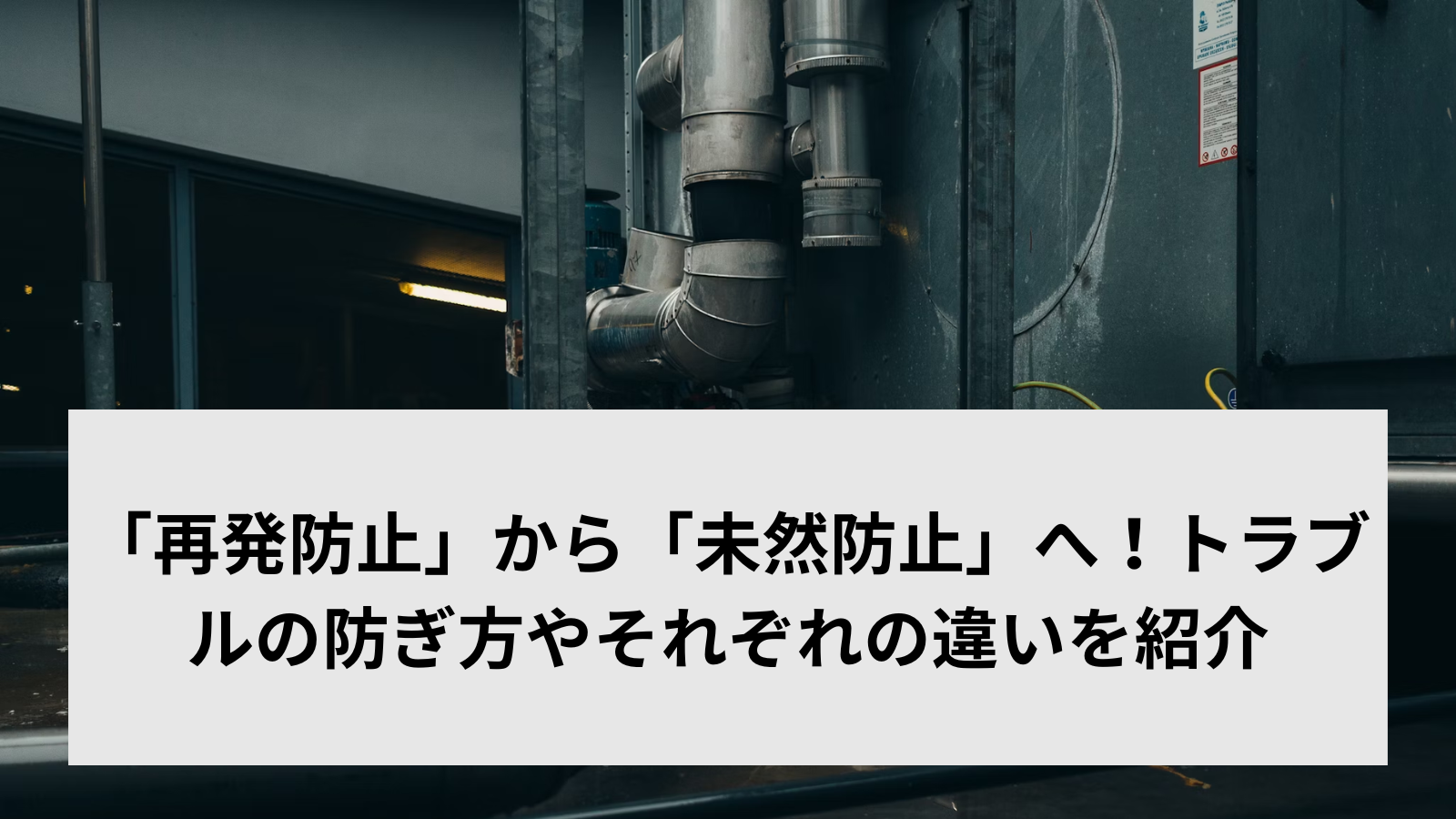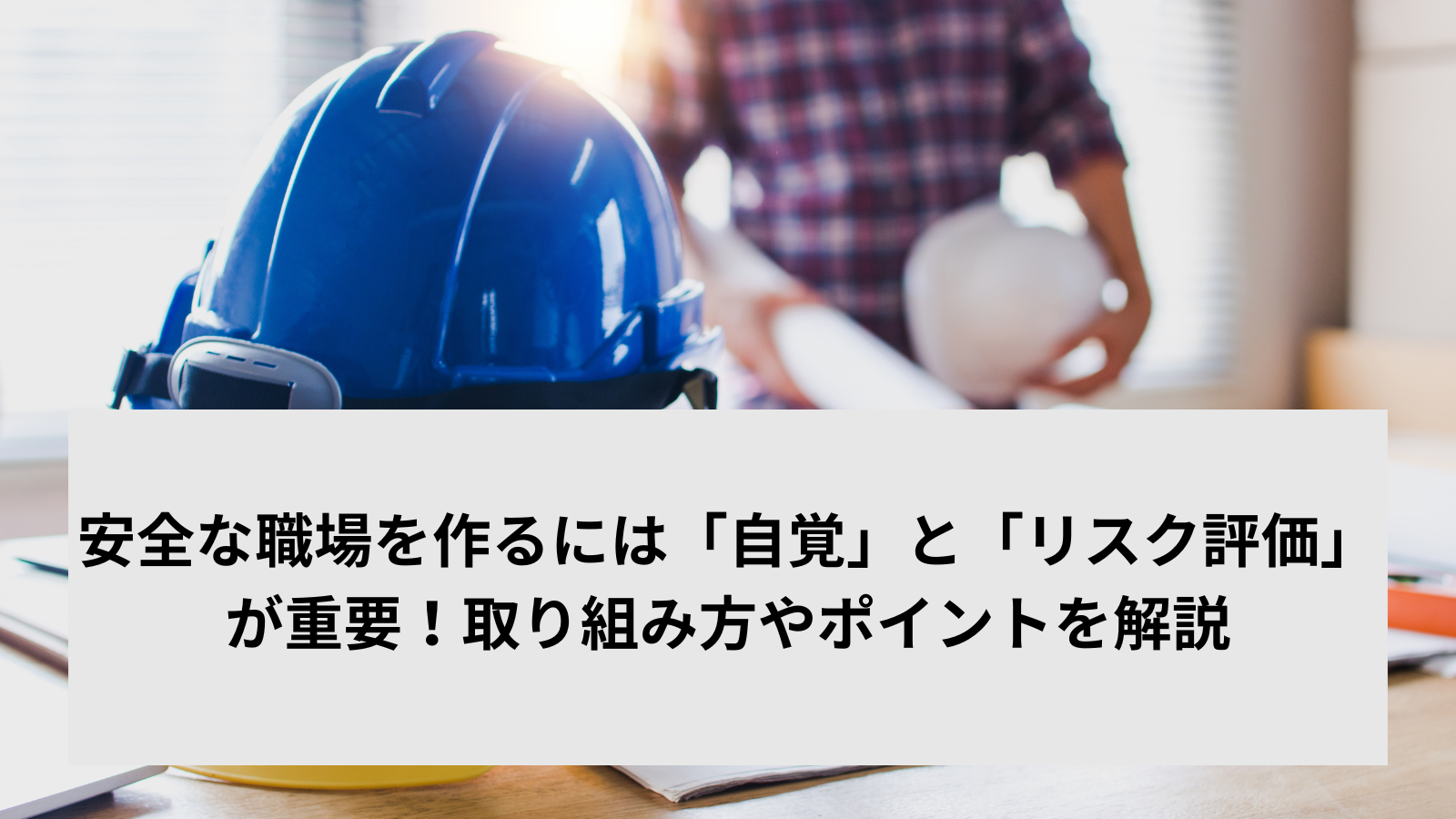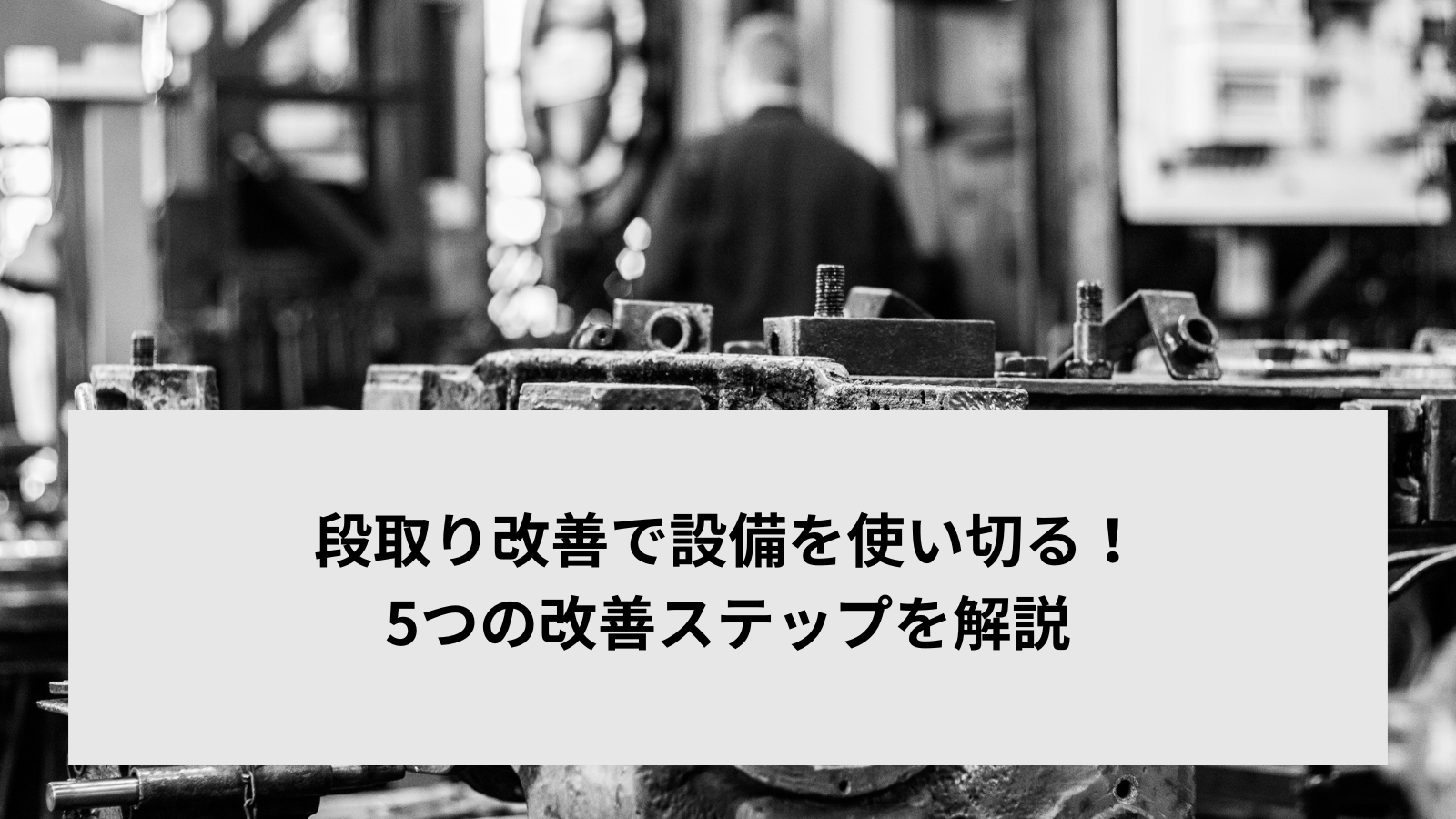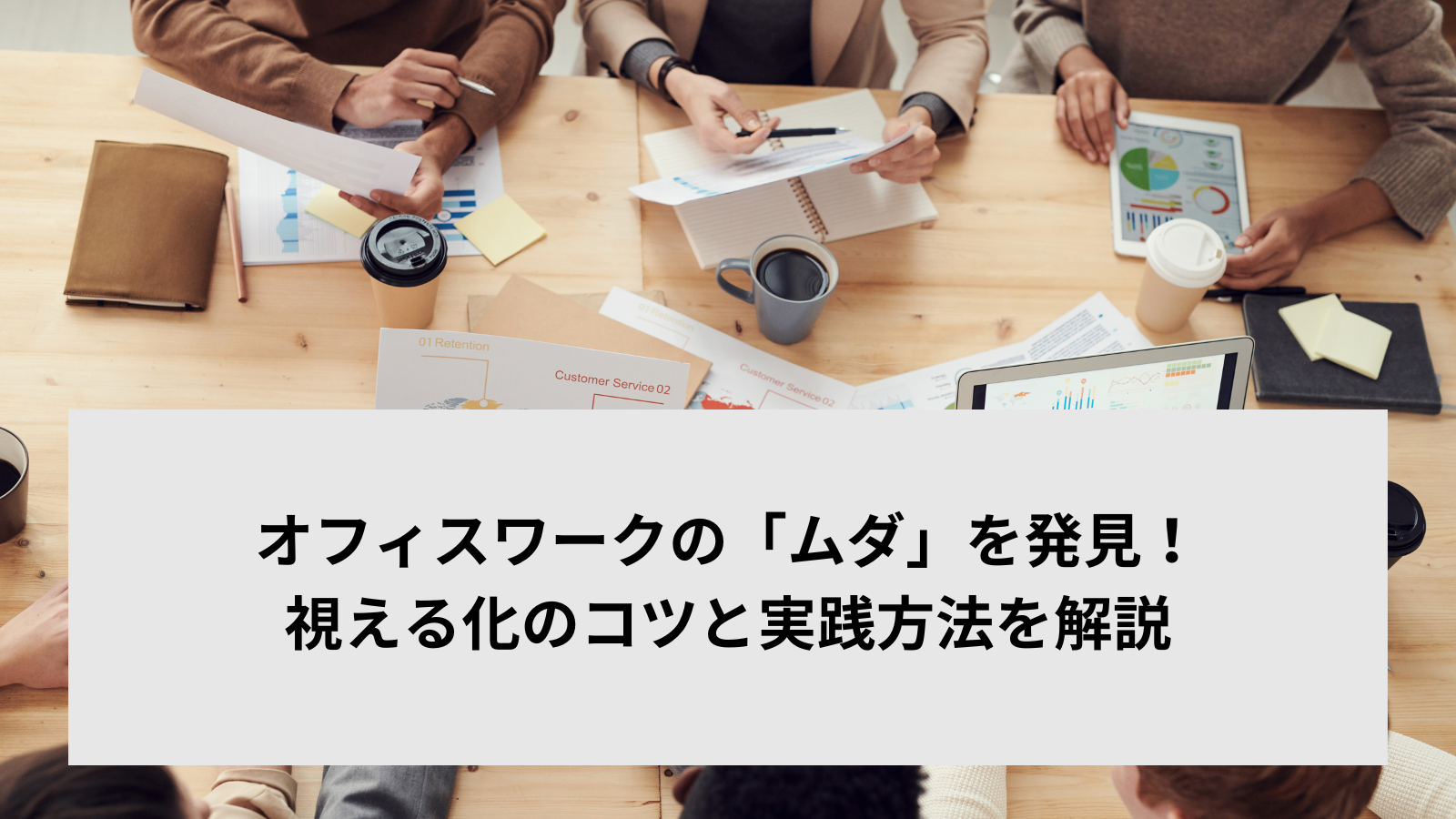現場力向上
「再発防止」から「未然防止」へ!トラブルの防ぎ方やそれぞれの違いを紹介

監修者
三尾 恭生
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて42年の現場経験、管理職の経験を経てOJTソリューションズに入社しました。座右の銘は「不易流行」。変える勇気と変えない勇気を持つことが大事だと信じ、現地現物でお客様と伴走しています。
仕事の段取りがスムーズに進むことで、期待した成果が得られます。しかし、トラブルや問題が発生すると、どれほど綿密に計画を立てていても、予定通りに進まなくなることがあります。
トヨタでは、こうしたトラブルを防ぐために、2つのレベルで対策を講じています。ひとつは、同じ問題を繰り返さないための「再発防止」、もうひとつは、類似の問題を未然に防ぐ「未然防止」です。
本記事では、製造業をはじめとする現場で頻発するトラブルへの対応策として、トヨタの現場で培われた「再発防止」と「未然防止」の考え方を紹介します。問題の根本解決や予防に取り組みたい方は、ぜひ参考にしてください。
未然防止とは?定義と再発防止・予防との違い
未然防止とは、問題が顕在化する前の段階で、リスクの兆候やシグナルを察知し、事前に対策を講じる活動です。単なる予測や勘に頼るのではなく、過去のデータや経験則、科学的な分析手法に基づいて、将来起こりうる問題を特定し、その発生を防ぐ行動を取る点が特徴です。
例として、製造現場で設備の振動や温度変化を継続的に監視し、異常の兆候を検知した時点で保全作業を行うことで、設備故障を未然に防ぐ取り組みが挙げられます。
再発防止・予防・未然防止の違い
| 項目 | 再発防止 | 予防 | 未然防止 |
| 対象 | 既に発生した問題 | 一般的なリスク | 兆候を察知した特定リスク |
| タイミング | 問題発生後 | 問題発生前(一般的対策) | 問題発生前(兆候ベース) |
| 手法 | 原因分析・対策実施 | 標準的な安全対策 | 予兆データの分析・監視 |
| アプローチ | 後追い・受動的 | 予防的・一般的 | 先回り・能動的 |
この違いを理解することで、品質管理や安全管理の取り組みをより戦略的かつ効果的に進めることができます。
未然防止の導入メリット
重大事故・品質問題の回避による信頼性向上
未然防止の最大の利点は、企業の存続に関わる重大事故や品質問題を事前に回避できる点です。大規模なリコールや事故による損失は、製品回収費用にとどまらず、賠償金、株価下落、ブランド毀損など、企業価値に深刻な影響を与えます。
自動車業界では、一件の品質問題が数百億円規模の損失につながることもあります。未然防止への投資は、こうしたリスクを回避する「保険」としての役割も果たします。
後追い対応の削減による生産性向上
問題発生後の対応に追われる「もぐら叩き」状態から脱却することで、現場の生産性は向上します。再発防止に時間を取られる現場では、本来の業務に集中できず、残業やストレスの増加につながります。
未然防止のしくみが整えば、緊急対応が減り、計画的な業務運営が可能になります。結果として、従業員満足度の向上や離職率の低下、付加価値創造への集中が実現します。
DX時代の「予兆検知×自動化」による競争優位
デジタル技術の進歩により、oTセンサーやAI予測モデルを活用することで微細な変化や複雑なパターンを検知し、自動的にアラートを発信・対策を実行することが可能になっています。
こうした先進的な未然防止システムを構築できる企業は、品質・効率の両面で競合他社に対して優位性を確立できます。
未然防止の導入ステップ
管理監督者が主導して未然防止の取り組みを進めることで、職場全体の安全性と品質が向上します。以下に、導入の5つのステップを具体的に解説します。
ステップ1:リスクの洗い出し
まずは、過去に起きた不具合やヒヤリハット事例を整理し、どのような場面で問題が発生しやすいかを把握します。作業者の経験や感覚も貴重な情報源です。「あの時ちょっと危なかった」「いつも気になる作業がある」といった声を集めることで、潜在的なリスクを見える化できます。ここでは、「問題が起きていないから安心」ではなく、「起きそうな兆しがあるか」を探る姿勢が重要です。
ステップ2:兆候の特定
次に、リスクが現れる前の兆候を特定します。例えば、設備の振動や温度の異常、作業記録のばらつきなどが予兆となることがあります。センサーやデータ分析を活用するだけでなく、現場の「いつもと違う」という感覚も大切です。兆候は小さな違和感として現れることが多いため、現場の目とデータの両方で捉えることが効果的です。
ステップ3:予兆の監視体制の構築
兆候を継続的に監視する体制を整えることで、問題の芽を早期に発見できます。IoTセンサーによるリアルタイム監視や異常検知のしくみを導入することで、予兆を自動的に捉えることが可能になります。また、作業者が日々確認するチェックリストに予兆項目を加えることで、現場の「予兆を見る習慣」を根付かせることができます。
ステップ4:対策のしくみ化
予兆が見つかった際に、確実に対応できるしくみを作ることが重要です。ポカヨケ(ミスを防ぐ仕掛け)を工程に組み込んだり、作業手順を見直してリスクの高い工程を分離・簡素化したりすることで、問題の発生を防げます。また、教育や訓練を通じて「予兆の見方」や「対応方法」を標準化することで、誰が対応しても同じレベルで未然防止ができる体制を築けます。
ステップ5:効果検証と横展開
最後に、導入した対策の効果を検証し、他の工程や拠点にも展開します。トラブル件数や品質データの変化を比較することで、対策の有効性を確認できます。さらに、現場の声を集めて「やりやすくなった」「安心感がある」といった実感を共有することで、改善の成果を組織全体に広げることができます。成功事例は社内報や改善事例集で共有し、横展開を促進しましょう。
再発防止から未然防止に発展した事例
ある工場では、組立工程においてボルトの締め忘れが繰り返し発生していました。締め忘れが見つかるたびに工程を止めて手直しを行う必要があり、納期遅れや品質への不安を招いていました。現場では口頭での注意喚起や作業者への指導を行っていましたが、ヒューマンエラーは完全には防げず、根本的な改善には至りませんでした。
そこで、再発防止策として「ボルトが正しく締められていないと次工程に進めない」しくみを導入しました。具体的には、トルクレンチに異常検知機能を搭載し、設定トルクに達していない場合は作業完了と認識されないようにしました。また、作業完了信号が出ない限り、次の工程に部品が送られないしくみを工程設計に組み込みました。
このしくみは、作業者の注意力に依存せず、工程そのものがミスを検知・防止する構造になっているため、締め忘れの再発を大幅に減少させることができました。さらに、この成功事例を他の類似工程にも横展開したことで、工場全体のボルト締めに関するトラブル件数が減少し、品質と納期の安定につながりました。
このように、再発防止のしくみを単なる「その場限りの対策」にとどめず、標準化・横展開することで、未然防止につながる好循環が生まれます。現場の課題をしくみで解決し、それを広げていくことで、組織全体のリスク感度と対応力が高まっていきます。
再発防止の問題解決方法については下記記事も参考にしてみてください。
ポカヨケとは何か?誰がやっても失敗しない「しくみ」を作る大切さ
トヨタのQCサークルとは?具体的な進め方や成功のポイントを紹介
問題解決の8ステップとは?トヨタの問題解決プロセスを解説
よくある質問(FAQ)
Q1. 未然防止とは具体的にどのような意味ですか?
A1. 未然防止とは、問題や事故が発生する前にリスクを予測し、あらかじめ対策を講じることを指します。「起きてから対応する」のではなく、「起こさないためのしくみづくり」が重要な考え方です。
Q2. 未然防止と再発防止の違いは何ですか?
A2. 未然防止は「起こる前に防ぐ」こと、再発防止は「一度起きた問題を繰り返さないようにする」ことです。両者を組み合わせることで、より強固な安全対策や品質管理が可能になります。
Q3. 製造現場での未然防止の事例を教えてください。
A3. 代表的な例として「ポカヨケ」があります。例えば、ボルトを締め忘れると次の工程に進めないしくみを作ることで、ヒューマンエラーを事前に防ぐことができます。
Q4. 未然防止を進める上で重要なポイントは何ですか?
A4. 個人の注意や努力に頼るのではなく、しくみやルールとして定着させることが重要です。また、リスクの洗い出しと優先順位付け、現場での実行性を考慮することも欠かせません。
Q5. 未然防止はどの分野でも活用できますか?
A5. 製造業や品質管理だけでなく、安全衛生、情報セキュリティ、医療、交通など、さまざまな分野で活用可能です。共通するのは「リスクを先読みして、問題を起こさない」姿勢です。
まとめ
トラブルを防ぐには、「再発防止」と「未然防止」の両方が重要です。再発防止は過去の問題から学び、未然防止は兆候を捉えて事前に対策を講じるしくみです。
特に、「再発防止」と横展開による「未然防止」を習慣的に続けていくことで、組織力の向上にもつながります。現場のトラブルや問題にお悩みの方は、ぜひこの考え方をしくみとして定着させることを検討してみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
TPM活動とは?8本柱・16大ロス・自主保全7ステップまで徹底解説
2026.01.29 -
QCDSとは? 優先順位、QCDとの違い、Sの意味(Safety/Service)を解説
2025.12.22 -
改善が進む職場を作る!現場リーダーが実践すべき3つのポイントとは?
2025.09.19 -
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説
2025.04.11 -
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
2025.04.04 -
オフィスワークの「ムダ」を発見!視える化のコツと実践方法を解説
2025.03.28

PAGE
TOP