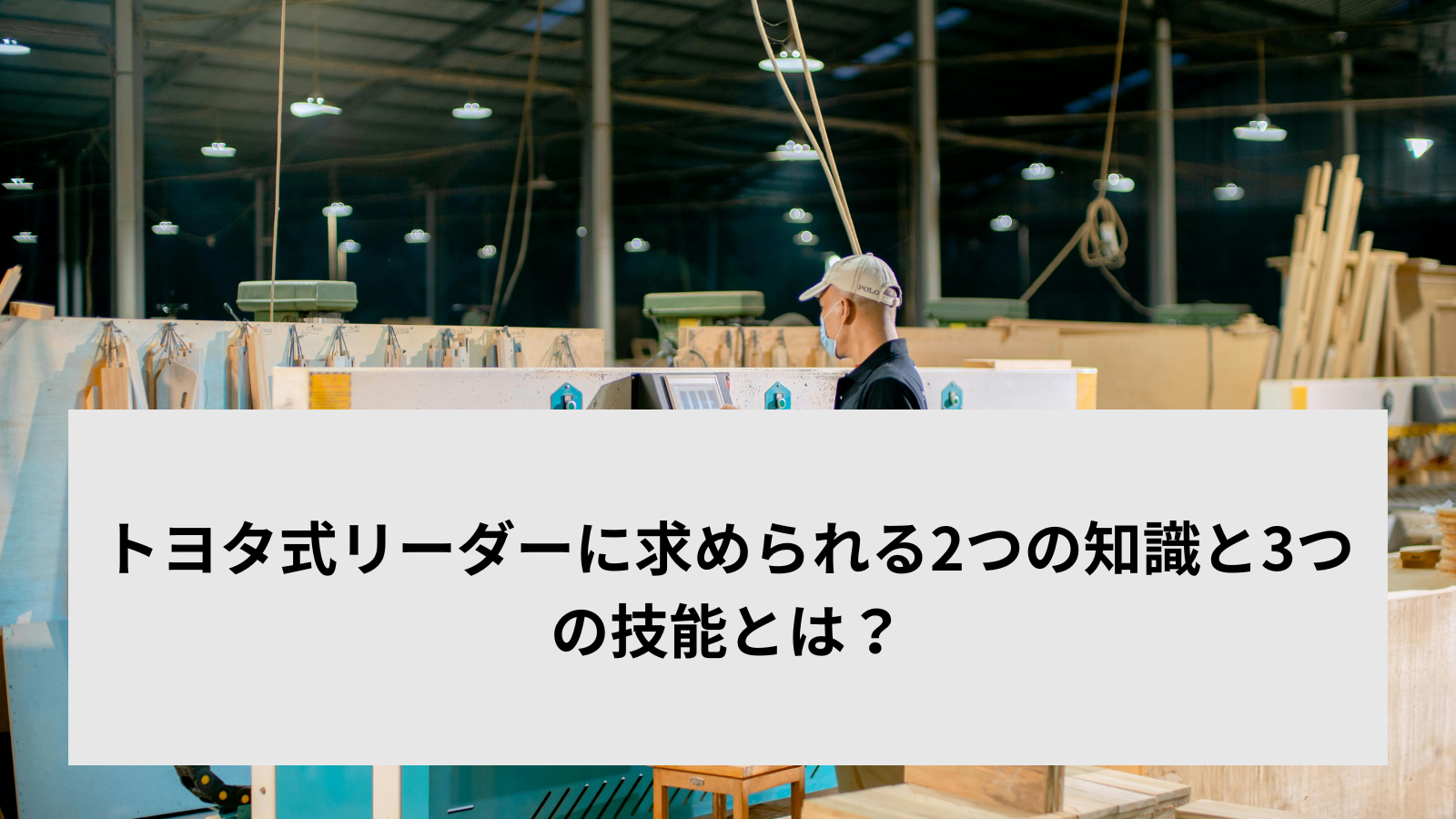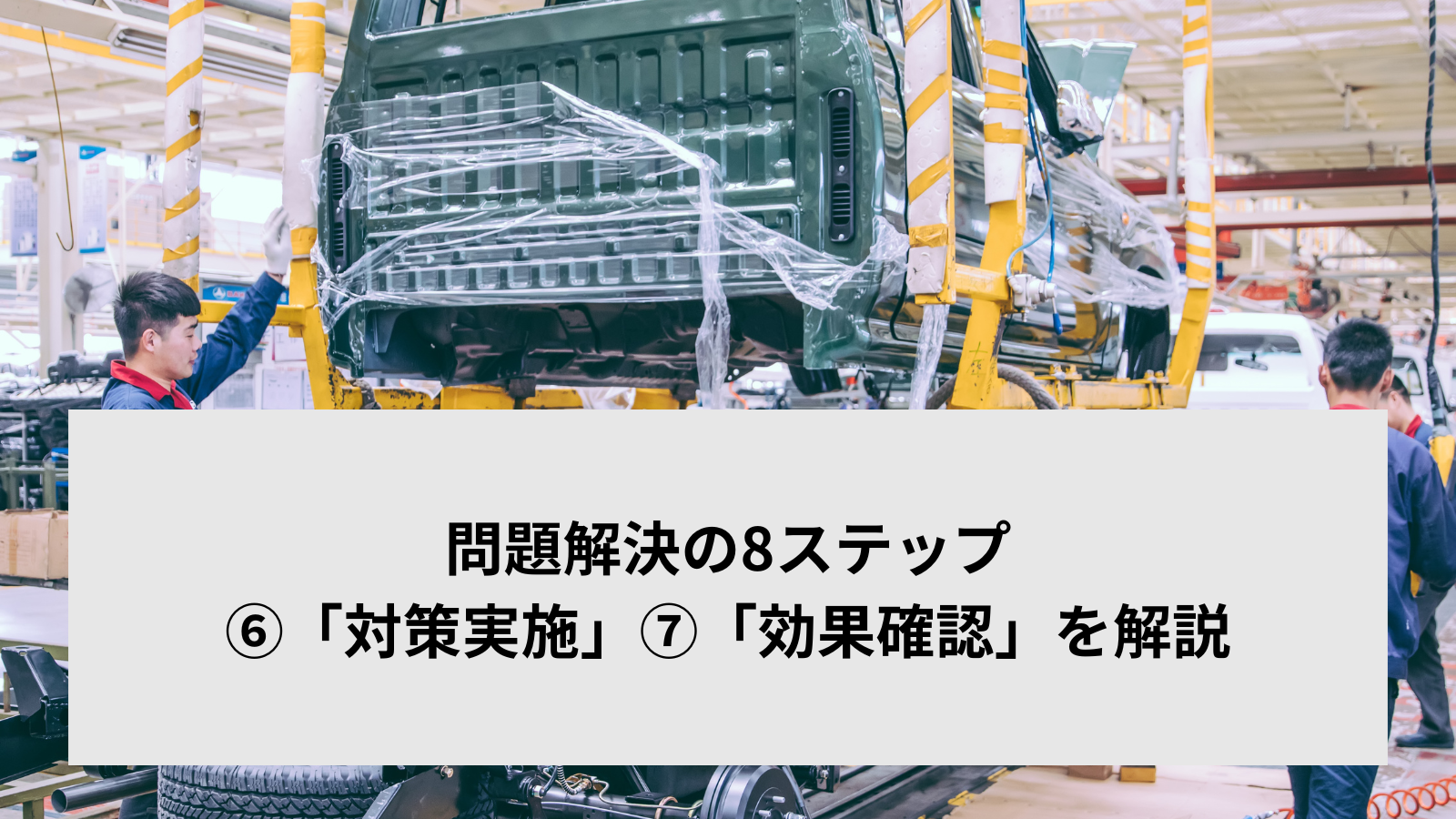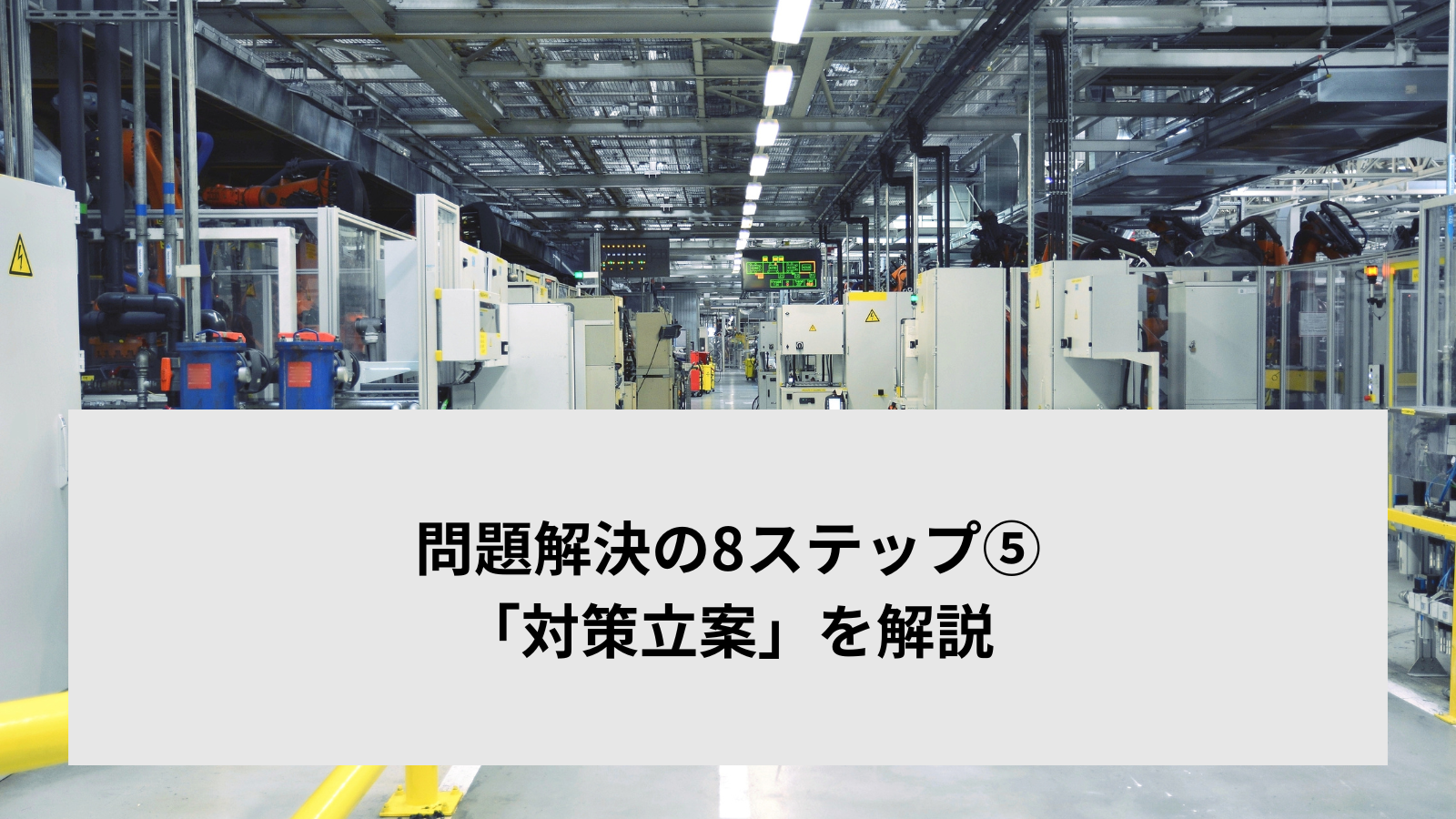OJT
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介

監修者
三尾 恭生
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて42年の現場経験、管理職の経験を経てOJTソリューションズに入社しました。座右の銘は「不易流行」。変える勇気と変えない勇気を持つことが大事だと信じ、現地現物でお客様と伴走しています。
トヨタの現場で根付く「問題解決」は、単なるトラブル対応にとどまりません。発生型・設定型・ビジョン指向型という3つの種類を用いて、現場の改善から中長期のイノベーション創出までを実現しています。
本記事では特に、未来を描く「ビジョン指向型」の考え方と実践法について、わかりやすく解説します。
問題解決の3つの種類
トヨタの問題解決には大きく分けて次の3つの種類があります。
①発生型問題解決
②設定型問題解決
③ビジョン指向型問題解決
発生型問題解決は、昨日今日に発生した問題や、慢性化して日々困っている問題を解決することをいいます。すでに存在する「あるべき姿」(目標や基準、標準)に達していない問題に対して問題解決をします。
また設定型問題解決は、これから半年〜3年後の期間で見たときに必要となる問題を解決することをいいます。現状では「あるべき姿」の基準を満たしていたとすると、より高い次元の「あるべき姿」を新たに設定し、意図的に問題をつくり出します。
ビジョン指向型問題解決とは
最後のビジョン指向型問題解決は、中長期的視野をもって世界情勢など大きな視点から「あるべき姿」を設定し、「現状」とのギャップを埋めていきます。自分で「あるべき姿」を設定する点では、設定型問題解決の発展型といえますが、大きな視点から「背景」までとらえる点が設定型との大きな違いです。
ここでいう「背景」とは、トヨタの場合では次のようなものがあります。
・世界の経済情勢はどうか、これからどのような動きを見せるか。
・世界の自動車産業はどのような状況か。今後どうなるか。
・日本の経済や自動車産業は、これからどのような状況になりそうか。
このような世界情勢から分析をスタートさせて、
・トヨタ自動車はどうあるべきか。
・自分の部署・職場は、どうあるべきか。
・自分がすべきことは何か。
と、身近なところまで問題を下ろして、ビジョン指向型問題解決のテーマを見つけていくのです。
ビジョン指向型が生むイノベーション
ビジョン指向型問題解決は、スケールが大きく視野が広いため、イノベーションにつながる可能性があります。トヨタのハイブリッド車「プリウス」は、ビジョン型の問題解決から生まれたイノベーションです。
プリウスが開発された当時、石油が枯渇し高騰したり、環境問題が深刻化したりすることが予測され、将来自動車のあり方が問われるのではないかと考えました。そうした背景をふまえて、「人と地球にとって快適であること」というコンセプトのもと、プリウスの開発が進みました。
効率化やムダの低減など生産性を高めることや目先の利益を確保することばかりに焦点を合わせていたら、決して生まれなかった発想でした。未来の「あるべき姿」に目を向けることにより、はじめてイノベーションは実現できます。
現場から始めるビジョン指向型思考
ビジョン指向型の問題解決は、実際には経営者やリーダーの仕事であることが多いです。しかし、管理監督者や一般社員にも関係ない話ではありません。
トヨタの現場では、発生型・設定型・ビジョン指向型を明確に区別するというよりも、状況に応じて柔軟に使い分けています。特に発生型から設定型への移行は、改善活動の成熟度を測る一つの指標になります。例えば、発生型が主体のQCサークル(小集団活動)においても経験値の高いメンバーで構成された場合やレベルが上がってくると設定型で取り組むサークルも近年では見受けられます。
ビジョン指向型問題解決においても、問題のテーマが大きくなるだけで基本的には発生型問題解決や設定型問題解決と踏むべきステップは一緒です。従って、日々の業務改善の中で問題解決を繰り返していくことによって、ビジョン指向型の素地が育ちます。「日々の問題解決が、将来のイノベーションにつながる」といっても過言ではないのです。
まとめ:未来を描く力が現場を変える
ビジョン指向型の問題解決は、指示されたことをやることからは生まれてきません。ビジョン指向型の問題解決をする際には、「何をしたいか」という意思が必要不可欠です。「こうしたい」という意思が込められることで、はじめてテーマに息が吹き込まれ、自発的に動くことができます。そのため、ビジョン指向型問題解決では「自分は(相手は)何をしたいか」という問いかけが重要です。
会社で示すビジョンも同様に、意思をこめて「こうなりたい」という姿を社員に具体的に示すことが重要です。ビジョンが単なるスローガンになっていないか、注意してみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタ式リーダーに求められる2つの知識と3つの技能とは?
2025.09.26 -
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介
2025.09.05 -
問題解決の8ステップ⑧「標準化・再発防止」を解説
2025.08.22 -
問題解決の8ステップ⑥「対策実施」⑦「効果確認」を解説
2025.08.15 -
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
2025.08.08 -
問題解決の8ステップ④「要因解析」を解説
2025.08.01

PAGE
TOP