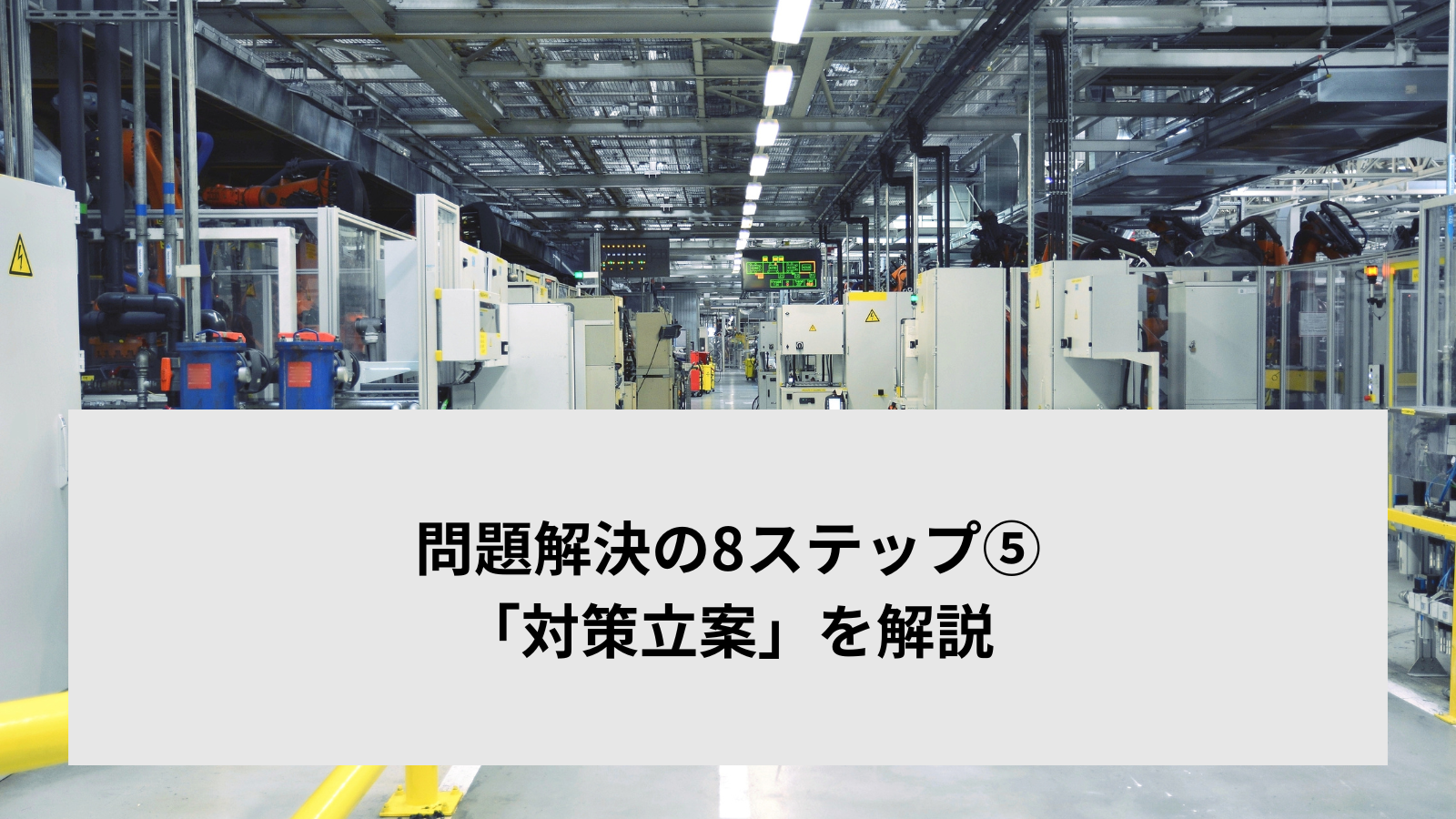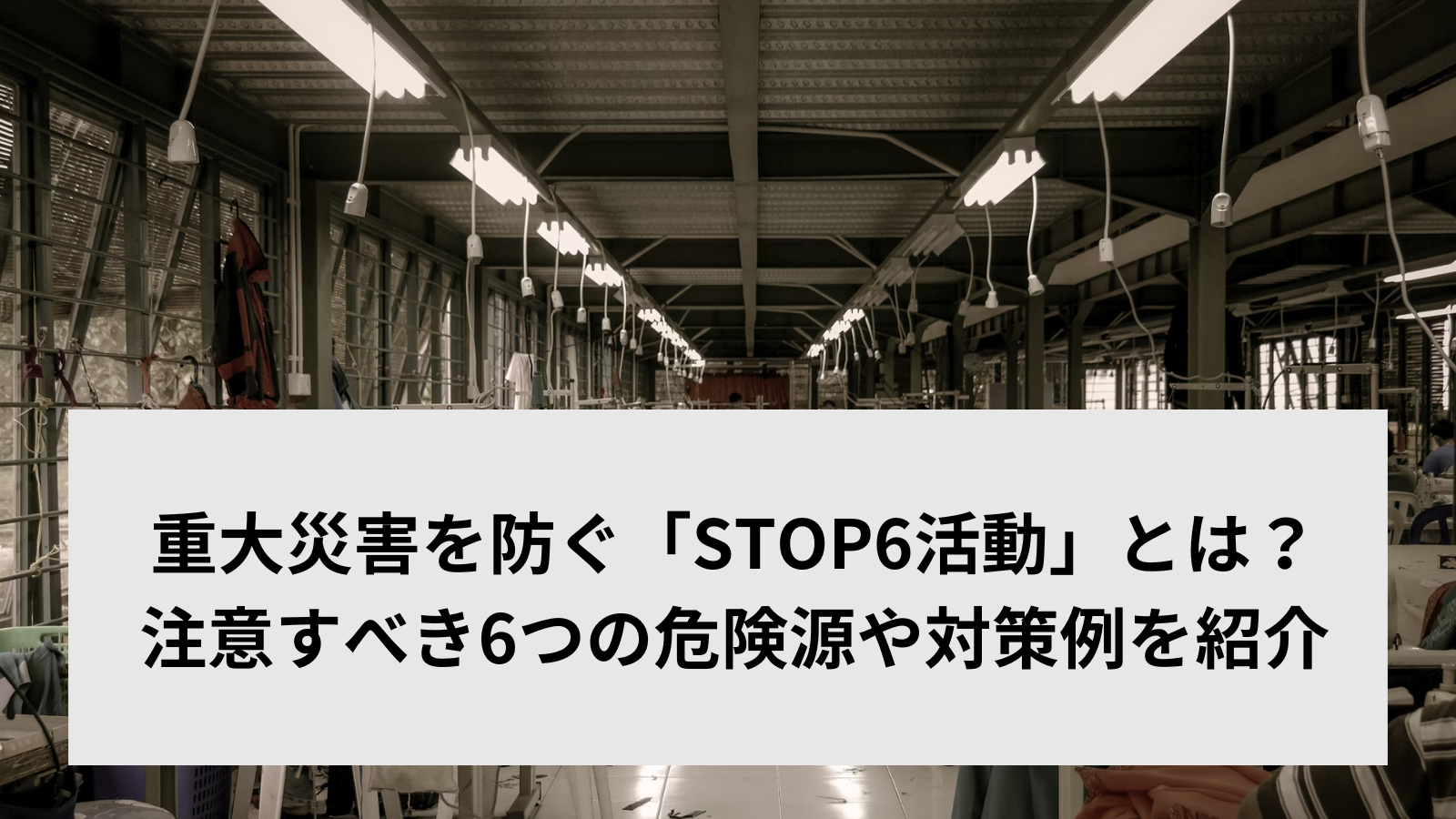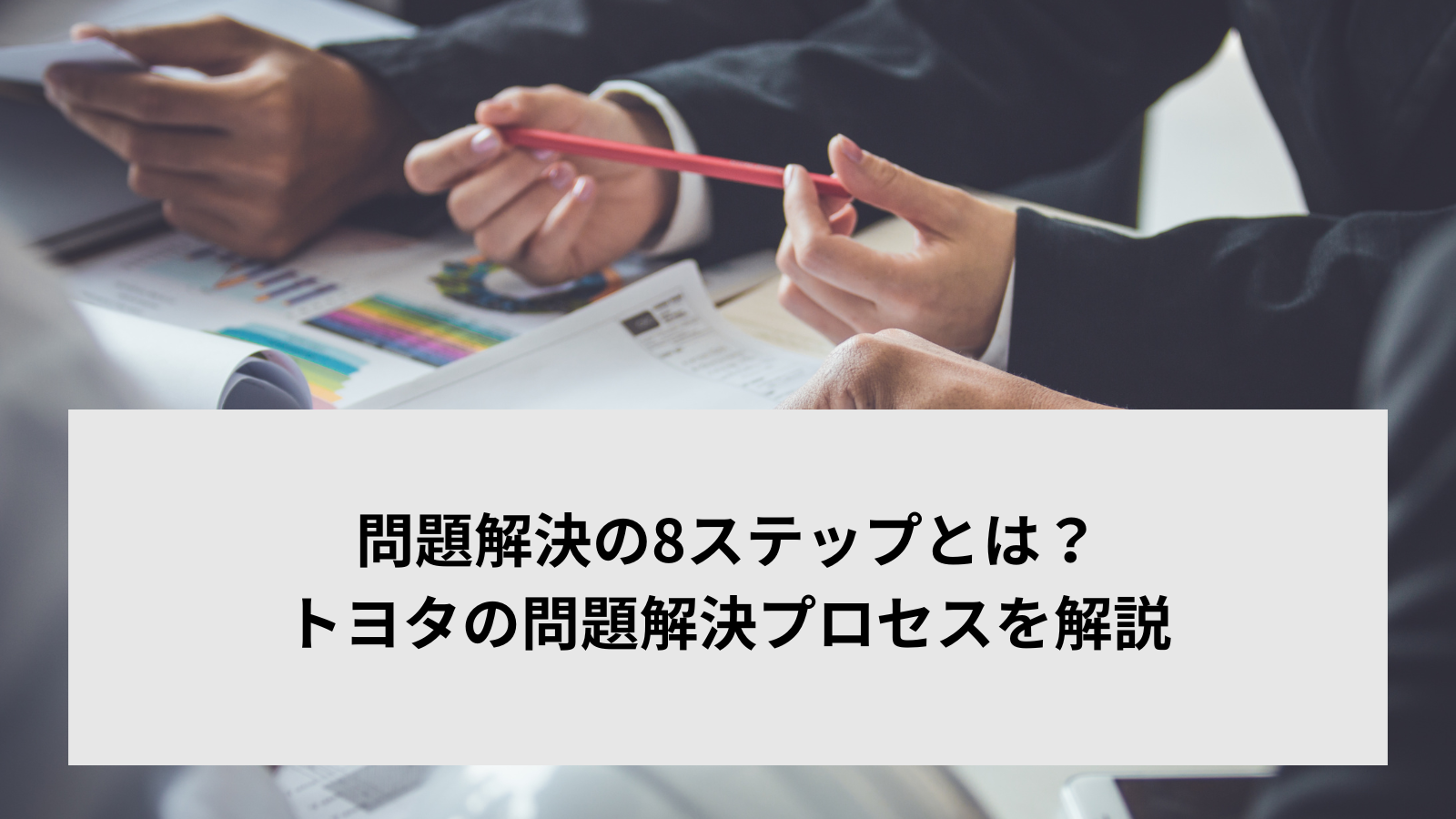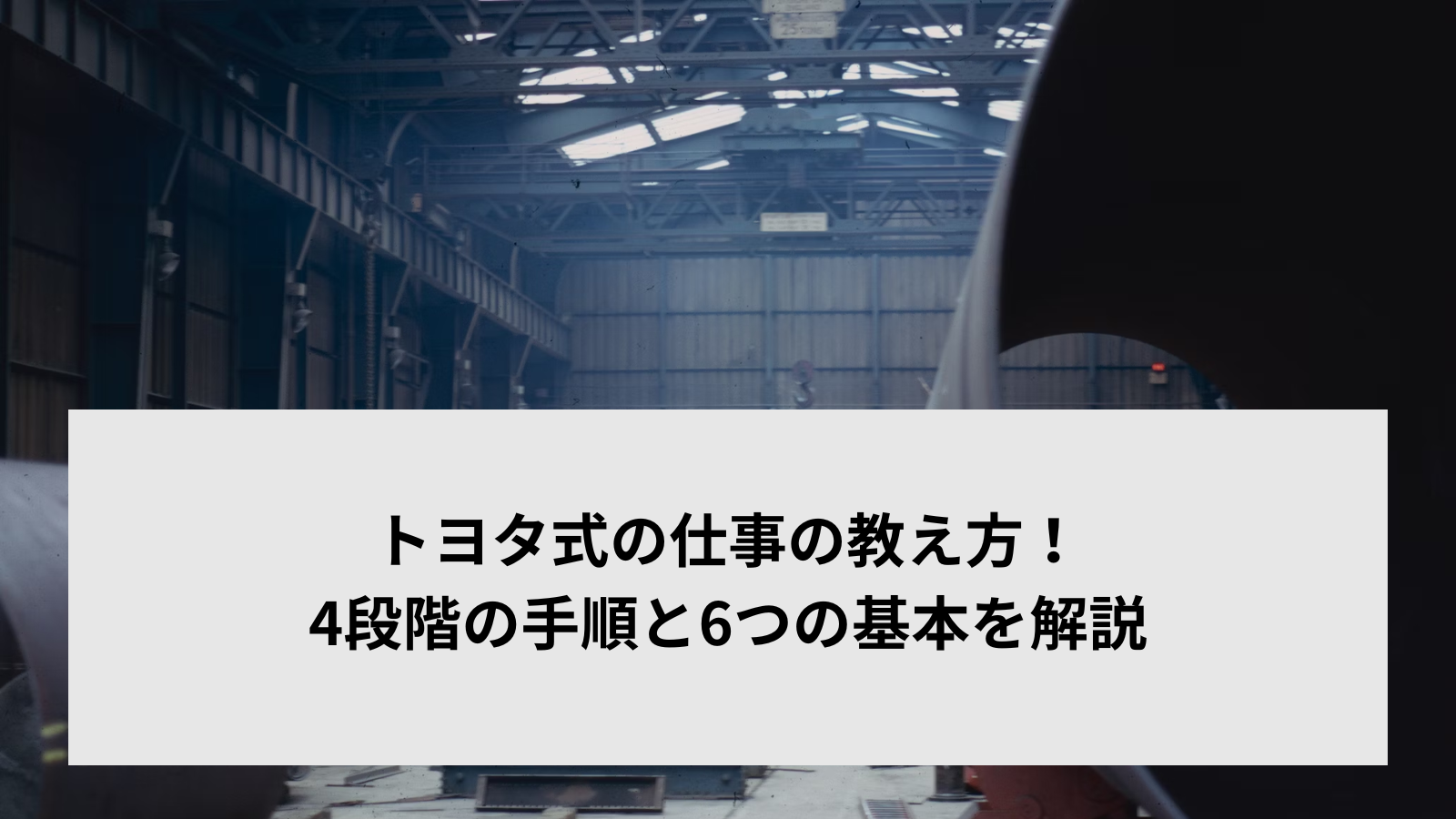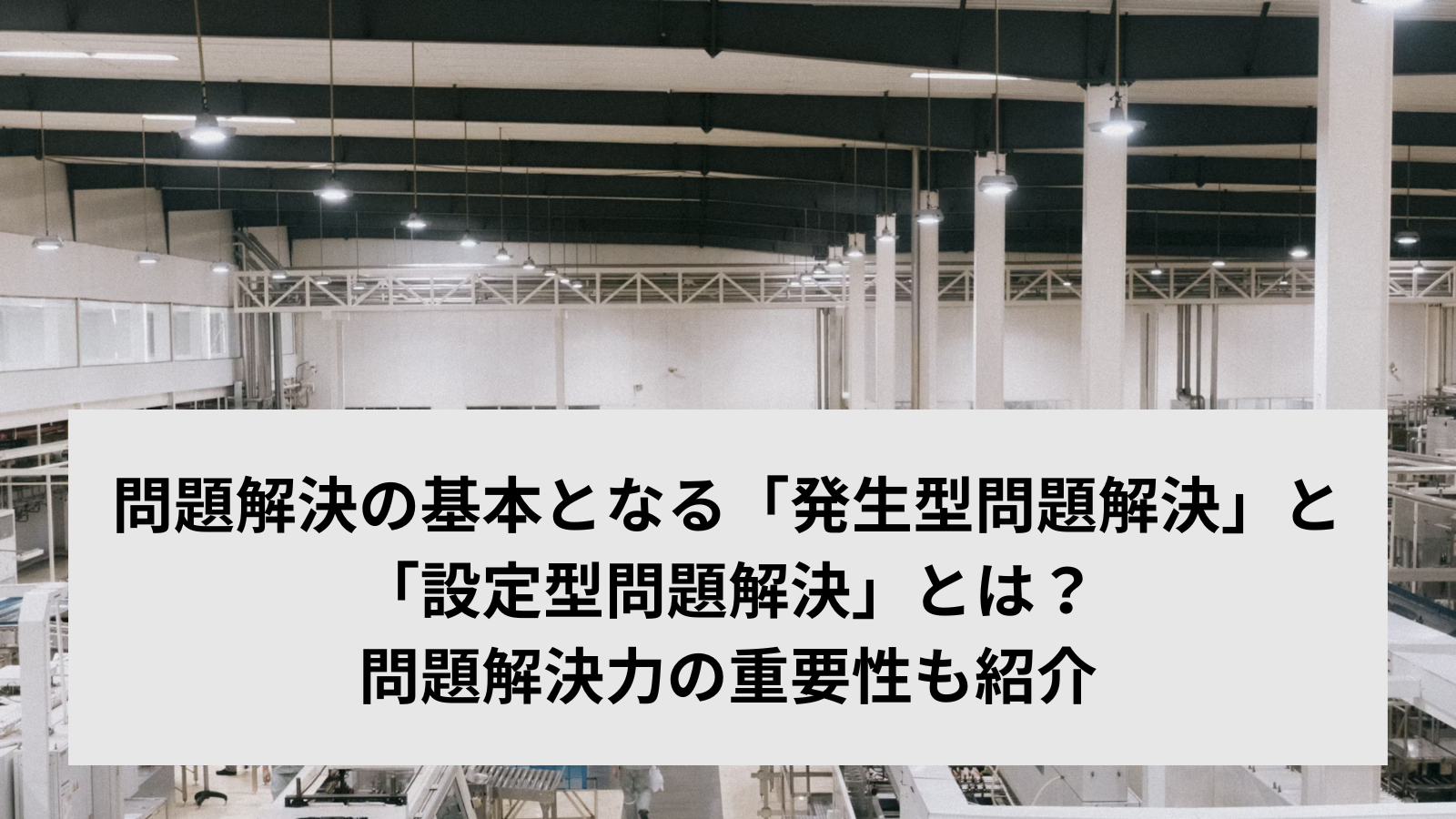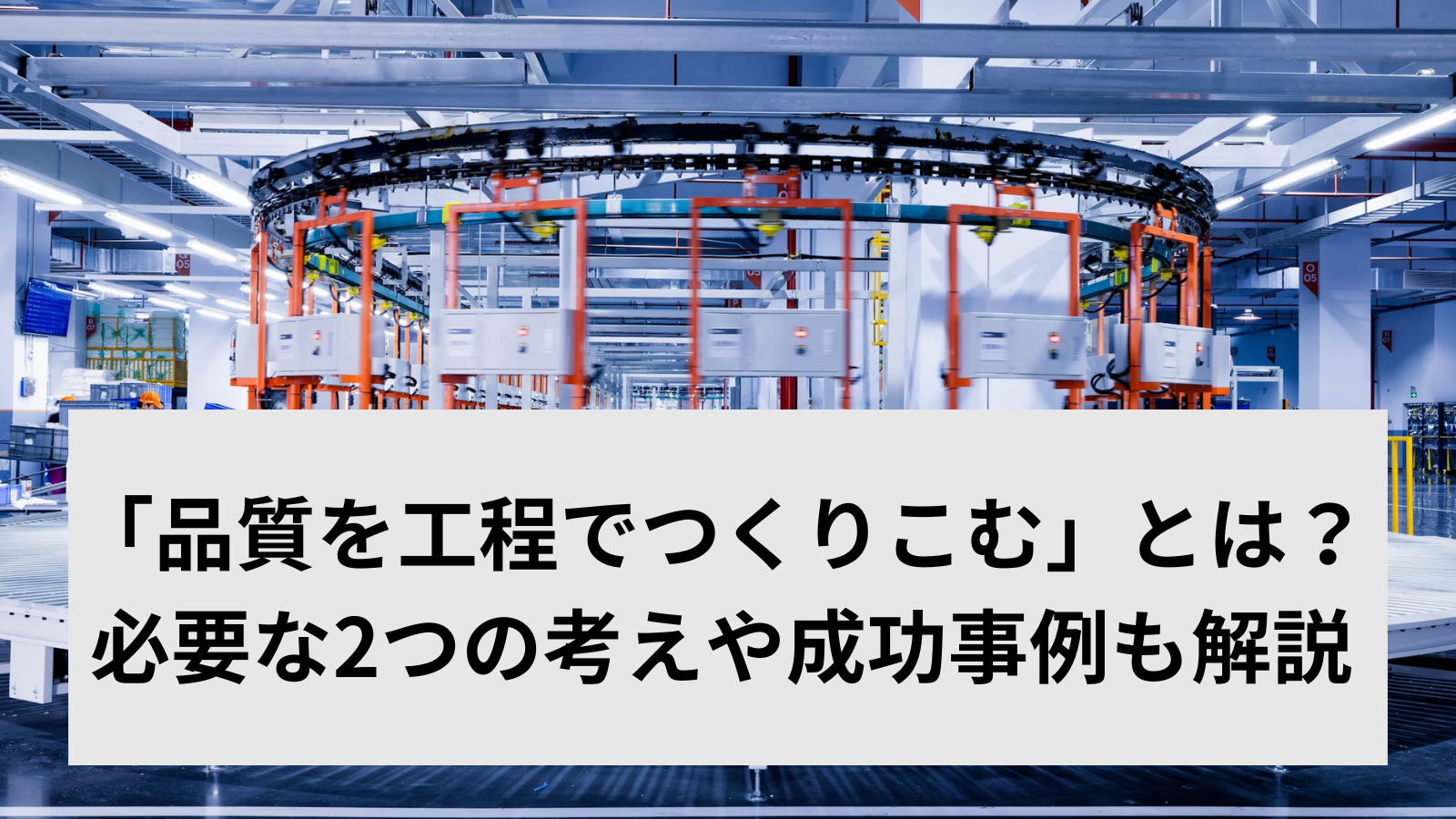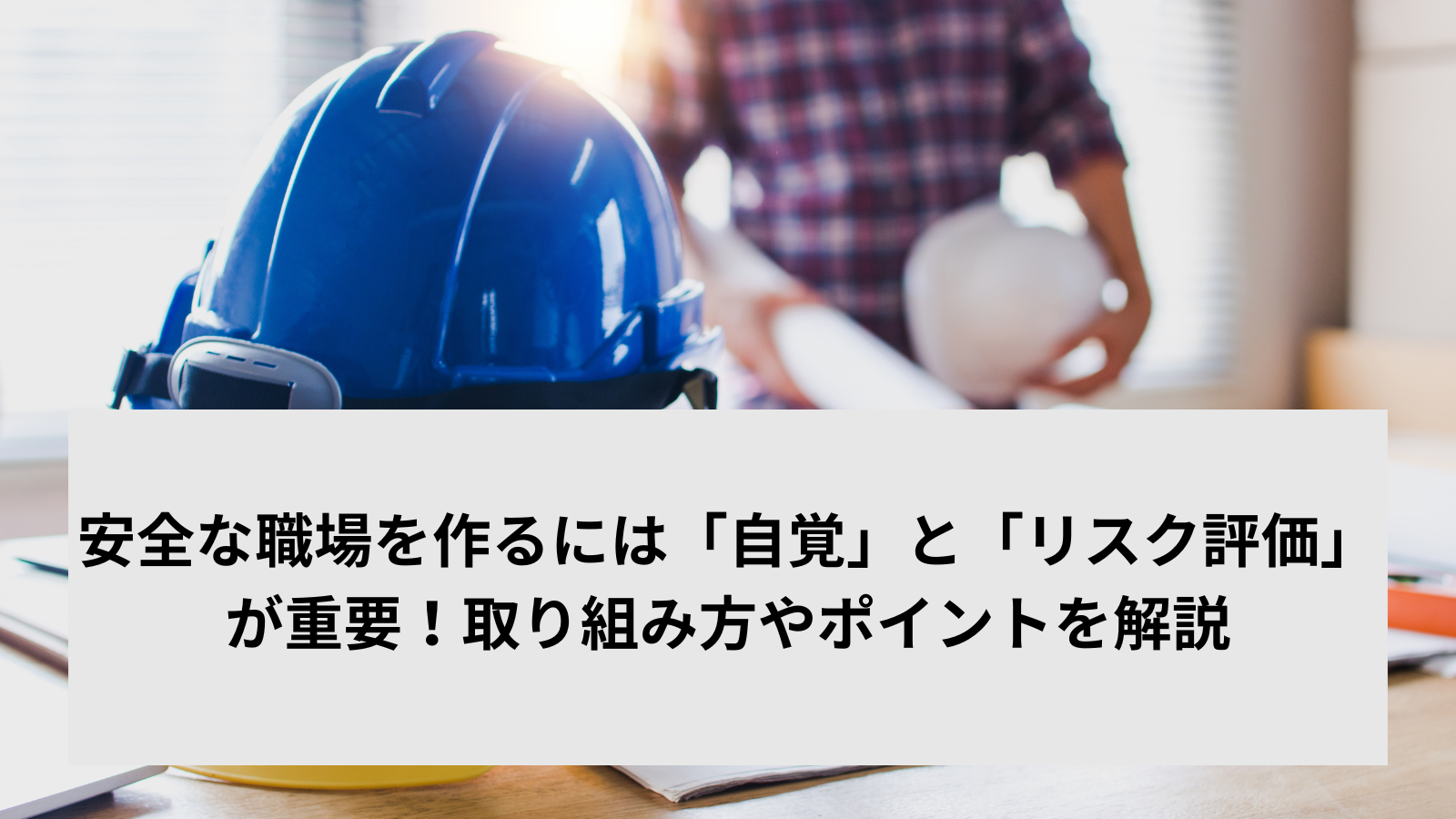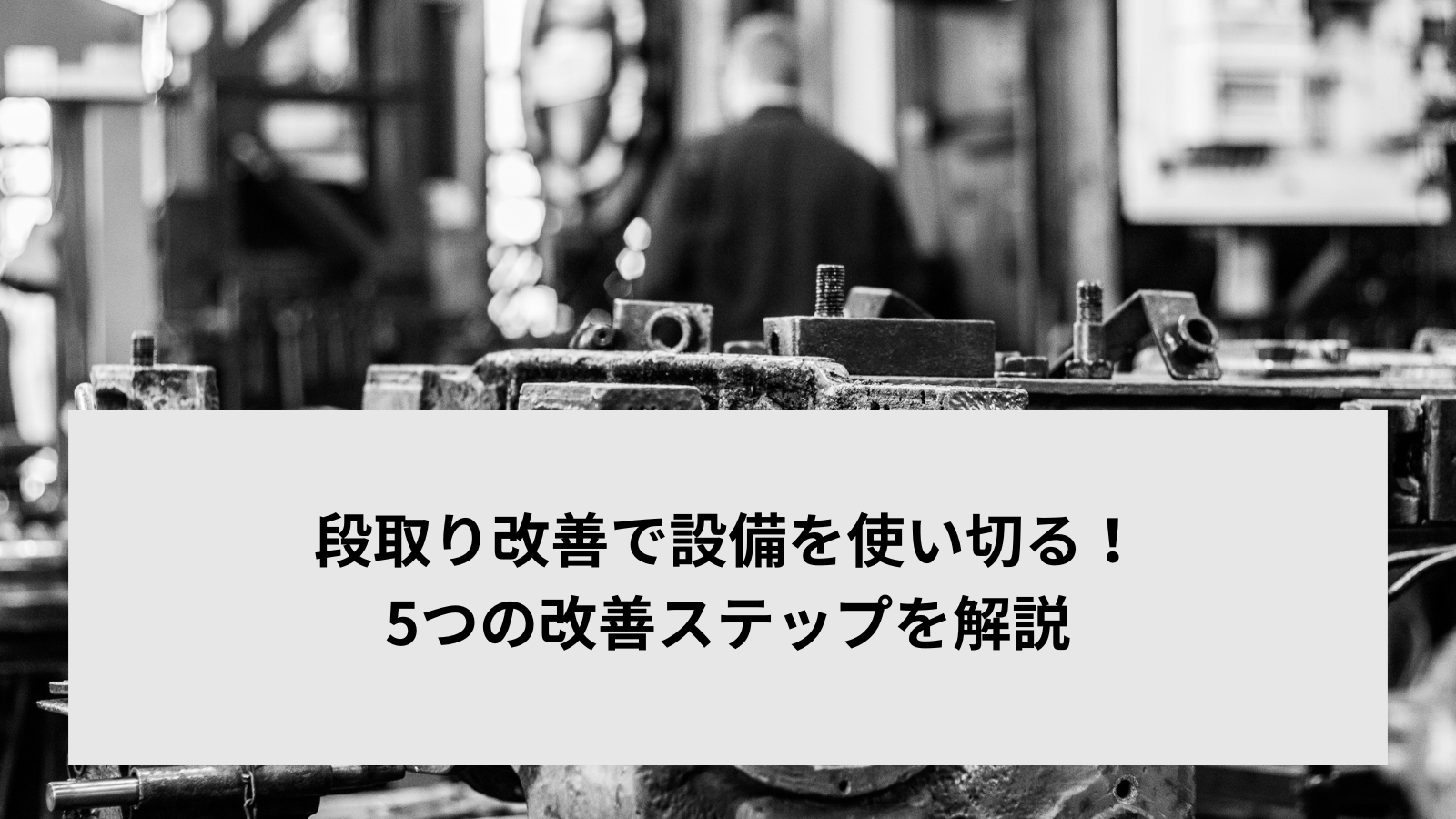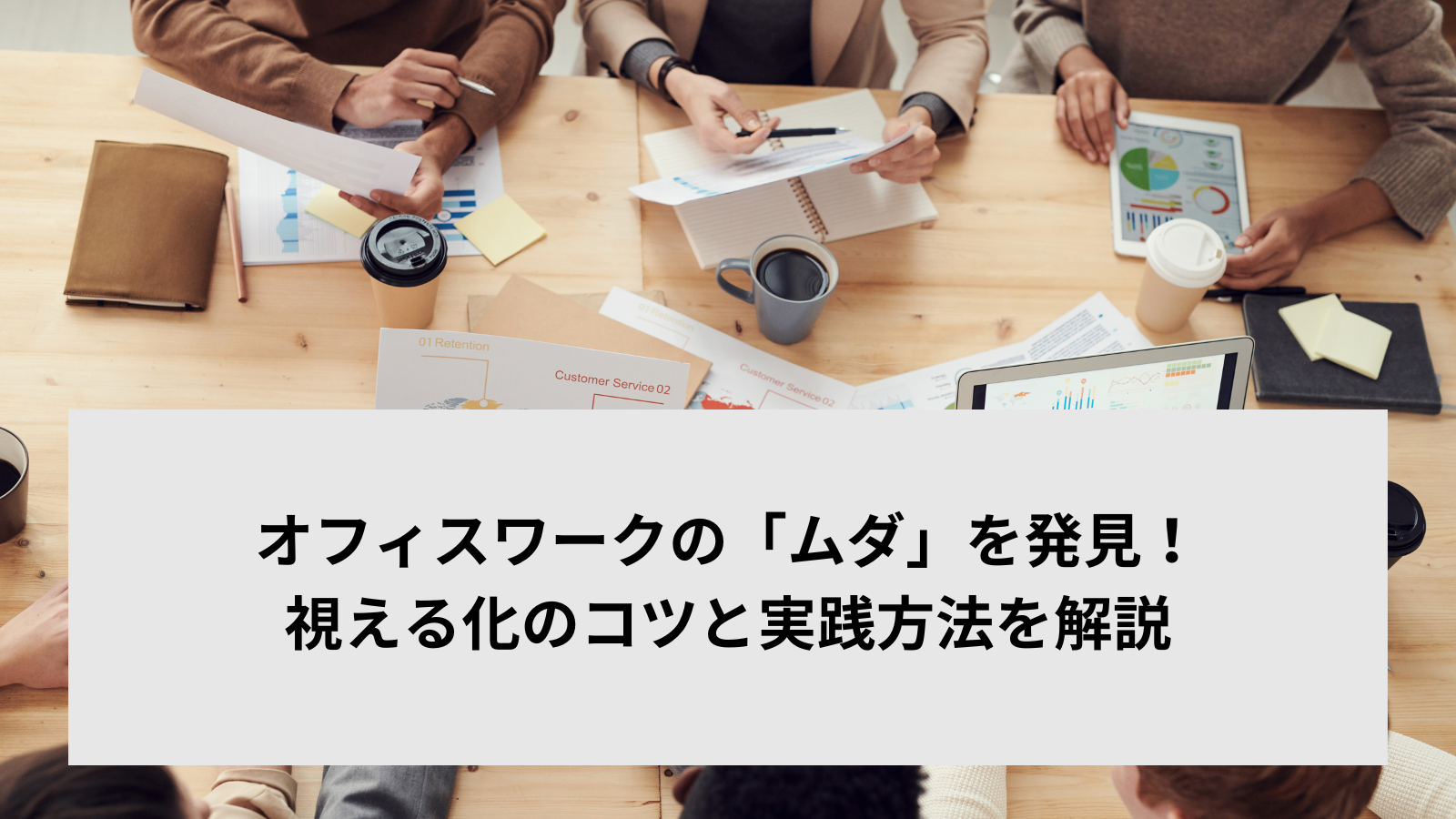OJT
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
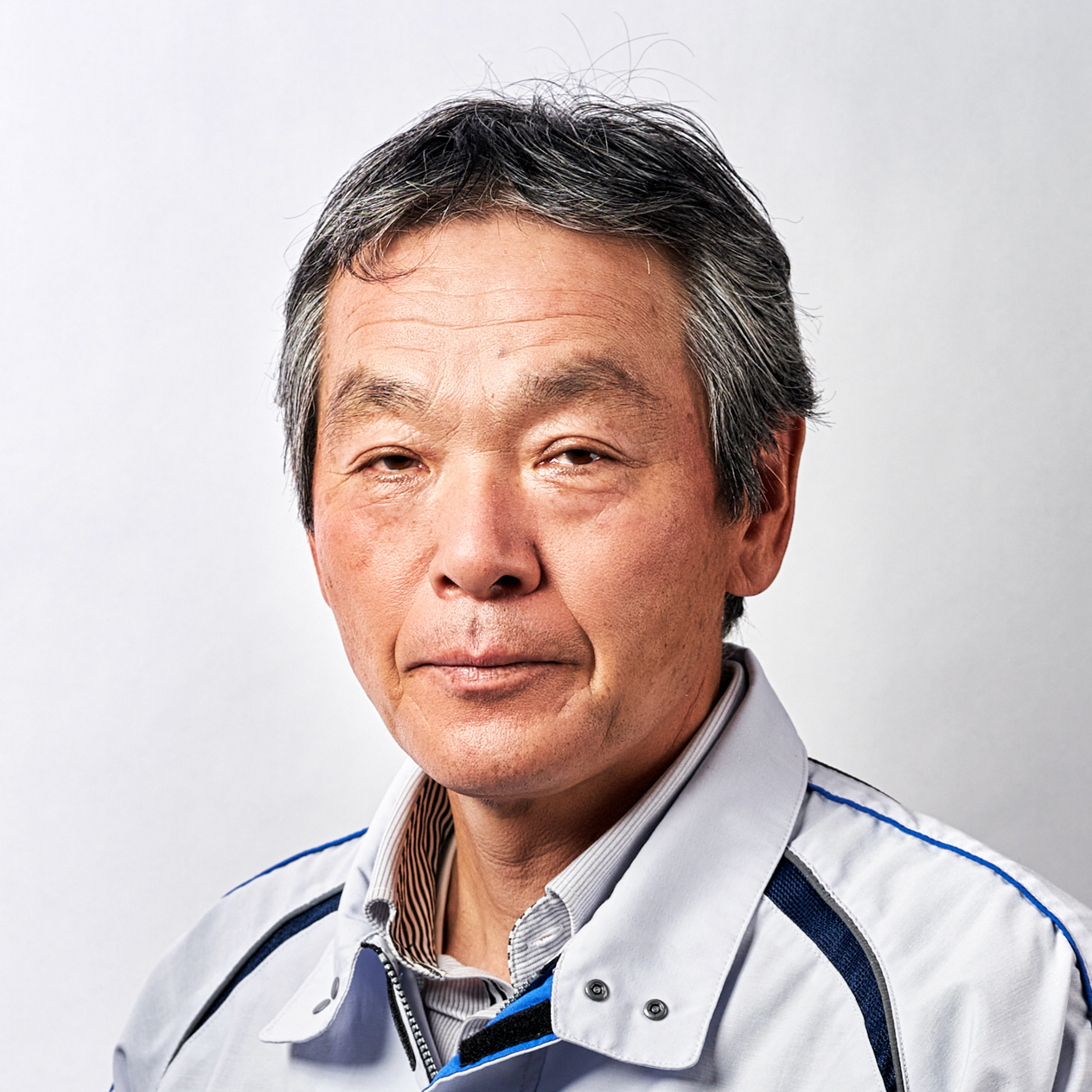
監修者
山本 昭則
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車のプレスにて39年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。改善活動には時に大変な場面もあります。それを乗り越える笑顔、会話を特に大事にしています。休日は趣味の山小屋づくりで精神統一をし、日々の仕事の英気を養っています。
「問題解決の8ステップ」は、トヨタで実践される問題解決の思考法です。8つのステップを踏むことで、解決までのプロセスを着実に進めます。
- 問題の明確化:何が問題かを考える
- 現状把握:現状を理解する
- 目標設定:何を目指すか決める
- 要因解析:なぜ起きるか考える
- 対策立案:対策案を考える
- 対策実施:対策を実行する
- 効果確認:効果を確認する
- 標準化・再発防止:後戻りを防ぐ
論理的な思考による一連のステップを踏むことで、勘や経験による思い込みを排除し、効率的に問題を解決することができます。
参照記事:問題解決の8ステップとは?トヨタの問題解決プロセスを解説
本記事では、8つのステップの「対策立案」について詳細に解説します。
対策案はできる限り多く出す
真因を特定したら、「どうすれば真因をなくすことができるか」を徹底的に考えます。ここでのポイントは、真因ごとにできるだけ多くの対策案を出すことです。
対策案を出す際には、次のような視点から考えることでアイデアが湧いてきます。
- 排除:それをやめてしまったらどうか
- 正反:それを反対にしたらどうか
- 拡大と縮小:大きくしたらどうか、小さくしたらどうか
- 結合と分散:それを結んだり、分けたりしたらどうか
- 集約と分離:まとめてみる、分解してみたらどうか
- 付加と削除:付け加えてみる、取り去ってみたらどうか
- 順序と入れ替え:順序を組み立て直す、作業手順を入れ替えたらどうか
- 共通の差異:違った点を活かしてみたらどうか
- 充足と代替:ほかに使えるか、他のモノに替えたらどうか
- 平行と直列:同時におこなったらどうか、順次おこなったらどうか
5つの視点から対策案を絞り込む
考えつく限りの対策案を出したら、それぞれの対策案を評価して絞り込んでいきます。絞り込む際には5つの視点で考えます。
- 効果:真因をなくすことができるか。目標を達成できるか。
- 実現可能性:実際に、無理なく対策を実行できるか。他の部署や組織を巻き込む必要はあるか。
- コスト・工数:どれほどの費用や時間がかかるか。何人でやれば納期に間に合うか。
- リスク:対策を実行する段階でリスクはあるか。
- 自己成長:この対策の実行を通じて、自分自身が成長できるか。
この際に、「対策を実行すると、何が起きるのか」をリアルに想像することが大切です。対策が真因を解決するためにどれだけ有効であっても、従業員の安全が損なわれたり、お客様に損害を与えるようであれば、対策案としては適当ではありません。目の前の問題を解決することだけでなく、その影響度を考えることも大切です。
また、対策案は自分の責任の範囲で考えるのが原則です。お客様や他部署にお願いする対策案では、他人事になってしまうだけでなく、対策を求められたほうも、押しつけられた施策ではモチベーションがあがりません。
対策の優先順位を決める
対策案を絞り込んだら、どの対策から取り組むかを決めます。真因が複数ある場合などは特に、すべての対策案を同時に取り組むことは難しいです。現実的に、どの真因の、どの対策から手をつけるか、優先順位を決める必要があります。
対策案の優先順位をつける際には、「安全」「品質」「コスト」「難易度」「効果」といった切り口について、「◎」「〇」「△」「×」などの評価を行い、「◎」が並んだ対策案から取り組んでいきます。また、最も優先順位の高い対策に取り組んでも、うまく効果があらわれないケースや、対策を複数組み合わせることで、相乗効果が生まれるケースもあります。1つの対策に取り組んだら、2番手、3番手の対策も順次実施していくことが大切になります。
またこのような切り口のほかに、その対策案が「現実的かどうか」という点もポイントになります。お金がかかるような対策や、まわりを巻き込まなくてはいけない対策などは、いくら効果が高いことが予想できても、実行までに時間がかかってしまいます。まずは現実的に自分たちができる対策から始める、という視点も大切です。
具体的な実行計画を立てる
取り組む対策を決めたら、具体的な実行計画をつくります。5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)にそった明確な計画に落とし込み、関係者や関連部署との間で意見調整を行って合意を得ます。また、チェック機能の計画を立てておくことや、予想される障害などの影響も検証し、その場合の対応を考えておくことも大切です。
まとめ
問題解決における「対策立案」は、特定した真因に対して効果的かつ実行可能な対策を検討するフェーズです。
まずは柔軟な発想で、できるだけ多くの対策案を洗い出すことがポイントです。その後、効果・実現可能性・コスト・リスク・自己成長といった5つの視点から対策案を評価・絞り込みます。
実行にあたっては、現実的に自分たちの手で実行可能かも重要な判断軸です。さらに、優先順位を「安全」「品質」「効果」などの観点から評価し、段階的に実施する順序を決定します。最終的には、5W1Hに基づいた実行計画を策定し、関係者との調整と合意形成を図ることで、現実的かつ実効性のある問題解決プロセスが実現します。


RANKING
人気記事ランキング
-

重大災害を防ぐ「STOP6活動」とは?注意すべき6つの危険源や対策例を紹介
2024.09.27 -

問題解決の8ステップとは?トヨタの問題解決プロセスを解説
2025.04.25 -

トヨタ式の仕事の教え方!4段階の手順と6つの基本を解説
2025.01.17 -

問題解決の基本となる「発生型問題解決」と「設定型問題解決」とは?問題解決力の重要性も紹介
2024.09.27 -

自工程完結とは?品質を工程で作り込むしくみ
2024.09.11
RELATION
関連記事
-
TPM活動とは?8本柱・16大ロス・自主保全7ステップまで徹底解説
2026.01.29 -
QCDSとは? 優先順位、QCDとの違い、Sの意味(Safety/Service)を解説
2025.12.22 -
改善が進む職場を作る!現場リーダーが実践すべき3つのポイントとは?
2025.09.19 -
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説
2025.04.11 -
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
2025.04.04 -
オフィスワークの「ムダ」を発見!視える化のコツと実践方法を解説
2025.03.28

PAGE
TOP