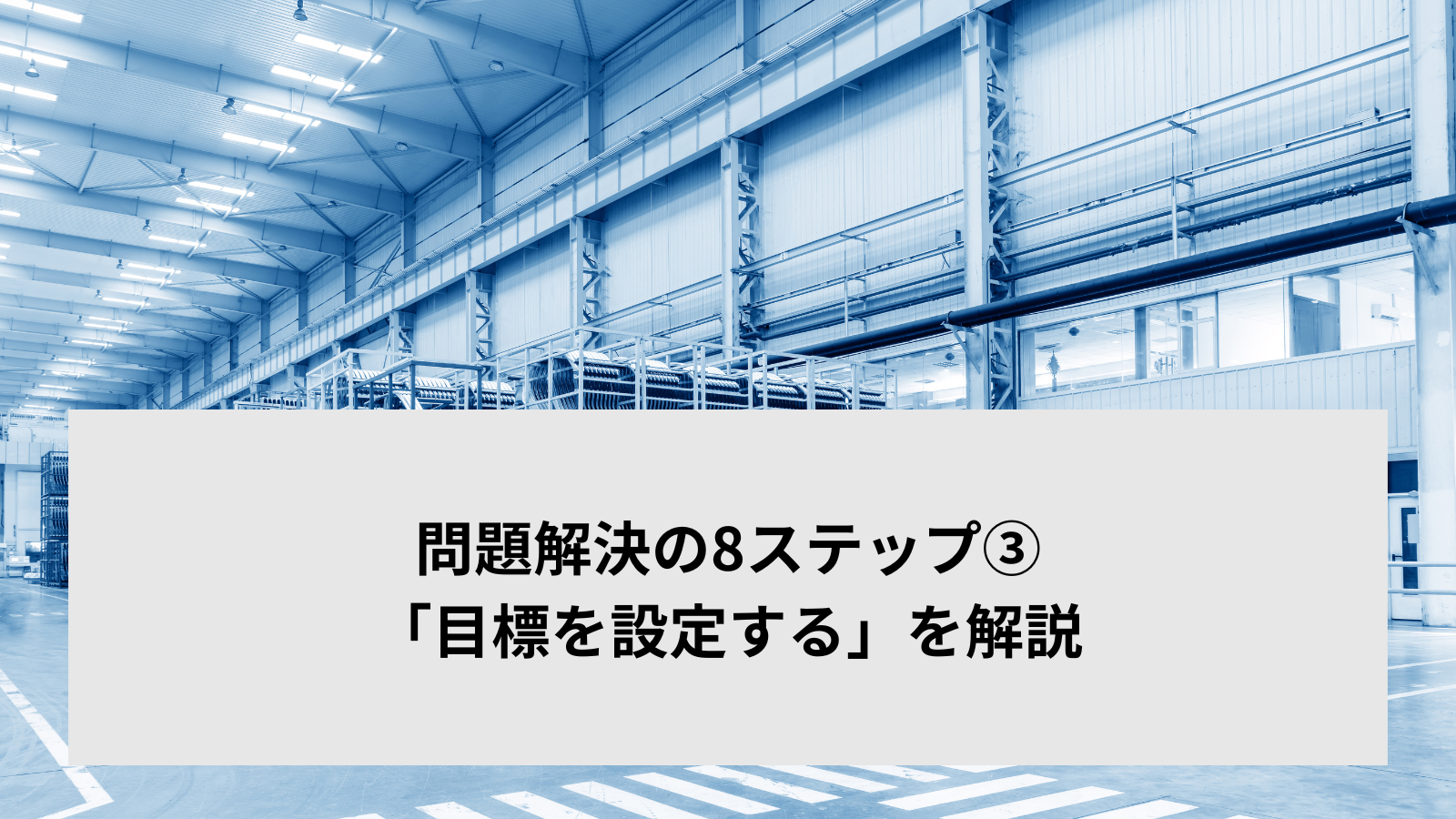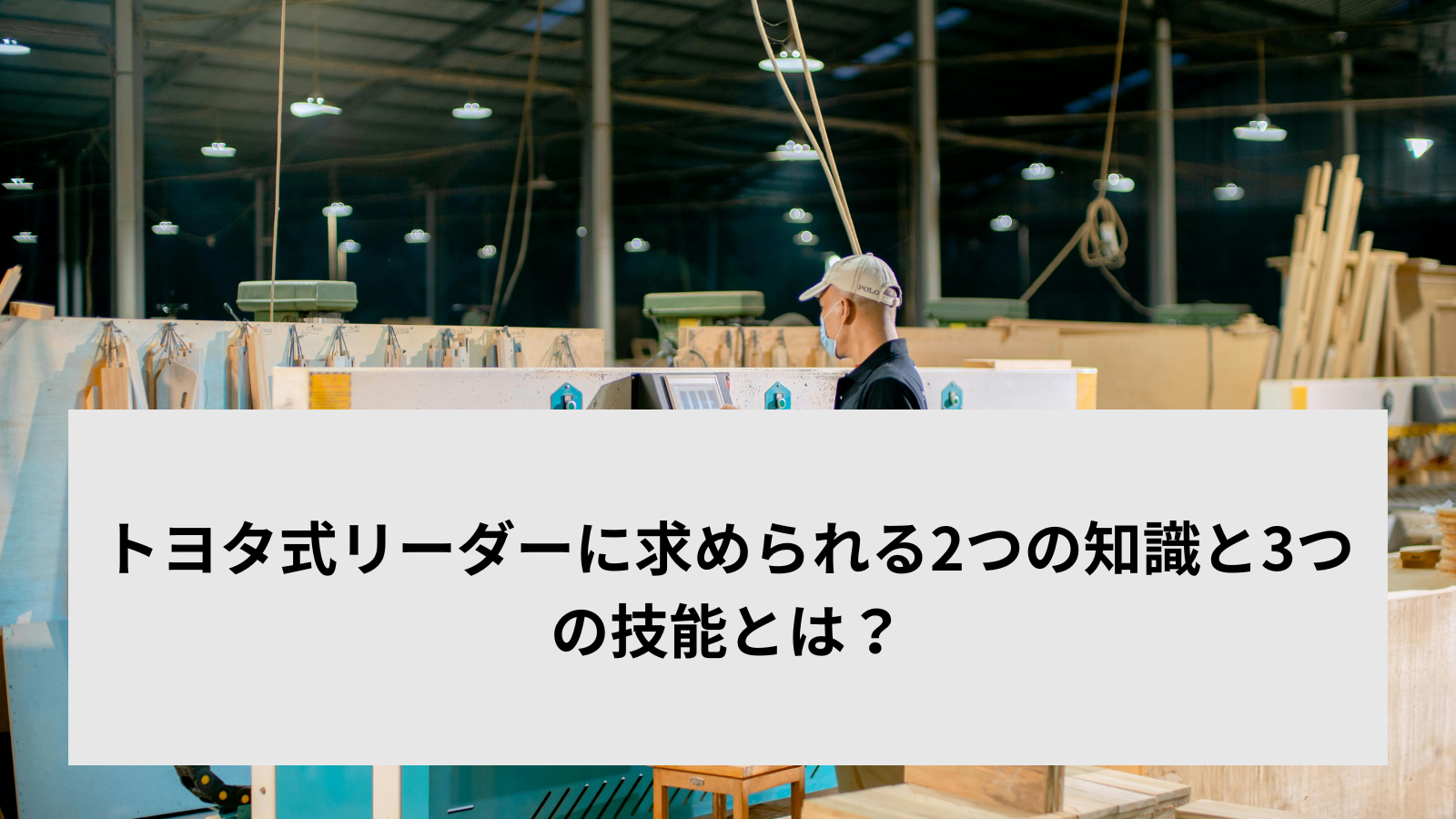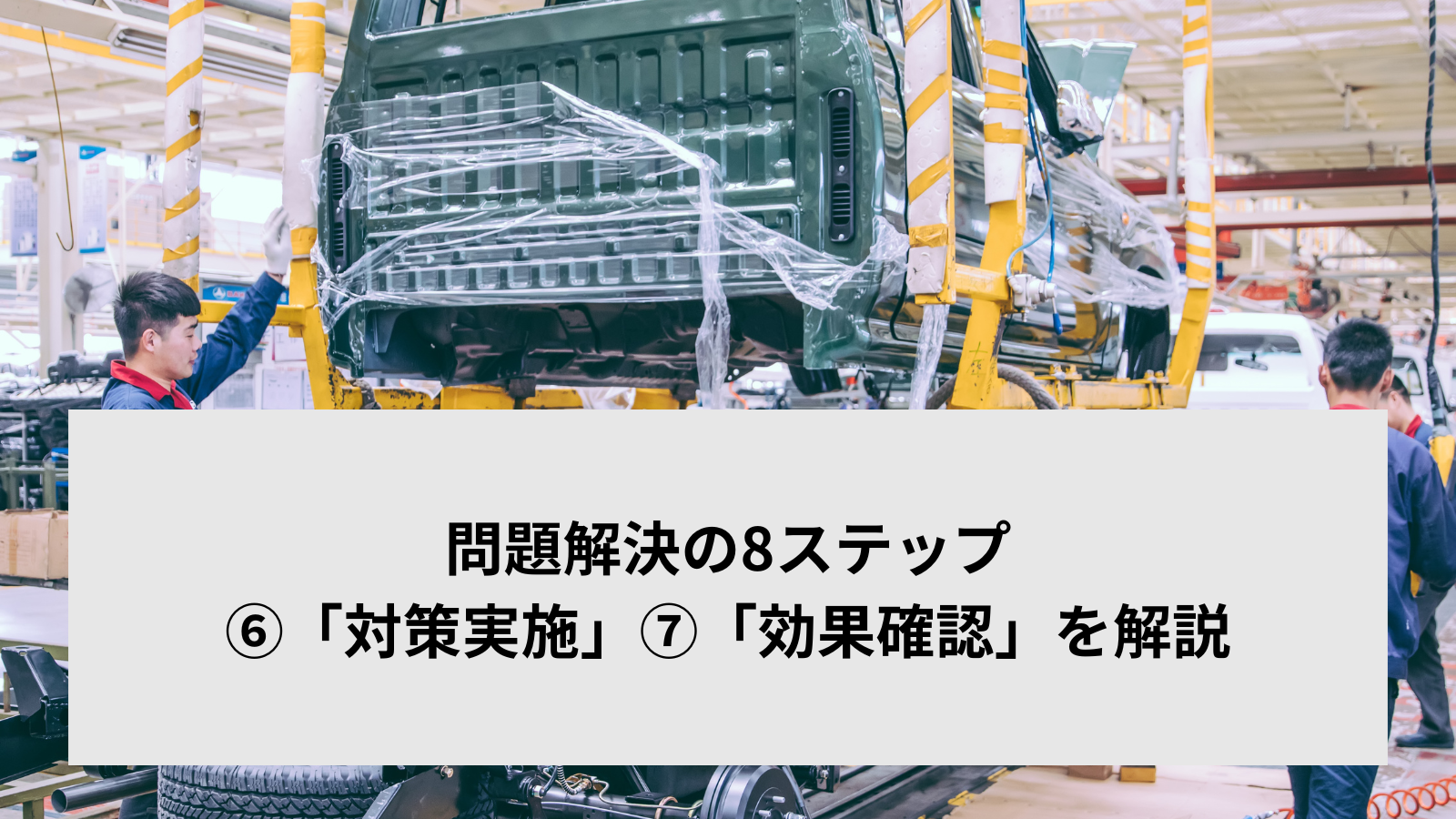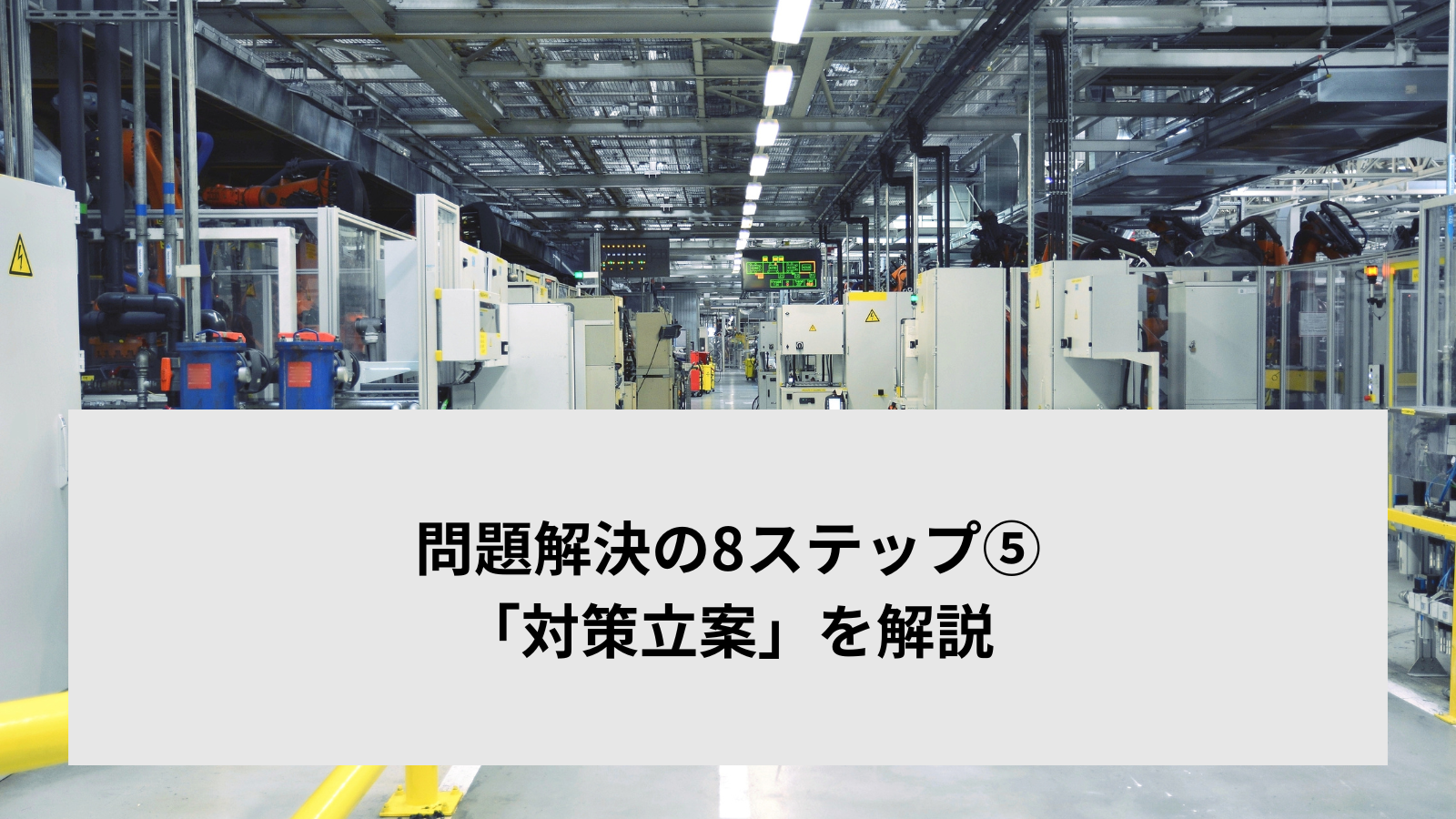OJT
問題解決の8ステップ③「目標を設定する」を解説

監修者
丸山 浩幸
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポートするエグゼクティブトレーナーをしています。大阪府出身、トヨタ自動車の品質管理にて41年の現場経験を経て、OJTソリューションズに入社しました。お客様の現場では「この改善、よかったで!」ともう一声の思いやりを大事に、仲間意識が高まるような改善活動ができるよう日々伴走しています。
「問題解決の8ステップ」は、トヨタで実践される問題解決の思考法です。8つのステップを踏むことで、解決までのプロセスを着実に進めます。
- 問題の明確化:何が問題かを考える
- 現状把握:現状を理解する
- 目標設定:何を目指すか決める
- 要因解析:なぜ起きるか考える
- 対策立案:対策案を考える
- 対策実施:対策を実行する
- 効果確認:効果を確認する
- 標準化・再発防止:後戻りを防ぐ
論理的な思考による一連のステップを踏むことで、勘や経験による思い込みを排除し、効率的に問題を解決できます。
参照記事:問題解決の8ステップとは?トヨタの問題解決プロセスを解説
本記事では、8つのステップの「目標設定」について詳細に解説します。
達成目標を決めるときに気をつけるポイント
問題点が明確になったら、取り組む問題に対して「達成目標」を決めます。その際に注意すべきポイントを4点解説します。
「やること」を目標にしない
1点目は、「やること」を目標にしないことです。
例えば、「部門の企画提出件数を増やす」という表現は、単に実施する内容を表明しているに過ぎません。この場合、目指す地点を示すような目標にする必要があり、「今年度中に各部員がそれぞれ企画書の採用率を20%アップさせる」といった形が適切です。
手段を目標にしない
2点目は、手段を目標にしないことです。
例えば、企画書の採用率を上げるためには「情報収集」や「プレゼン力のアップ」が必要となるかもしれませんが、これらはあくまで目標を達成するための手段に過ぎません。手段が目標になってしまうと、その手段を講じた段階で満足してしまい、問題解決に結びつかない結果となってしまいます。
「あるべき姿」と「目標」を一致させない
3点目は、「あるべき姿」と「目標」を一致させないことです。
問題解決は、あるべき姿と現状のギャップを埋めるために解決すべき問題テーマを決め、具体的な問題点に絞り込んで取り組むのが正しいプロセスです。そのため、ここで設定する目標は、その細分化された具体的な問題を取り除くための目標でなければなりません。
例えば、「国内売上の前年対比20%アップ」が「あるべき姿」である場合、それをそのまま目標とすることはできません。より具体的な目標として「東北地方の売上の前年対比40%アップ」や「20代顧客の売上の前年対比25%アップ」といった形にする必要があります。
つまり、目標設定の段階では、あるべき姿に到達する過程としての目標を立てることになります。目標が達成されたら貢献度を確認し、次の問題に取り組みます。こうして一つずつ目標を達成することで、あるべき姿の実現を目指していきます。
少し背伸びするような目標を立てる
4点目は、すぐに達成できる目標を立ててしまうことです。
人は自分に甘いため、どうしても簡単に達成できそうな目標を立てがちです。自ら解決する意思を込め、少し背伸びをしなければならないような目標を立てることが問題解決力を向上させるコツです。
あまりにも実現性のない目標は考えるべきではありませんが、自分が「これくらいならできる」と思うレベルの2〜3割増しの目標を設定するとよいでしょう。
具体的な数値で示す
達成目標を決定する際には、「何を」「いつまでに」「どうする」という3つの要素を具体的に設定することが求められます。特に「どうする」の部分では、目標を数値で明確に示す必要があります。
例えば、「クレーム品の発生を減らす」という漠然とした目標では、たとえ1件でも減れば目標達成となり、真の問題解決にはつながりません。「クレーム品の発生を、12月末までに、月2件以下とする」のように、具体的かつ定量的な数値であらわすことがポイントです。
目標数値を決める際は、現状データや部署の目標を踏まえ、現実的な範囲で上司などと話し合って決定するとよいでしょう。また、期限を明確に区切ることも大切です。行動を促し、目標が単なる願望で終わることを防ぎます。
営業やスタッフ部門、サービス業など、数値化が難しいとされる分野においても、できるだけ数値化する工夫をすることで、情熱と責任感を持って目標達成に向かうことができ、具体的な改善効果を数値で実感することが可能になります。
定性的な目標は、KPIを活用する
売上高や利益率、販売台数、コスト削減率、リードタイムの短縮など、定量的に数値化できる目標は設定しやすいですが、なかには「ブランドイメージを高める」のように、定性的な目標で数値に置き換えが難しい場合があります。
このような場合、KPI(Key Performance Indicator)を活用することで、定性的な目標を定量的に把握することが可能になります。KPIとは、「目標を達成するための重要な業績指標」を指します。
例えば「ブランドイメージを高める」という目標に対して、「リピート率」や「広告出稿金額」などをKPIとして設定することで、ブランドイメージをある程度定量化できます。さらに、「店舗の清掃状態」などといった、ブランドイメージ向上に貢献するものでも数値であらわしにくい指標であれば、その「状態」をレベル化し、「1時間に1度の清掃チェックができていればレベル5」「1日に1度であればレベル3」といった具体的な基準を設けることで、定量的な追跡が可能となります。
目標では抽象的な言葉は使わない
抽象的な言葉を使わないことも目標設定のポイントになります。
具体的には、「頑張る」「効率を上げる」「検討する」「対応する」「徹底する」といった曖昧な言葉は避けるべきです。曖昧な言葉を使用すると、目標が達成できなかった際に「頑張りました」といった主観的な言い訳の余地を生み出してしまいます。
そのため、目標は具体的な数値に置き換えることが不可欠であり、客観的に評価できる形で示すことが大切です。
まとめ
問題解決における「目標設定」は、解決への方向性を明確にするための大事なステップです。
達成に向けてチャレンジする意志を持って、定量的かつ具体的な目標を設定することが重要です。抽象的な表現にせず、できる限り数値に置き換えることを意識しましょう。
現場での取り組みをより確かなものにするためにも、ぜひ実践してみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタ式リーダーに求められる2つの知識と3つの技能とは?
2025.09.26 -
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介
2025.09.05 -
問題解決の8ステップ⑧「標準化・再発防止」を解説
2025.08.22 -
問題解決の8ステップ⑥「対策実施」⑦「効果確認」を解説
2025.08.15 -
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
2025.08.08 -
問題解決の8ステップ④「要因解析」を解説
2025.08.01

PAGE
TOP