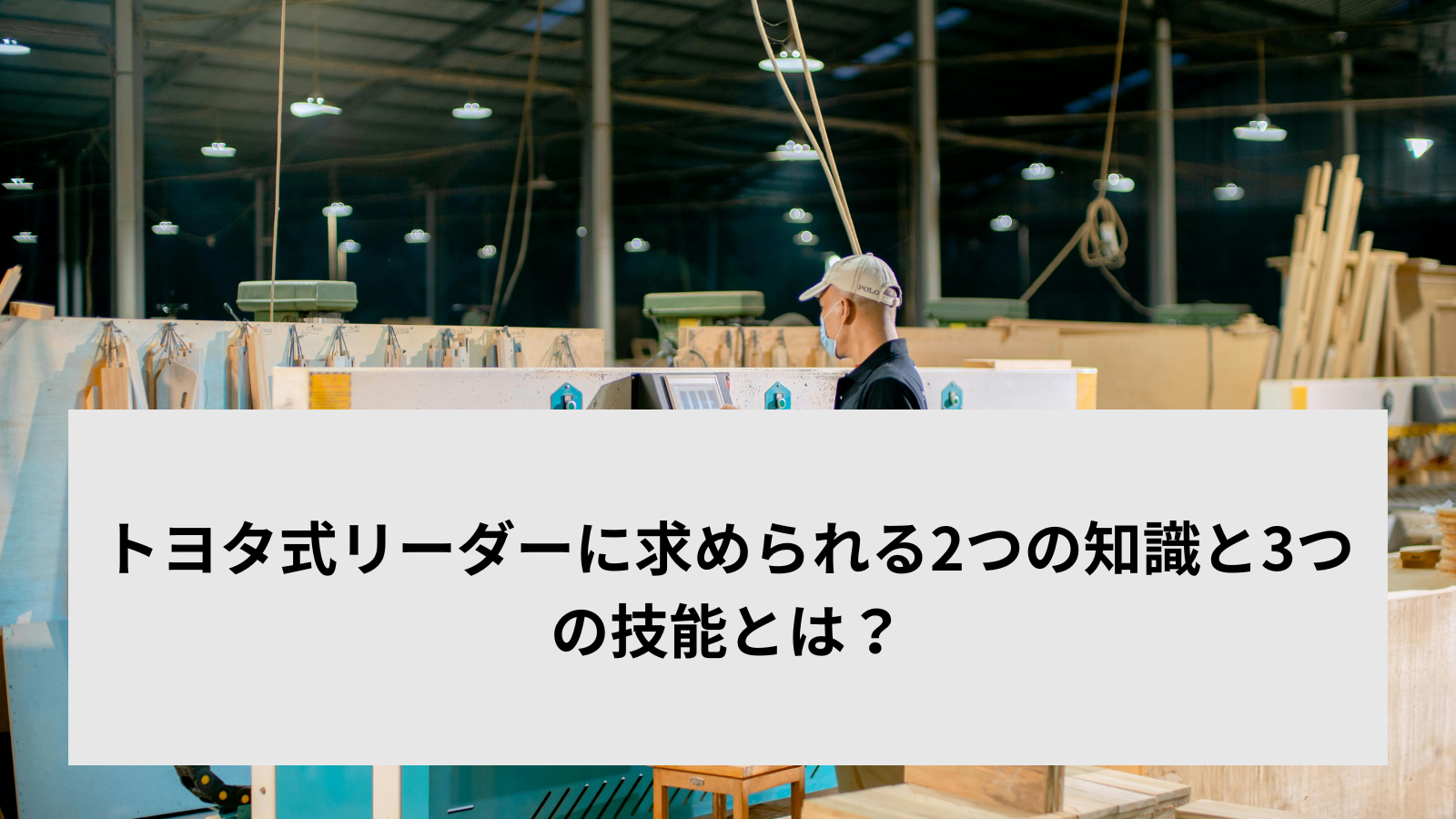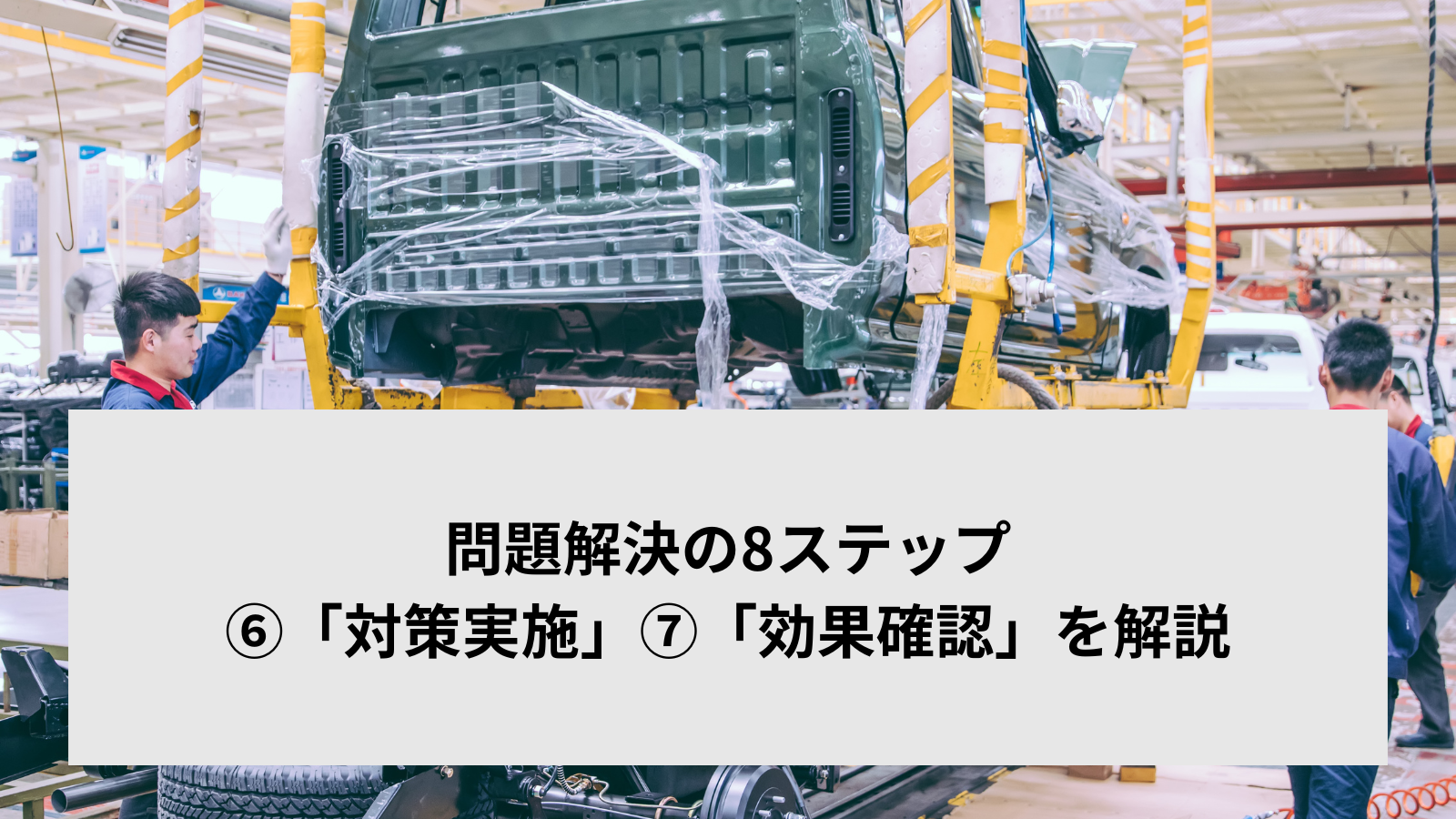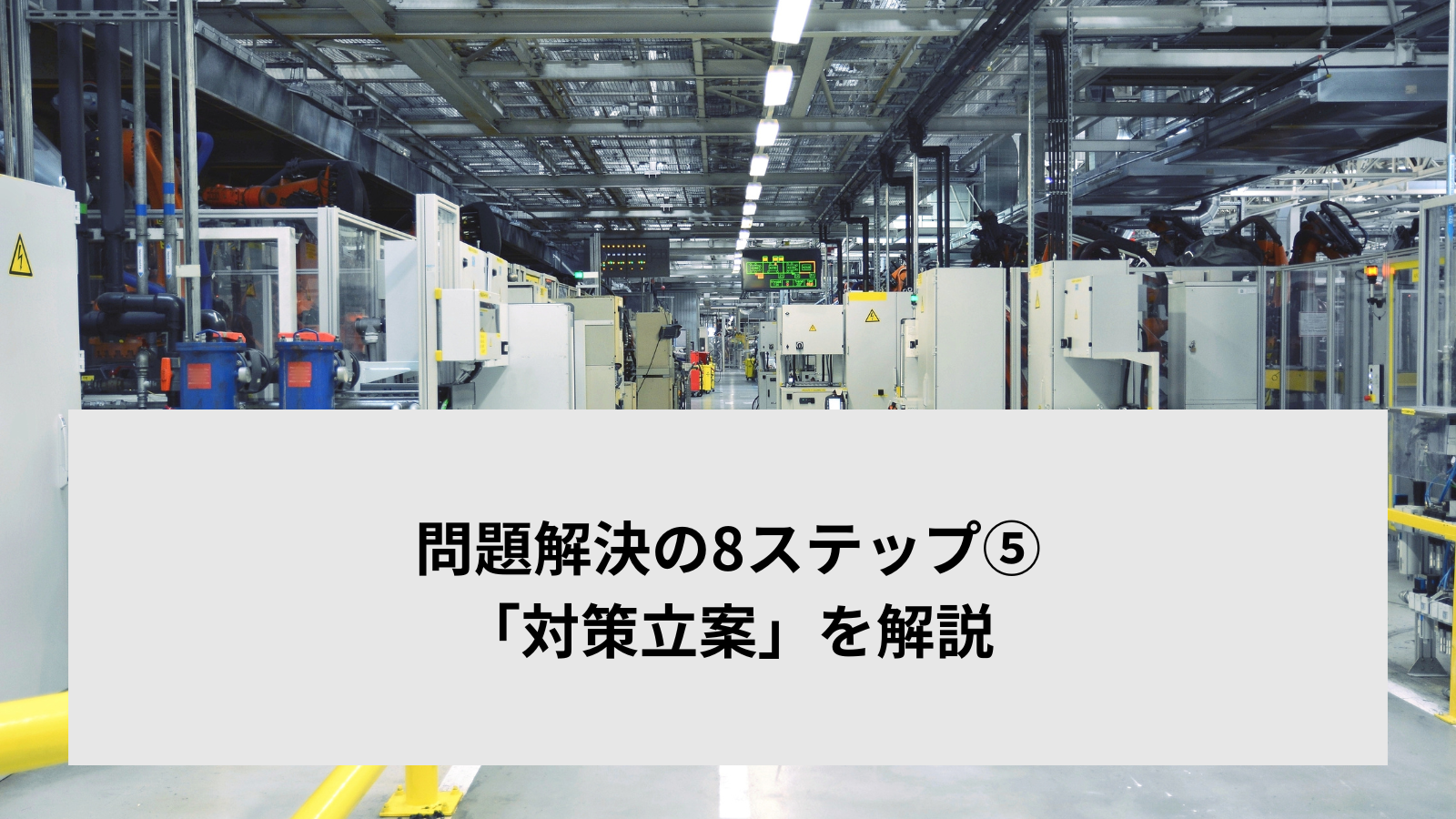OJT
問題解決の8ステップ②「現状把握」を解説

監修者
三尾 恭生
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車にて42年の現場経験、管理職の経験を経てOJTソリューションズに入社しました。座右の銘は「不易流行」。変える勇気と変えない勇気を持つことが大事だと信じ、現地現物でお客様と伴走しています。
「問題解決の8ステップ」は、トヨタで実践される問題解決の思考法です。8つのステップを踏むことで、解決までのプロセスを着実に進めます。
- 問題の明確化:何が問題かを考える
- 現状把握:現状を理解する
- 目標設定:何を目指すか決める
- 要因解析:なぜ起きるか考える
- 対策立案:対策案を考える
- 対策実施:対策を実行する
- 効果確認:効果を確認する
- 標準化・再発防止:後戻りを防ぐ
論理的な思考による一連のステップを踏むことで、勘や経験による思い込みを排除し、効率的に問題を解決することができます。
参照記事:問題解決の8ステップとは?トヨタの問題解決プロセスを解説
本記事では、8つのステップの「現状把握」について詳細に解説します。
問題を層別し、問題点を特定する
現状把握のステップは、問題テーマをより細かく、具体的に取り組む問題点まで絞り込むプロセスになります。
私たちが直面する問題の多くは、さまざまな小さな問題が複雑に絡み合って生じているため、大きくて曖昧な状態であることが多いです。
例えば、「クレーム品の発生を減らす」という問題テーマだけでは、何が本当に解決すべき問題なのか、どこから手を付ければよいのかが不明確なままです。また、問題が大きなままだと、個人のレベルでは具体的に何をすべきかが見えてきません。
そこで、大きな問題をより小さな具体的な問題へと整理し、優先的に取り組むべき「攻撃対象」を特定することが求められます。経験豊富なベテランや優秀な人ほど、過去の成功体験から「この問題にはこう対処すればうまくいく」という思い込みでいきなり対策に走りがちですが、これには気を付けなければなりません。本来解決すべき問題にたどり着けず、的外れな対策を打ってしまう結果につながる可能性があるからです。
事実をデータで把握する
現状把握を正確に行うためには、事実を定量的な数値で示しておく必要があります。「なんとなく」の現状把握では、結果として曖昧な問題しか特定できず、それに対する対策も曖昧なものになってしまうためです。
工程の状況や時系列の変化など、事実に基づいた正しいデータを収集、整理します。
問題を「層別」し具体化する
問題の現状をデータで把握したら、次にデータの「バラツキ」を見つけます。この「バラツキ」があるところに、問題が潜んでいるとトヨタでは考えます。
そのための方法が「層別」です。層別とは、例えば「人別」「年齢別」「場所別」「商品別」「機種別」など、共通点を持つグループに分類してデータを多面的にとらえることを目的とした分析手法です。これにより、これまで見えなかったデータの特性や偏り、すなわち「バラツキ」がはっきりと浮き彫りになります。
具体的な例として、「クレーム品の発生が工場別でワースト1位」という問題があったとします。これを以下のように層別していくことで、解決すべき具体的な課題が見えてきます。
まず、「発生部署別」に層別すると、クレームの約60%が「製造部門」で発生していることが判明しました。これは、さまざまな発生部署があるなかで製造部門の発生率が圧倒的に高いという「バラツキ」を示しています。
次に、製造部門で発生したクレーム品を「品名別」に層別すると、そのうちの多くが「商品A」であることが判明します。
さらに、商品Aのクレームを「不良の種類別」に層別すると、最も件数が多いのが「ラベルの貼り間違い」であることが特定されます。
この一連の層別によって、「製造部門における商品Aのラベルの貼り間違い」という、最も優先的に解決すべき具体的な問題だと特定されるのです。
この事例のように、明確な「バラツキ」が見られる層別は問題の所在を具体化するうえで効果的な切り口になりますが一方で、どの層でも発生頻度が同じような場合は「感度が悪い」層別となり、問題の特定にはつながりません。適切な層別を見つけるには慣れが必要で、時にはなかなかたどり着けないこともありますが、さまざまな切り口を試すことが大切です。感度が悪いと感じたら、その切り口に固執せず、次に疑わしい層別に取り組むのがコツです。
4つのWで層別する
層別の切り口は多岐にわたりますが、どこから手を付ければよいかわからない場合、基本的なアプローチとして「4つのW」を用います。これは、「何が(What)」「どこに(Where)」「いつ(When)」「誰が(Who)」という視点からデータを分類する方法です。具体的には、以下のような切り口が挙げられます。
- 何が(What):製品別、用途別、カテゴリー別
- どこに(Where):工程別、ライン別、部位別
- いつ(When):月別、曜日別、シフト別
- 誰が(Who):年齢別、職位別、経験年数別
このようにさまざまな層別を試していくうちに、「この問題の場合は、この層別が怪しい」というように勘が働くようになります。まずは、できるだけたくさんの切り口から問題を層別することを意識するとよいでしょう。
現地現物でプロセスをみて問題点を特定する
取り組む問題を絞り込んだら、さらに現場のプロセスを調査します。その際に、常に心がけておきたい考え方が「現地現物」です。これは、「現場を見ることによって真実が見える」というトヨタの現場で重視されている考え方です。
問題のある状態は突然生じるものではなく、そこに至るプロセスが必ず存在します。現地現物に基づき、実際に起きていることを自分の目と耳で確認しながらプロセスをさかのぼることで、問題の発生箇所を特定することができます。
小問題は大問題につながっている
問題解決は、大きな問題を一気に解決しようとするのではなく、小さな問題から着実にアプローチしていくことが成功への鍵となります。
例えば「製品の品質を上げる」といったテーマは、あまりに広範で、どこから手をつけるべきか不明瞭になりがちです。
そこで、問題を「傷をなくす」「へこみをなくす」といった具体的な課題に絞り込むことによって、対策の実行へとつなげることができます。
大きな問題は、いずれ取り組むべきものですが、これらを一気に片付けようとすると、やることが多すぎて挫折につながります。すぐに解決できないような大きな問題は、「今年はまずこの部分に手を付ける」というように、少しずつ周囲から崩していくアプローチもよいでしょう。解決できる小さな問題から取り組むことで、成功体験が自信になります。最も避けるべきは、「時間がかかるから」という理由で、いずれ解決しなければならない問題を放置してしまうことです。
まとめ
問題解決8ステップにおける「現状把握」は、取り組む問題をより具体化して対象を絞り込むステップです。
- 問題を層別し、具体化する
- 取り組む問題を決める
- 現地現物でプロセスを見て問題点を特定する
思い込みではなく、事実に基づいて、解決すべき問題を正確に定める姿勢が大切です。遠回りのように見えても、堅実なアプローチが結果を生みます。ぜひ実践してみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
トヨタ式リーダーに求められる2つの知識と3つの技能とは?
2025.09.26 -
ビジョン指向型の問題解決とは?考え方や事例を紹介
2025.09.05 -
問題解決の8ステップ⑧「標準化・再発防止」を解説
2025.08.22 -
問題解決の8ステップ⑥「対策実施」⑦「効果確認」を解説
2025.08.15 -
問題解決の8ステップ⑤「対策立案」を解説
2025.08.08 -
問題解決の8ステップ④「要因解析」を解説
2025.08.01

PAGE
TOP