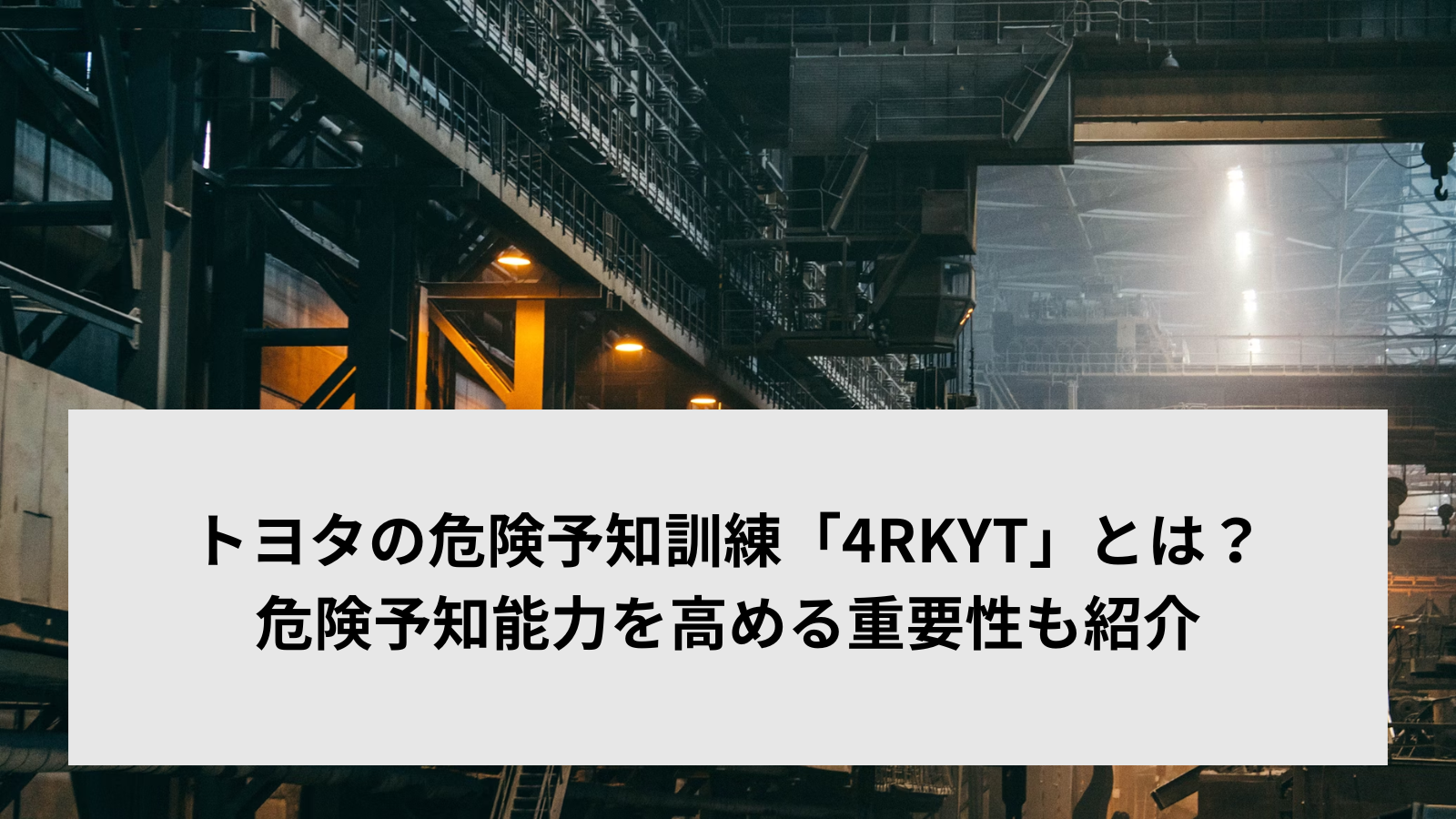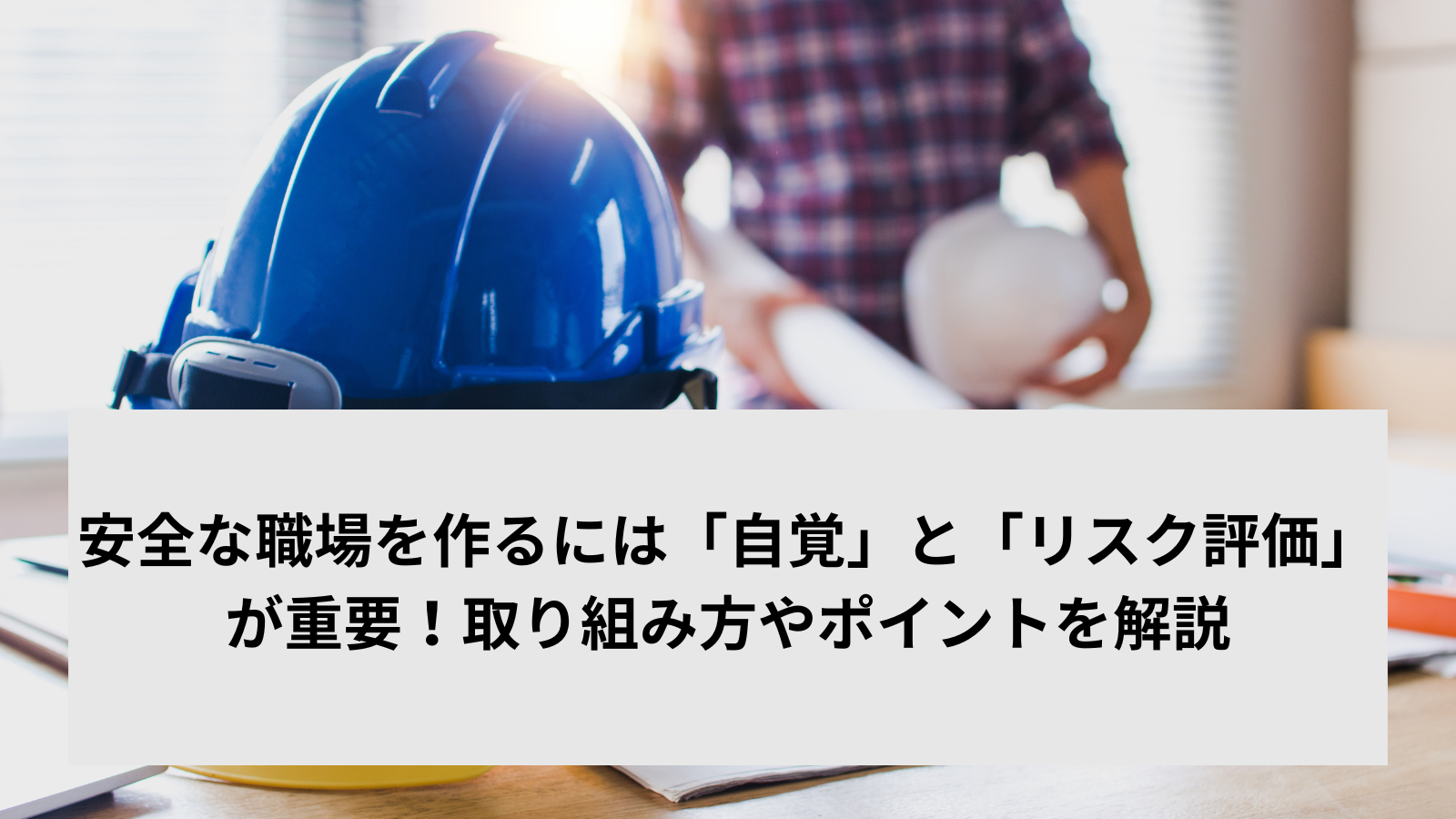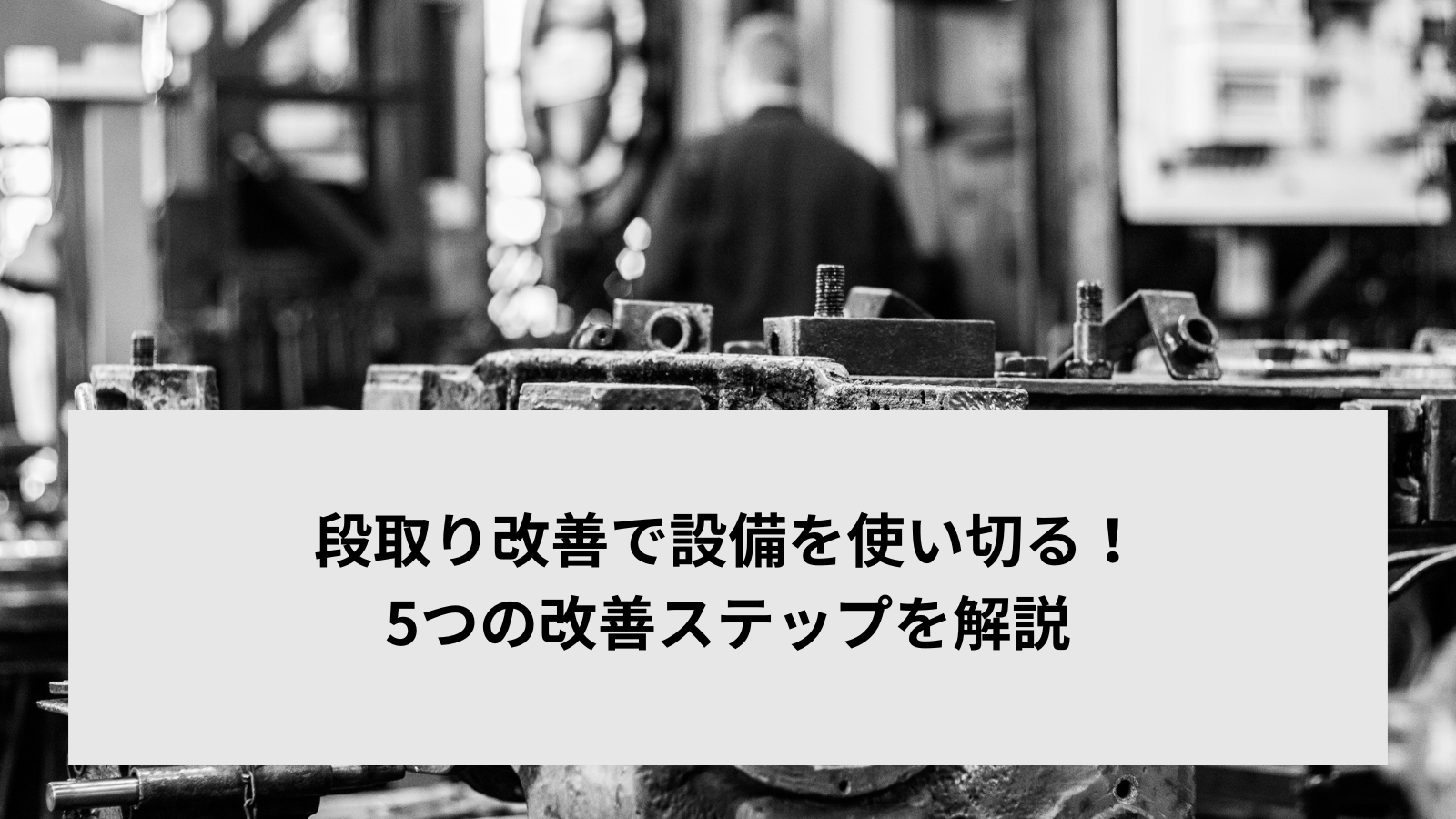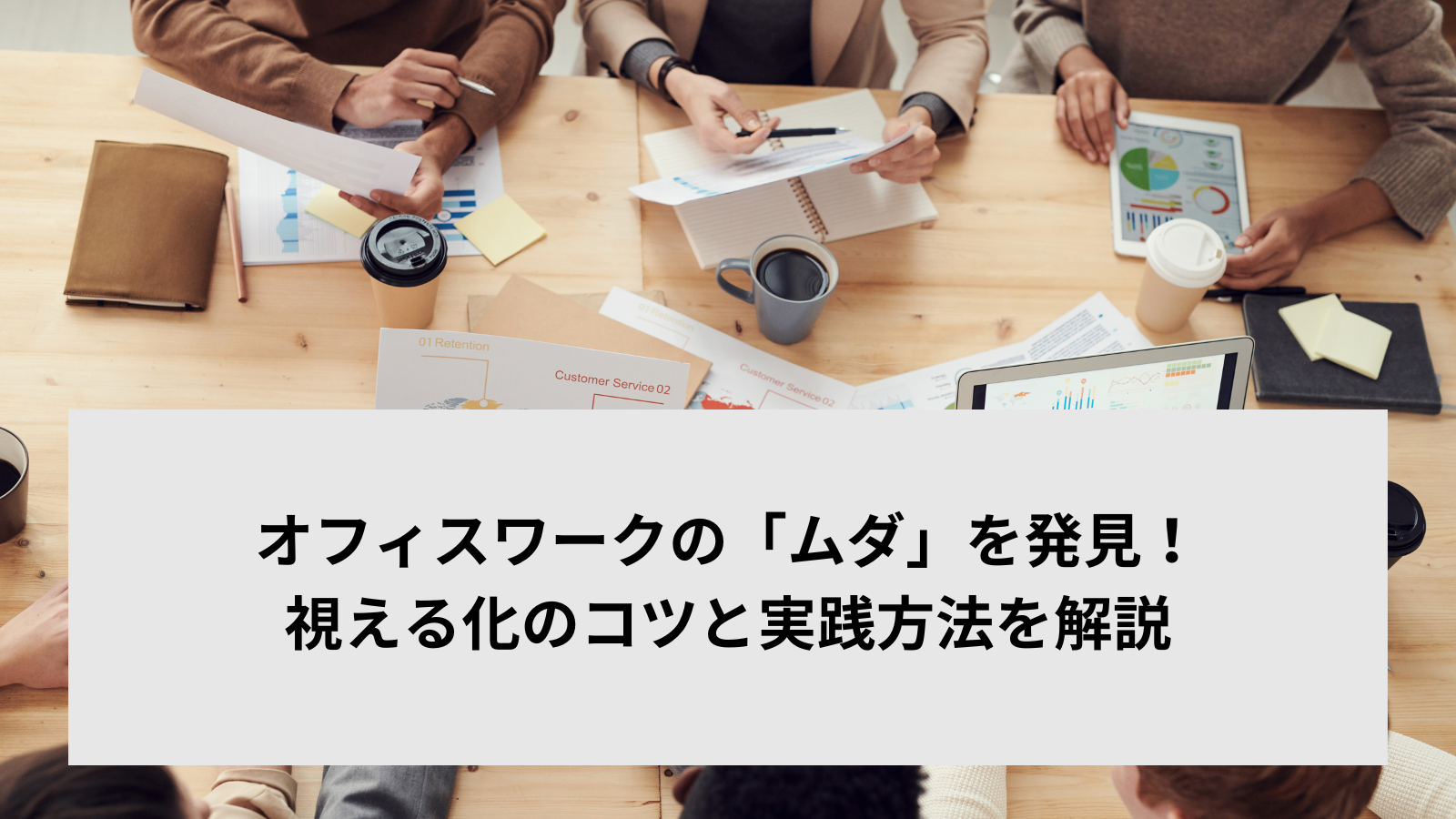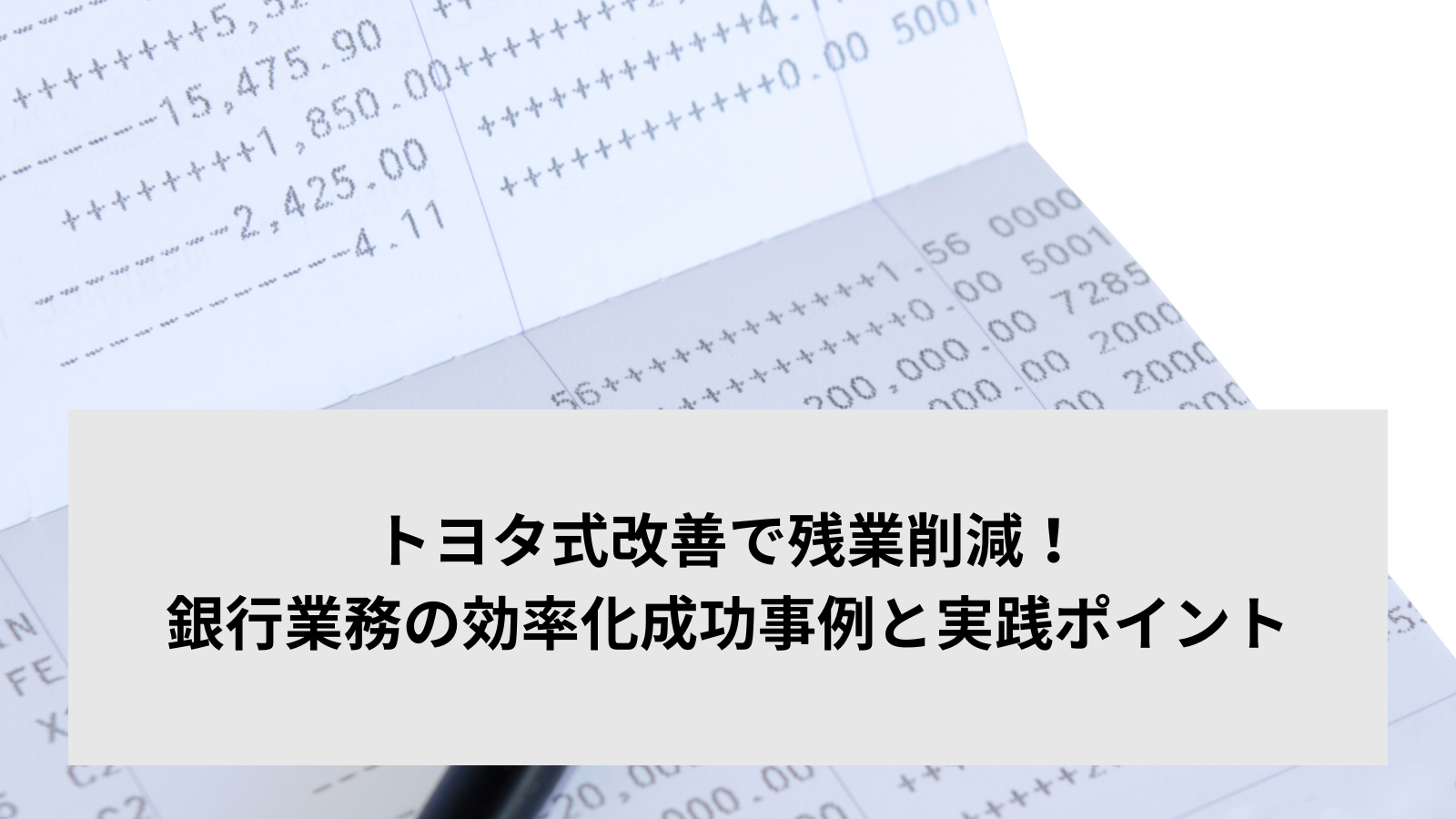現場力向上
トヨタの危険予知訓練「4RKYT」とは?危険予知能力を高める重要性も紹介

監修者
見城 吉昭
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車の機械加工にて39年の現場経験を積み、OJTソリューションズに入社しました。趣味の読書や旅行で自分の世界を広げながら、現場で働く人の声を大事に「働く人の心のための改善」に日々取り組んでいます。
工場などの生産現場には多くの危険が潜んでいます。労災を防ぐための物的な対策はもちろん重要ですが、実際に作業をするメンバーの危険に対する感度、危険予知能力を高めることが大切です。トヨタでは危険予知訓練として「4R(ラウンド)KYT」を定期的におこなっています。
4RKYTをおこなうことで危険を危険と認識でき、自分が働く職場に危険が潜んでいないか細心の注意を払えるようになります。また、段階を踏んで訓練をおこなうことで、どのような作業や場所に危険が発生しやすいか予測する力、危険に対してどう手を打つか考える力も習得できます。
本記事では、4RKYTの概要をはじめ、取り組みのポイントや訓練をおこなった体験談もお伝えします。メンバーが安心して仕事に取り組める環境づくりを目指している方は、ぜひご覧ください。
4RKYTとは?危険予知訓練の基本を3分で理解
4RKYTは、4R(ラウンド)とKYT(ケー・ワイ・ティー)を合わせた言葉です。KYTとは、「危険(Kiken)予知(Yochi)訓練(Training)」の頭文字を取った略語で、職場や作業現場で起こりうる危険を事前に予測し、その対策を立てることで労働災害や事故を防止する安全管理活動のことを指します。
KYTは単なる危険探しではありません。チーム全員が参加して危険要因を洗い出し、具体的な行動目標を設定することで、「安全な行動を習慣化する」ことが本質的な目的です。この訓練により、作業者一人ひとりの危険感受性を向上させ、ヒューマンエラーによる事故を効果的に防止できます。
そして4Rとは、KYT活動の際に4つのラウンドに分けて行うということです。具体的には以下の4つのラウンドに分けられます。
- 危険箇所の洗い出し
- もっとも危険な箇所の特定
- 対策案を考える
- 対策の決定と唱和
KYTの意味と3つの基本原則
KYT(危険予知訓練)を効果的に進めるためには、「チーム活動」「現場主義」そして「問題意識の共有」という三つの重要な原則があります。
まず、KYTはチームでコミュニケーションをとり、話し合いで進めることが不可欠です。それぞれの作業者が持つ異なる視点や経験を活かし、多角的に危険要因を洗い出すことで、より精度の高い危険予知が可能になります。
次に、訓練は常に現場主義で進めます。机上の空論ではなく、実際の作業環境やその時々の状況に即して危険を予知することが重要です。現場のリアルな状況を具体的に想定してこそ、実効性のある対策を見つけ出すことができます。
そして最後に、発見された危険要因とそれに対する対策は、チーム全体で問題意識を共有しなくてはなりません。たとえ一人が危険に気付いても、その情報が共有されなければ事故防止にはつながりません。チームで話し合い、合意を形成することで、全員が同じ目的意識を持って安全行動に取り組むことができます。
なぜ今KYTが重要なのか?労災統計データが示す必要性
厚生労働省の労働災害統計によると、労働災害発生原因全体のうち96.4%が、労働者の不安全な行動に起因すると言われています。労働災害技術の進歩により設備や機械の安全性は向上していますが、人間の不安全行動による事故は依然として多く発生しているのが現状です。
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo90_1.html)
また、近年では働き方改革や労働安全衛生法の強化により、企業の安全管理責任がより厳しく問われるようになりました。KYTの実施は、法的な義務を果たすだけでなく、企業の社会的責任を果たす重要な取り組みとしても位置づけられています。「ケガを経験して一人前になる」という時代はとうの昔に過ぎ去っています。会社として、従業員の安全を守るために危険予知能力を高める機会を用意するのが経営の義務と言ってもいいでしょう。
4RKYTの具体的な手順
現場によって4RKYTの実践方法は異なりますが、トヨタでは例えば月に1回、30分ずつ4人~5人の班に分かれて業務時間内におこないます。メンバー構成はより多くの視点から現場を見られるよう、ベテラン作業員・中堅作業員・新人作業員と経験年数をバラバラにして構成します。
そして、実践する際は4RKYTシートを使い、リーダーと書記を決めて実作業や作業の動画、写真を見ながらラウンドごとに会話形式で進めていきます。複数人の視点で現場を見ることで、自分では気付けないような危険箇所に気付けるのが大きなメリットです。それぞれのラウンドの内容を詳しく解説します。
①危険箇所の洗い出し
1ラウンド目は、危険箇所の洗い出しです。作業の写真や動画を見ながら、どのような危険が潜んでいるのか意見を出し合います。メンバー全員に自分事と思ってもらうためにも、可能な限り実際に現場でおこなう作業を対象にするのが好ましいです。また、危険箇所については事実・予知を問わず、メンバー全員から意見が出るようにリーダーが進行役となって進めます。
1ラウンド目の重要なポイントは、原因と結果がわかる形で意見を出すことです。例えば、「脚立から身を乗り出しているから、落下する」など結果も含めて発言し、自分や仲間が危険にさらされるかもしれないという視点を持ち、自分事に置き換えさせることが大切です。また、出てきた意見は否定せずに、思いつく限り洗い出すようにします。
②もっとも危険な箇所の特定
2ラウンド目は、もっとも危険な箇所の特定です。1ラウンドで出てきた危険箇所のなかからもっとも危ないと思うものを絞り込んでいきます。災害の大きさや災害頻度、直近に災害が起こっているかなどを基準にして、一番対策すべきだと思われるものを1つだけ選びます。
ただし、基準に厳密さを求めすぎて会話が止まってしまうのは避けなければなりません。もちろん安全対策会議などでは厳密にすべきですが、あくまでも4RKYTはトレーニングの一環であるため、メンバー全員が「これが一番危ないため、対策したい」と共通して感じるものを選ぶことがポイントです。
③対策案を考える
3ラウンド目では、2ラウンド目で絞り込んだもっとも危険な箇所の対策案を考えます。具体的かつ自分達が実践可能な対策案を思いつくだけ全員で書き出します。このとき1ラウンド目と同じように、周りの意見を否定しないようにするのが重要です。
対策には人的対策と物的対策の2種類がありますが、できるだけ人的対策をメインに案を出すのがよいでしょう。もちろん物的対策の案を出してはいけないわけではありませんが、物的対策は時間とお金がかかり簡単にはできません。今日から自分ができる対策を思いつく能力を鍛えるためにも、まずは人的対策案を考えることが有効です。
例えば、足場に昇降機があって挟まれる危険が潜んでいる場合、例えば人的対策は「作業時に指定の立ち位置で両足を揃える」、物的対策は「安全な設備に交換する」が挙げられます。しかし、物的対策は自分ができる対策の範囲を超えてしまっていることが多いです。そのため、「4RKYTは人的対策を考える訓練」と捉えておこなうことがポイントです。
④対策決定と唱和
4ラウンド目では、対策の決定をします。3ラウンド目で考えた対策に優先順位をつけて、実際におこなう対策を1つに絞り込みます。そして、メンバーひとりひとりに「自分はこうする」と、行動目標を決めさせます。
最後は「〇〇、ヨシ!」を標語にしてチーム全員で指差唱和をおこなってください。唱和する理由は、チームで共通認識を持つことができ、また、耳に残ることで、少なくともその日の作業中は忘れないからです。このように、指差唱和には大きな効果があります。例えば「台車ストッパー、ヨシ!」など、決めた対策に対して指差唱和を徹底してみてください。
そして、対策を決めたらチーム全員で必ず現場で実践し、管理監督者はそれが守られているかチェックすることが重要です。
4RKYTの体験談と取り組みのヒント
最後に、4RKYTをおこなった実際の体験談をご紹介します。あるトレーナーは、トヨタに入社した当時は4RKYTにしぶしぶ取り組んでいたそうです。なぜなら、当時の題材は安全部署から送られてくるイラストで、自分が普段おこなっている作業との違いやイラストのわかりづらさなどを感じていたからです。そのため自分事に置き換えることができず、なかなか意欲的になれませんでした。
当時は危険予知能力が低かったと話すトレーナーですが、長く現場で働いていると小さなケガやヒヤリを経験することもあったそうです。そのため、「自分はもちろん、他のメンバーにケガをさせてはいけない」と意識が変わっていきました。
そこで、自分事に置き換えるべく、イラストではなく自分たちがおこなっている作業を題材にしたところ、積極的に参加する人が増え、あらためて日常にも危険が潜んでいることに気付くことができました。これから4RKYTを導入しようとお考えの方は、実際の作業を撮影した短い動画から始めると、気付きが得られるはずです。
よくある質問(FAQ)
KYT実施に関して現場でよく寄せられる質問に、実務的な観点からお答えします。
Q1. KYTの実施にはどのくらいの時間が必要ですか?
A1. 標準的な4ラウンド法では30分程度が適切です。重要なのは時間の長さよりも、参加者全員が集中して取り組むことです。
Q2. KYTとリスクアセスメントはどう使い分ければいいですか?
A2. 両手法は目的と適用場面が異なります:
| 比較項目 | KYT | リスクアセスメント |
| 目的 | 危険感受性の向上・訓練 | リスクの定量評価・管理 |
| 実施タイミング | 日常的・作業前 | 計画段階・変更時 |
| 対象範囲 | 特定の作業・場面 | 作業全体・システム全体 |
| 参加者 | 現場作業者中心 | 管理者・専門家中心 |
| アウトプット | 行動目標・対策 | リスク評価表・改善計画 |
効果的な使い分け
- 日常的な危険予知:KYTで作業者の意識向上
- 設備導入・手順変更時:リスクアセスメントで体系的評価
- 継続的改善:両手法の結果を相互に活用
Q3. KYTの効果が実感できません。どう改善すればよいでしょうか?
A3. 効果が実感できない場合は、以下の点を見直してみましょう:
よくある課題と対策
- 形式的な実施
- 対策:実際のヒヤリハット事例を題材に使用
- 現場の写真を撮影して具体的な危険を可視化
- 参加者の消極性
- 対策:発言しやすい雰囲気づくり
- 「正解」を求めず、どんな意見も受け入れる姿勢
- マンネリ化
- 対策:手法のバリエーション導入
- 他部署との合同KYTで新しい視点を取り入れ
- フォローアップ不足
- 対策:決定した行動目標の実行状況を定期確認
- 効果測定の結果をフィードバック
まとめ
危険予知能力が欠けていると、ヒヤリとするような出来事が起こったり実際にケガをしてしまったりするなどの事故につながってしまう可能性があります。そのため、トヨタではメンバー全員の危険予知能力を高めるためのしくみとして、「4RKYT」を訓練として定期的におこなっています。
4RKYTはメンバーの危険に対する感度、想像力を高めることを目的としていますが、チーム活動を通して職場全体の安全意識を向上させるメリットもあります。現場の安全を徹底したいけど、何から取り組めばよいかわからないとお悩みの方は、ぜひ4RKYTを試してみてはいかがでしょうか。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
QCDSとは? 優先順位、QCDとの違い、Sの意味(Safety/Service)を解説
2025.12.22 -
改善が進む職場を作る!現場リーダーが実践すべき3つのポイントとは?
2025.09.19 -
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説
2025.04.11 -
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
2025.04.04 -
オフィスワークの「ムダ」を発見!視える化のコツと実践方法を解説
2025.03.28 -
トヨタ式改善で残業削減!銀行業務の効率化成功事例と実践ポイント
2025.03.28

PAGE
TOP