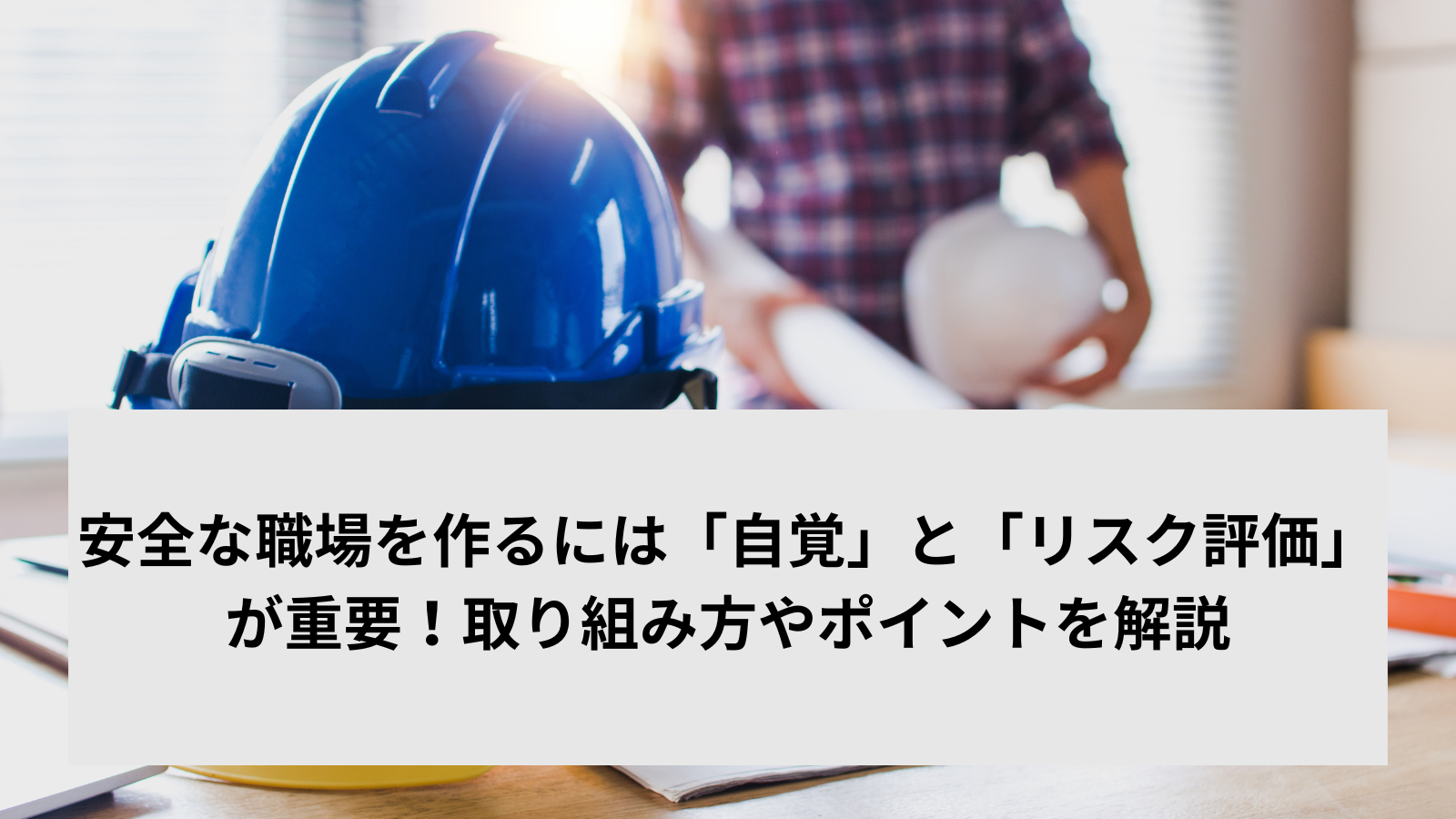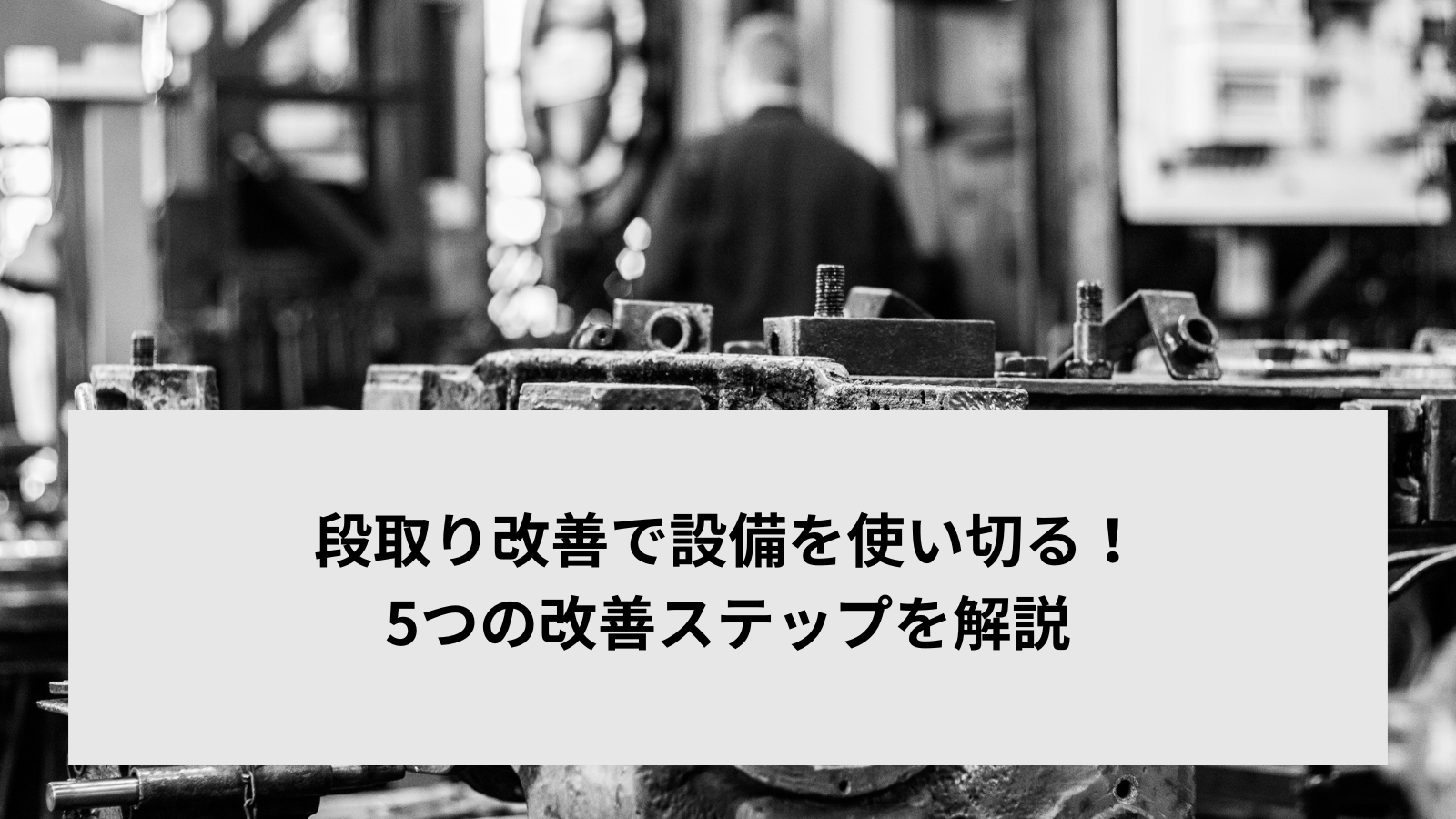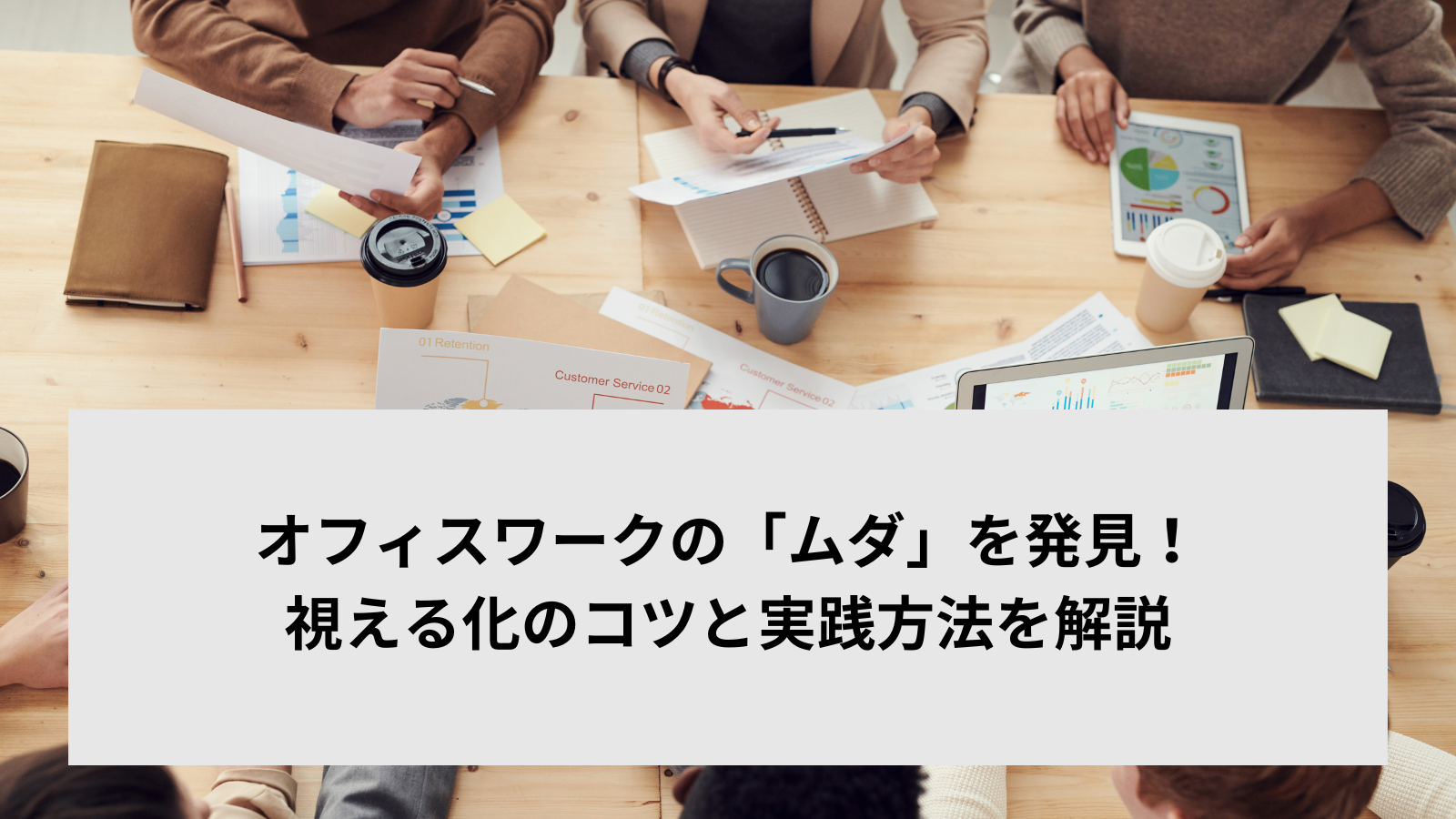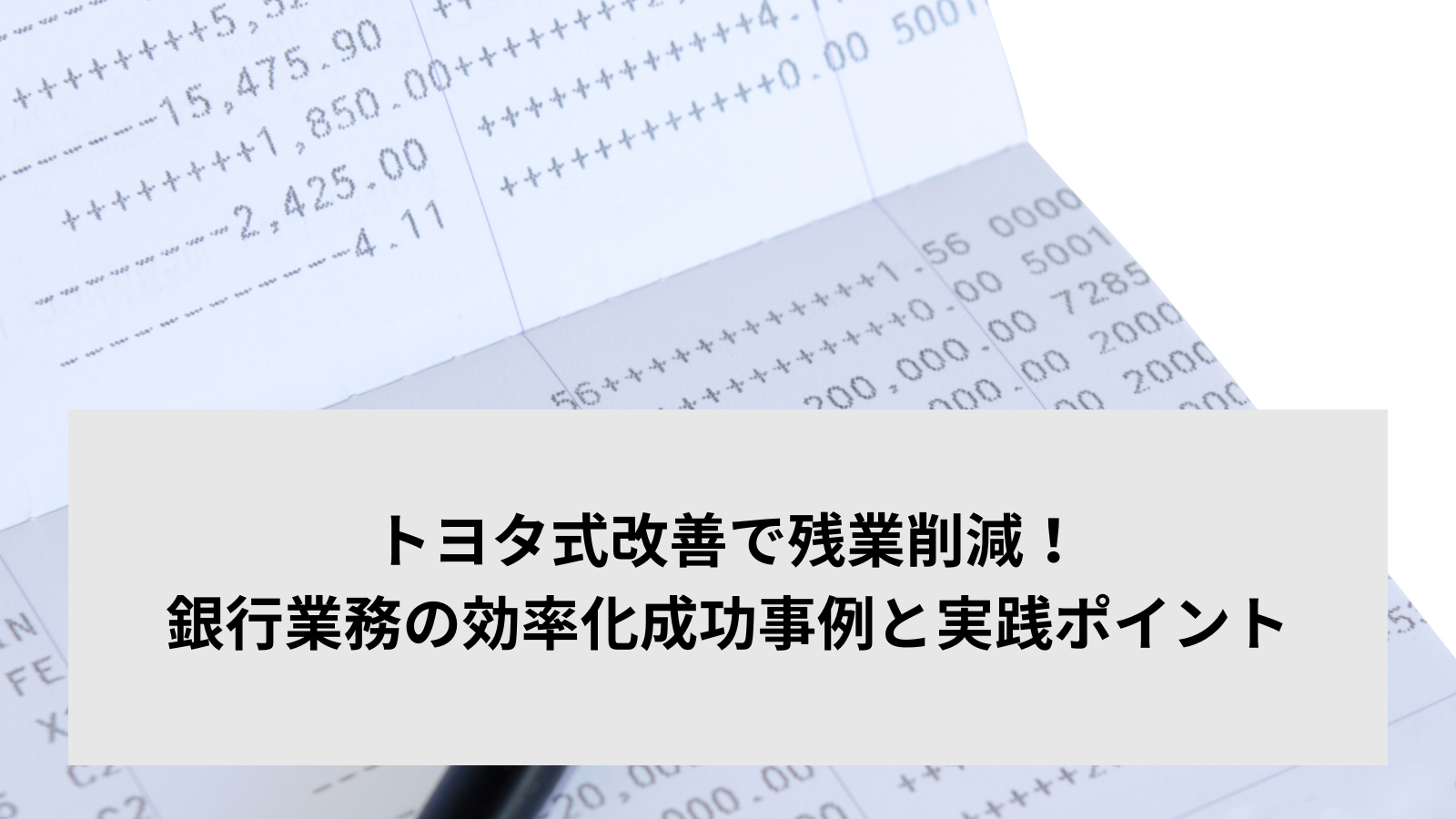現場力向上
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説

監修者
見城 吉昭
OJTソリューションズで、お客様の改善活動と人材育成をサポ―トするエグゼクティブトレーナーをしています。トヨタ自動車の機械加工にて39年の現場経験を積み、OJTソリューションズに入社しました。趣味の読書や旅行で自分の世界を広げながら、現場で働く人の声を大事に「働く人の心のための改善」に日々取り組んでいます。
労災による痛ましい事故で亡くなる人は、年間で755名(2023年)にものぼるといわれています。単純計算で毎日2人以上が亡くなっていることになります。
どの職場でも、「安全第一」と大きく掲げてあることがほとんどですが、「本当に実践」されている職場はどれほどでしょうか。本記事では、トヨタの安全活動を参考に、安全な職場作りに欠かせない「自覚」と「リスク評価」について解説します。
安全活動のよくある実態
「安全第一」を徹底できていない理由は「安全第一を優先すると、生産性が落ちてしまうのではないか?」「ルールは決めてやっているが、これ以上どうやればよいのかわからない」ところにあると考える管理監督者は多いです。
また、現場の作業者が「安全活動は上からの押し付けだ」と、自分事にできていないこともあるでしょう。
実際の作業基準となる手順書やマニュアルを見てみても、品質や生産性については書かれていますが、安全に対しては書かれていない、というのが多くの職場の現状です。
保護具を例に挙げると、軍手を保護具として使用している職場も多くみられますが、軍手では、いざというときに身を守ることができません。
鉄板や切粉を扱う職場では、切創対策用の手袋が必要です。作業の危険度に合わせて選定し、もし切れる所を触っても保護できるものを保護具と指定し、必ず使わせるようにする。このように作業者を守ることが、経営者や管理監督者の義務です。
災害が起きた際に、「たまたま今日だけ人が変わった」「決まりどおりやらせているはずだった」というのは言い訳で、原因は身を守れないものを保護具として与えていた管理監督者にあります。災害は偶然に起きるのではなく、必然的に起きます。
安全な職場の第一歩は「理解」から
トヨタの安全活動を推進していく最初のステップは「理解」から始まります。これは、「管理監督者と作業者が職場や作業の危険性を理解すること」です。職場のどこが危ない、どのような作業が危ない、ということをお互いに理解し、共有することが大切です。
管理監督者が部下にどのような作業をさせているのかを理解していなければ、安全な作業を提供させることはできません。もし大きな事故が発生した場合に、作業の危険性を理解せずに任せていた、といった場合は処罰の対象となるような責任もあるのです。死亡事故が起きてしまった場合は、会社の信用は失墜し、調査によって、何週間も生産が止まることもあります。
実際に発生する事故の多くは、事前に危険を理解し、共有できていれば防げるものです。危険予知をおこなう時間を惜しみ、危険な作業を無防備に実施してしまっていることが事故や災害につながります。立派な分厚い対策マニュアルを整備する前に、まずは心から職場の危険を「理解」し共有することから始めてください。
危険性を定量的に「リスク評価」する
次のポイントは、「リスク評価」です。厚生労働省が推奨しているOSHMSという「安全管理のしくみをつくる活動」のなかにも、「リスクアセスメント」という項目があります。
「リスクアセスメント」とは、作業の危険性をリスクとして評価し、それを改善してリスクを低減する活動のことです。作業の危険性を、経験や感性で評価するのではなく、誰もが客観的にわかるよう、リスクとして定量的に評価することが重要です。
管理監督者は、部下に絶対ケガをさせない思いで、作業者は、絶対ケガをしない思いで、安全に取り組むことが大切です。管理監督者と作業者がともに、各作業をリスク評価によって定量的にリスクを「自覚」することが大切です。
リスク評価の事例
多くの企業は作業のなかで一番危険と思われる作業だけに対してリスク評価をおこないますが、トヨタの場合は、作業の「すべて」の手順に対してリスク評価をおこなっています。
例えば、「10キロの荷物を台車に載せ、運搬し、棚に収納する」という作業を考えてみます。
一般的なリスク評価の場合では、一番危険な「棚に収納する」という作業だけを選定し、下記のように評価することが多いです。
・作業の頻度では、毎日2度運搬するので5点
・10㎏の荷物を腰の高さの棚に置くので、ケガのレベルは「ギックリ腰になる」恐れがあるので6点
・ケガの発生する危険性は、何も対策されていなく人任せなので8点
合計19点で、高度の危険作業となります。
一方で、トヨタがおこなうリスク評価では、作業のそれぞれの手順をリスク評価します。この場合では、「①台車に載せる」「②運搬する」「③棚に収納する」それぞれを評価します。
①10㎏の荷物を台車に乗せる
・頻度は毎日2度乗せるので5点
・ケガのレベルは「ギックリ腰になる」恐れがあるので不休災害で6点
・発生頻度は対策が無く、人任せなので8点
①は合計19点で、高度の危険作業です。
②台車を運搬する
・頻度は毎日2度乗せるで5点
・ケガのレベルは、「台車が通路の凸にぶつかり足を打撲する」恐れがあるから2点
・ケガの発生頻度は対策されていないので8点
②は合計15点で、中度の危険作業です。
③10㎏の荷物を棚に収納する
・作業の頻度では、毎日2度運搬するので5点
・10㎏の荷物を腰の高さの棚に置くので、ケガのレベルは「ギックリ腰になる」恐れがあるので6点
・ケガの発生する危険性は、何も対策されていなく人任せなので8点
③は合計19点で、高度の危険作業です。
この事例のように、作業には作業の手順があり、それぞれの手順のなかにも大きなリスクが潜んでいます。そのため、作業の中の「一番危険な部分」だけに注意すればいいというわけではありません。
あくまで目的は安全であり、一部分にだけ注目し点数をつけたから大丈夫、ではなく作業全体で考えることが大切です。
まとめ
今回説明したとおり、安全確保は経営者や管理監督者の責務です。まずは職場の危険を理解し、その危険を管理監督者と作業者で共有することから始めます。
また、「リスク評価」をおこなうことで、定量的に作業の危険を把握して、それを管理監督者と作業者それぞれが「自覚」することが、安全な職場作りのために有効な手段となります。
特に昔と今は安全作業の基準が違います。昔は高速で回転する製品に直接手を出すことが普通の場合もありましたが、現在は巻き込まれリスクでNGの場合がほとんどです。年齢の高いベテラン社員の方の納得度を高める為にも数値で危険度を表すことは役に立ちます。
紹介した方法を実践して、安全な職場作りに取り組んでみてください。
無料資料ダウンロード
面白いほどムダが見つかる
トヨタ式
「7つのムダ」
RELATION
関連記事
-
QCDSとは? 優先順位、QCDとの違い、Sの意味(Safety/Service)を解説
2025.12.22 -
改善が進む職場を作る!現場リーダーが実践すべき3つのポイントとは?
2025.09.19 -
安全な職場を作るには「自覚」と「リスク評価」が重要!取り組み方やポイントを解説
2025.04.11 -
段取り改善で設備を使い切る!5つの改善ステップを解説
2025.04.04 -
オフィスワークの「ムダ」を発見!視える化のコツと実践方法を解説
2025.03.28 -
トヨタ式改善で残業削減!銀行業務の効率化成功事例と実践ポイント
2025.03.28

PAGE
TOP